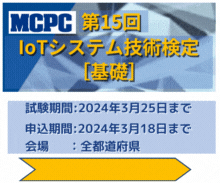IEICE ICT PIONEERS WEBINARシリーズ~第46弾~
無料
主催:(一社)電子情報通信学会サービス委員会
非線形信号処理からAIへ
―40年前の研究が今活きる―
荒川 薫(明治大学)
【開催日時】2023年12月19日(火)15:00~16:00
講演内容
今から40年ほど前、本講演者は非線形信号処理の研究を開始した。この研究は、雑音で不鮮明になった画像に対して何が映っているのか人が認識できるように、計算機処理により雑音劣化画像から、エッジ情報を損なうことなく、真の画像信号を推定しようとするものである。それから間もなく、第二次AIブームが起こり、この研究はニューラルネットワーク型信号処理に繋がった。その後、対話型進化計算を導入して、人の好みや感性を考慮した画像処理の研究となった。本講演では、雑音除去から始まり、人の感性をも考慮することになった非線形信号処理の研究を紹介する。また、40年前に提案した非線形信号処理の手法が、第三次AIブームを支える深層学習の重要技術であるresidual networkに相当するものになっていることもお話しする。
田口亮副会長からの紹介文
荒川薫先生は40年前に非線形ディジタル信号処理の研究を始められた我が国のパイオニアであり、その後、ニューラルネットやファジィ論理と繋げることで知的信号処理という新しいカテゴリーを生み出しました。現在は、人の感性を画像・音響処理に考慮するため深層学習を用いた研究を行っていて、知覚情報処理という新しい研究のトレンドを示してくれています。また、荒川先生の本会における調査理事等でのご貢献は当然のこと、社会的なご貢献も顕著です。長年にわたり、総務省・電気通信紛争処理委員会及び情報通信審議会の審議に携わり、特に電気通信紛争処理委員会では委員長代理を務め、多岐にわたる紛争事案等の解決を通じて情報通信の健全な発達に多大な貢献されたことから令和5年度「情報月間」総務大臣表彰を受賞されました。そして、2014年には日本学術会議会員も務めらました。
講演では、40年前に非線形ディジタル信号処理の研究を始められてから、その後、ニューラルネット、ファジィ論理、AI、そして人の感性を研究に融合させることで、常に新しい研究スタイルを追求されてきたことについてのお話を頂きます。様々な分野の研究者、そして、「新しい研究の方向性を切り開く」という観点から、教育に携わる多くの方々にも、ご聴講いただければと思います。
講師略歴

荒川 薫
1980年東大・工・電子卒、1986年同大学院博士課程修了。この間、カリフォルニア工大留学。工学博士。東大工学部助手を経て、1989年明治大学理工学部専任講師、1992年同助教授、1998年同教授、2013年同大学総合数理学部教授、2017年同学部長、現在に至る。専門は、知覚情報処理。2005年電子情報通信学会論文賞、2021年度SCAT会長大賞、令和5年度「情報月間」総務大臣表彰受賞。電子情報通信学会フェロー。