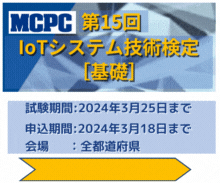ジャンル別 小特集
| Vol.107(2024) | ||
|---|---|---|
| 3月号 | 小特集 AIチップに向けた不揮発性メモリ技術とその展望 | |
| 小特集編集にあたって | 開 達郎 | |
| 不揮発性メモリを用いたニューロモルフィックAIハードウェアの最新技術と今後の展望 | 野村 修、森江 隆 | |
| 三次元フラッシュメモリ技術とニューラルネットワーク応用 | 三谷 祐一郎 | |
| 金属酸化物系シナプス素子のニューラルネット回路応用 | 丸亀 孝生、水島 公一、野村 久美子、西 義史 | |
| 生体神経機能を模倣する人工シナプスメモリスタ素子 | 酒井 朗 | |
| 強誘電体メモリの特徴と技術の進展 | 酒井 滋樹、高橋 光恵 | |
| スピントロニクス技術の進展とMRAM,論理演算素子への応用 | 與田 博明 | |
| 相転移材料の最新動向とニューロモルフィックデバイスへの応用 | 双 逸、姜 信英、須藤 祐司 | |
| 粘菌に触発された組合せ最適化計算機「電子アメーバ」とその記憶機能 | 葛西 誠也、青野 真士 | |
| 2月号 | 小特集 自動運転を支える情報通信技術の最新動向 | |
| 小特集編集にあたって | 松本 敦 | |
| 完全自動運転社会実現に向けた技術開発動向と課題 | 菅野 敦史 | |
| コネクテッド(V2X)技術の最新動向 | 熱田 隆 | |
| 自動運転を支えるセンシング技術の最新動向 | 伊東 敏夫 | |
| 車載光ネットワークの最新動向 | 高橋 亮、岩瀬 正幸、津田 裕之 | |
| 自動運転を支えるEMC設計評価技術 | 和田 修己 | |
| 1月号 | 小特集 通信障害と社会 | |
| 小特集編集にあたって | 石橋 圭介 | |
| 通信障害と社会 | 谷脇 康彦 | |
| 「ライフライン」としての次世代サイバーインフラの実現に向けて | 中尾 彰宏 | |
| 通信障害と報道 | 堀越 功 | |
| Vol.86(2003) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 小特集発行にあたって | 岩間一雄 |
| 1.P vs. NP 問題−解決へのはるかなる道− | 天野一幸 | |
| 2.ホーン理論と推論問題 | 牧野和久 | |
| 3.データ検索のためのコンパクトなデータ構造 | 定兼邦彦 | |
| 4.列挙アルゴリズムに関する最近の話題 | 宇野毅明 | |
| 8月号 | 小特集発行にあたって | 伊藤康之 |
| 1.次世代産業基盤を支えるフェムト秒テクノロジーの動向 | 中沢正隆 | |
| 2−1 超高速OTDM伝送技術 | 中沢正隆 | |
| 2−2 超高速光デバイス基礎技術 | 渡辺正信、秋本良一、板谷太郎、河島整、土田英実 | |
| 2−3 超高速全光スイッチ開発の現状と課題 | 石川浩、田島一人 | |
| 3−1 フェムト秒高輝度X線パルス発生装置 | 鳥塚健二、酒井文雄 | |
| 3−2 半導体パルス光源及び圧縮デバイス | 小川洋、李英根 | |
| 4−1 フェムト秒レーザを用いたナノ構造の観察・制御・加工 | 藤田克昌 | |
| 4−1フェムト秒レーザを用いたナノ構造の観察・制御・加工 | 河田聡、高田健治 | |
| 4−2 フェムト秒パルスレーザを用いた超高速分光 | 小林孝嘉 | |
| 4−3 フェムト秒光パルスの時間・周波数関係を利用した空間精密計測 | 美濃島薫 | |
| 3月号 | 小特集発行にあたって | 白石智 |
| 1−1 インターネットの歩み−その誕生と歩み,そして,日本における発展− | 村井純 | |
| 1−2 インターネットを構成する技術 | 太田昌孝 | |
| 1−3 モバイルインターネットの発展 | 石川憲洋、高橋修 | |
| 2−1 インタラクティブ通信サービス | 松田正宏、松倉隆一 | |
| 2−2−1 ユビキタスネットワーク | 塚本昌彦、西尾章治郎、宮原秀夫 | |
| 2−2−2 ユビキタスサービス | 今井和雄、山崎憲一 | |
| 2−3 CDNと通信・放送融合 | 奥村康行、青柳慎一、篠原弘道 | |
| 2−4 衛星を利用したインターネット | 河合宣行、長谷川亨 |
| Vol.85(2002) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 小特集発行にあたって | 今井浩 |
| 1.量子情報科学の来し方行く末 | 長岡浩司 | |
| 2.量子情報科学入門 | 松本啓史 | |
| 3.量子通信路符号化−Holevoの主題と変奏− | 藤原彰夫 | |
| 4.量子誤り訂正とエンタングルメント純粋化 | 松本隆太郎 | |
| 5.量子情報伝送容量 | 浜田充 | |
| 6.量子系の統計的推測(理論と応用) | 林正人 | |
| 7.光量子暗号システム | 南部芳弘、富田章久 | |
| 8.量子公開鍵暗号 | 田中圭介、岡本龍明 | |
| 9.量子コンピュータ科学入門 | 岩間一雄、山下茂 | |
| 3月号 | 小特集発行にあたって | 後藤敏行 |
| 1.総論−21世紀を迎えた情報考古学− | 堅田直 | |
| 2−1 様々な年代推定法−その原理と分類− | 松浦秀治 | |
| 2−2 鉛同位体比による青銅器の鉛産地推定をめぐって | 新井宏 | |
| 2−3 著者を探る古文書の計量分析 | 村上征勝 | |
| 3−1 コンピュータを利用した遺跡・文化資産の復元 | 門林理恵子、金谷一朗、千原国宏 | |
| 3−2 遺物・遺構の三次元計測と認識 | 佐藤宏介、塚本敏夫 | |
| 3−3 考古学データベースの現状と課題 | 宝珍輝尚@都司達夫 | |
| 3−4 地理情報システムによる遺跡データベースの構築 | 横山隆三、千葉史 | |
| 4−1 シミュレーションによる遺跡分布の推定 | 及川昭文 | |
| 4−2 人口考古学におけるシステムダイナミックス手法の応用 | 原俊彦 | |
| 5−1 発掘現場におけるリアルタイムアーカイビングへの期待 | 三宮健、植村俊亮 | |
| 5−2 コンピュータに支えられる考古学の課題 | 植木武 |
| Vol.84(2001) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 小特集発行にあたって | 本城和彦 |
| 1.総論−システムLSIの可能性と課題− | 黒田忠広 | |
| 2−1 ゲーム機向けシステムLSI | 斎藤光男、田胡治之、岡田豊史 | |
| 2−2 Bluetooth応用システムLSI | 高柳俊成、羽鳥文敏 | |
| 2−3 DVD用システムLSI | 清家忠義、秋山利秀、書上透、田村裕吏、高橋利彦、飯島行雄、豊蔵真木 | |
| 3−1 システムLSIを支えるデバイス,プロセス技術 | 池田修二、三井泰裕、尾内享裕、徳永尚文 | |
| 3−2 デシミクロンCMOSシステムLSIの低消費電力技術とチップアーキテクチャ | 水野正之、相本代志治 | |
| 2月号 | 5.無線アクセス技術 | 守倉正博、梅比良正弘、阿部宗男 |
| 6.モバイルアクセス技術 | 尾上誠蔵、山尾泰 | |
| 7.衛星通信システムを用いたアクセス技術 | 門脇直人、村田孝雄 | |
| 小特集発行にあたって | 市川弘幸 | |
| 1.アクセスネットワークの現状と将来展望 | 三木哲也、篠原弘道 | |
| 2.xDSLアクセス技術 | 山野誠一、堺和則、三好清司、松本一也 | |
| 3.光アクセス技術 | 渡辺隆市、山口一雄 | |
| 4.CATVアクセス技術 | 安川交二、北川和雄、伴泰次 |
| Vol.83(2000) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 白井宏 |
| 1−1 ITSの意義と基本概念 | 高羽禎雄 | |
| 1−2 システムアーキテクチャ,プラットホーム | 藤井治樹 | |
| 1−3 ITSの歴史と情報通信 | 津川定之 | |
| 2−1 現行の日本におけるプロジェクト | 羽鳥光俊 | |
| 2−2 標準化動向 | 藤井健 | |
| 2−3 ITSプロジェクトの国際動向 | 石太郎 | |
| 3−1 体系化,研究活動,セミナーなどの啓蒙活動 | 中川正雄 | |
| 3−2 ITSと学会とのかかわり,学会としての貢献,他学会のITSに関する活動状況 | 河野隆二 | |
| 4.国内各組織における研究開発活動 | 長谷川孝明 | |
| 5−1 自動車産業に与えるITSのインパクト | 榊原清則 | |
| 5−2 21世紀へ向けた走行支援道路システムについて | 山内照夫 | |
| 2月号 | 2−3 電子マネー | 岡本龍明 |
| 2−4 インターネットとセキュリティ | 佐々木良一 | |
| 2−5 公平性保証とプライバシー保護 | 佐古和恵 | |
| 2−6 コンテンツ配信と不正コピー防止 | 遠藤直樹、小出昭夫 | |
| 2−7 遠隔医療と電子カルテ | 喜多紘一 | |
| 2−8 ワンストップサービス | 山崎重一郎 | |
| 小特集発行にあたって | 岡崎彰夫 | |
| 1.概論 | 辻井重男 | |
| 2−1 次世代ICカードシステムと暗号技術 | 大山永昭 | |
| 2−2 暗号技術と電子商取引−米国の現状− | 前川徹 |
| Vol.82(1999) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 井波大二郎 |
| 1.フォトニックネットワークの展望 | 青山友紀 | |
| 2−1 DWDM用光デバイスの研究開発動向 | 姫野明、宮哲雄 | |
| 2−2 広帯域光増幅器 | 大越春喜 | |
| 2−3 WDM用半導体光源 | 山口昌幸 | |
| 2−4 ファイバグレーティング | 金森弘雄 | |
| 3−1 フォトニックネットワーク時代の光デバイス−システムが描くイメージ− | 桑原秀夫 | |
| 3−2 アレー導波路回折格子(AWG)デバイス | 鈴木扇太 | |
| 3−3 ハイブリッド光集積デバイス | 東盛裕一、加藤邦治 | |
| 3−4 導波路型光スイッチ | 岡山秀彰 | |
| 3−5 半導体光増幅器を用いた全光型光波長変換技術 | 田島一人 | |
| 3−6 波長可変AOフィルタ | 清野実 | |
| 2月号 | 小特集発行にあたって | 西園敏弘 |
| 1.移動通信の変遷と展望 | 羽鳥光俊 | |
| 2.IMT−2000のサービスとシステム要求条件 | 田原康生、歌野孝法、冲中秀夫、丸山辰夫 | |
| 3.IMT−2000標準化の状況 | 佐々木秋穗、山本浩治 | |
| 4.IMT−2000の無線伝送方式 | 岡坂定篤、古谷之綱、渡辺文夫 | |
| 5.W-CDMAの無線実験 | 尾上誠蔵、武内良男 | |
| 6.無線端末技術 | 本間光一、Erkki TIITTANEN、浜田国広 | |
| 7.IMT−2000ネットワークアーキテクチャ | 沢田寛、有馬秀平 | |
| 8.移動通信ネットワークの進展 | 高畠達美 |
| Vol.81(1998) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 仙石正和 |
| 1.新世紀における空間データ基盤の役割 | 伊理正夫 | |
| 2.空間情報科学の展開 | 岡部篤行 | |
| 3.道路管理システムと空間データ | 斎藤修平、東明佐久良、岡田英樹 | |
| 4.郵政事業と国土空間データ基盤について | 佐野設夫、磯部俊吉 | |
| 5.マーケティング分野での空間データ活用 | 足立弘 | |
| 6.空間データとモバイルコミュニケーション | 篠田庄司、仙石正和 | |
| 2月号 | 小特集発行にあたって | 佐藤誠 |
| 1.医用生体工学の展望 | 斎藤正男 | |
| 2.磁気で何がどこまでわかるか | 小谷誠 | |
| 3.光で何がどこまでわかるか | 金井寛 | |
| 4.細胞の生きのよさ−細胞の活動状態を測る− | 神保泰彦 | |
| 5.生体高分子と微細加工技術 | 鷲津正夫 | |
| 6.生物ラジカルと生体情報計測 | 鎌田仁、大矢博昭 | |
| 7.人の感覚の代用どこまで | 伊福部達 | |
| 8.バーチャルリアリティと生体 | 舘すすむ |
| Vol.80(1997) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 永沼充 |
| 1.総論−化合物半導体デバイスの魅力− | 神谷武志 | |
| 2.通信用光デバイス | 吉田淳一、板屋義夫 | |
| 3−1 面発行レーザ | 伊賀健一、小山二三夫 | |
| 3−2 可視光半導体レーザ | 波多腰玄一 | |
| 4.マイクロ波ミリ波デバイス | 本城和彦 | |
| 5.超高速低消費電力ディジタルIC | 佐野栄一 | |
| 6−1 超高性能半導体レーザに向けて | 石川浩 | |
| 6−2 マイクロ波ホトニクスデバイス | 佐藤憲史 | |
| 6−3 半導体ナノ構造の電子デバイス応用の展望 | 榊裕之 | |
| 2月号 | 小特集発行にあたって | 新津善弘 |
| 1.総論 | 宮原秀夫 | |
| 2.インターネットにおける通信技術の検証 | 村井純、植原啓介 | |
| 3.インターネットにおけるネットワーク管理技術の検証 | 浅見徹 | |
| 4.インターネットにおけるセキュリティ技術の検証 | 菊池浩明 | |
| 5.インターネットにおけるビジネス利用の可能性の検証 | 会津泉 | |
| 6.多様化するネットワークインフラへの適用性の検証 | 斎藤孝文 |
| Vol.79(1996) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 大石進一 |
| 1.総論−電子情報通信と数字のかかわり,どう数学を学ぶか− | 伊理正夫 | |
| 2.情報幾何 | 甘利俊一 | |
| 3.関数解析と逆問題 | 小川英光 | |
| 4.電子情報通信とグラフ・ネットワーク理論 | 篠田庄司 | |
| 5.VLSI設計と数学 | 白川功 | |
| 6.回路理論と数学 | 西哲生 | |
| 7.ロボットの手先技量と非線形回路理論 | 有本卓 | |
| 8.非線形関数解析とその電子情報通信システムへの応用 | 堀内和夫 | |
| 9.精度保証付き数値解析にまつわるできたてほやほやの話 | 大石進一 | |
| 10.複素関数論とz変換 | 板倉文忠 | |
| 11.だ円曲線と通信工学 | 笠原正雄 | |
| 12.符号化技術と情報数理 | 平沢茂一 | |
| 13.記数法・確率・情報・符号化 | 韓太舜 | |
| 14.パーソナル通信と直交性 | 中川正雄、真田幸俊 | |
| 15.光ソリトンの数学 | 長谷川晃 | |
| 16.幾何学と視覚情報処理 | 杉原厚吉 | |
| 17.電子情報通信と離散数学 | 渡辺治 | |
| 18.微分方程式とシミュレーション | 浅井秀樹 | |
| 19.フーリエ解析とウェーブレット−信号処理への応用− | 斉藤隆弘 | |
| 20.統計−パターン認識から社会科学まで− | 関田巌、栗田多喜夫 | |
| 2月号 | 2.暗号・認証技術 | 松井充 |
| 3.ネットワークセキュリティ技術−インターネットファイアウォール現状と展望− | 則房雅也、廬偉 | |
| 4.システムセキュリティ技術 | 中野秀男 | |
| 5.セキュリティ応用−ディジタルキャッシュ− | 太田和夫 | |
| 6.情報セキュリティをめぐる法的話題 | 辛島睦 | |
| 小特集発行にあたって | 木戸出正継 | |
| 1.総論−文明構造・文化概念の変容と情報セキュリティ− | 辻井重男 |
| Vol.78(1995) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 河合直行 |
| 1.総論 | 小林駿介 | |
| 2−1−1 カラー受像管 | 福田久美雄 | |
| 2−1−2 カラーディスプレイ管 | 山口明雄 | |
| 2−1−3 電界放射ディスプレイ | 横尾邦義 | |
| 2−2 カラープラズマディスプレイ | 内池平樹 | |
| 2−3−1 TFTカラー液晶ディスプレイ | 金子節夫 | |
| 2−3−2 STNカラー液晶ディスプレイ | 渡辺拡 | |
| 2−3−3 反射型液晶ディスプレイ | 内田龍男 | |
| 2−3−4 強誘電性液晶ディスプレイ | 稲葉豊、神辺純一郎 | |
| 2−3−5 高分子分散型液晶ディスプレイ | 若林常生 | |
| 2−4 LEDフルカラーディスプレイ | 中村修二 | |
| 3−1 大画面ディスプレイ | 堀口圭介 | |
| 3−2 3次元画像ディスプレイ | 磯野春雄 | |
| 3−3 バーチャルリアリティ用ディスプレイ | 広瀬通孝 | |
| 4.映像ソフト技術者からみた期待 | 岸本登美夫 | |
| 2月号 | 小特集発行にあたって | 竹中豊文 |
| 1.パーソナル移動通信の展望 | 羽鳥光俊 | |
| 2−1 無線アクセス技術 | 藤野忠、田近寿夫 | |
| 2−2 セル構成技術 | 秦正治 | |
| 2−3 無線回線制御技術 | 赤岩芳彦 | |
| 3−1 パーソナル移動通信のためのインテリジェントネットワーク | 中島昭久 | |
| 3−2 パーソナル移動通信のためのソフトウェア | 飯田一朗 | |
| 4−1 パーソナル移動通信におけるメディア処理 | 森戸誠 | |
| 4−2 携帯情報端末のネットワーキング | 松本充司 | |
| 5−1 PHSの標準化動向と実用化実験の結果について | 飯田徳雄 | |
| 5−2 欧米における技術動向 | 本間光一、加藤修 |
| Vol.77(1994) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 石井六哉 |
| 1.生体の生理や機能をみる−生体情報の新たな可視化技術− | 宮川道夫 | |
| 2.地中をみる−遺跡探査− | 西村康、斎藤正徳、亀井宏行、荒井郁男、寺町康昌 | |
| 3.古くて見えなくなってしまったものをみる−文化財を科学の目でみる− | 田口勇 | |
| 4.目に見えない現象をみる−極限域光現象の画像化計測− | 土屋裕 | |
| 5.宇宙から電波で地球をみる−電波リモートセンシング− | 古浜洋治、岡本謙一 | |
| 6.電波観測により物理学の基礎法則を宇宙にみる−やはり本当だったクェーサーの“超光速現象”− | 大師堂経明 | |
| 7.流体の流れをみる−流れの可視化の最新動向− | 小林敏雄 | |
| 8.計算結果をみる−流れのシミュレーションとその可視化− | 桑原邦郎 | |
| 2月号 | 1−1 人工生命とは | 星野力 |
| 1−2 人工生命研究の現状−生命の複雑性の理論− | 田中博 | |
| 2−1 進化分子工学 | 伏見譲 | |
| 2−2 人工生命と生物の個体発生−機械と生気− | 土居洋文 | |
| 2−3 カオスによる複雑さと多様性の創発と進化 | 金子邦彦 | |
| 2−4 生態系と人工生命 | 徳永幸彦 | |
| 3−1 人工生命と虫型探索 | 伊庭斉志 | |
| 3−2 ジェネシスマシン−人工生命に基づく超並列計算機構− | 北野宏明 | |
| 3−3 自律ロボット・進化ロボット | 伊藤宏司 | |
| 小特集発行にあたって | 小川英光 |
| Vol.76(1993) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 今井元 |
| 1.はじめに | 嶋正利 | |
| 2.アーキテクチャ動向 | 徳田健 | |
| 3.高集積化動向 | 内山邦男 | |
| 4.1 ビデオシグナルプロセッサ(VSP)ULSIの高性能化 | 榎本忠儀、山品正勝 | |
| 4.2 インタフェース高速化 | 山田通裕 | |
| 5.低電圧化の動向 | 各務正一 | |
| 6.周辺回路の動向 | 森昭助 | |
| 7.マイクロプロセッサシステム開発環境の動向 | 小野定康、藤井哲郎 | |
| 8.1 ワークステーション | 下山健 | |
| 8.2 ロボット | 鞍掛三津雄 | |
| 8.3 伝送機器 | 塩浜二郎 | |
| 8.4 自動車 | 玉木一好、大倉勝徳 | |
| 8.5 AV機器 | 水口博 | |
| 8.6 家庭電化製品 | 寺井春夫 | |
| 2月号 | 3−1 ネットワークプランニングと通信行政 | 竹田義行 |
| 3−2 ネットワークプランニングと周波数有効利用 | 甕昭男 | |
| 3−3 コモンキャリアからみたネットワークプランニング | 加納貞彦 | |
| 3−4 国際網のネットワークプランニング | 松本潤 | |
| 3−5 VANにおけるネットワークプランニング | 三谷一二、加藤義文 | |
| 3−6 物流分野のネットワークプランニング | 高橋善彦 | |
| 3−7 企業内情報通信網のプランニング | 菅野実、西野誠一、佐藤勝三 | |
| 4−1 ネットワークプランニング技法 | 上田徹 | |
| 4−2 ネットワークプランニングツール | 川島幸之助、小林浩 | |
| 5−1 テレコミューティングと都市の変容 | 大西隆 | |
| 5−2 東京テレポートタウンにおける情報通信基盤の整備 | 相沢学 | |
| 6.21世紀へ向けた情報ネットワークプランニング | 安田靖彦 | |
| 小特集発行にあたって | 間瀬憲一 | |
| 1.情報ネットワークのプランニングとは−21世紀情報基盤のための長期的先行投資− | 辻井重男 | |
| 2.NETWORKS'92の話題から | 村野和雄、中条孝文、岡崎弘幸 |
| Vol.75(1992) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 宮坂栄一 |
| 1.DNAを通してヒトをみる | 長谷川政美 | |
| 2.類人猿を通してヒトの進化をみる | 鈴木晃 | |
| 3−1 ラジオアイソトープ(RI)法で脳の生理現象をみる | 舘野之男 | |
| 3−2 脳の構造をみる | 橋本隆裕、舘野之男 | |
| 3−3 脳の電気・磁気現象をみる | 橋本勲 | |
| 4−1 人の心の発達をみる | 無藤隆 | |
| 4−2 人の認知行動をみる | 海保博之 | |
| 5−1 番組を通して人をみる−日本企業の知的集団主義− | 相田洋 | |
| 5−2 物理学を通して人をみる−物理学と人間の視点における相似と相違− | 柘植俊一 | |
| 2月号 | 小特集発行にあたって | 川戸信明 |
| 1.スーパコンピュータのハードウェア | 内田啓一郎 | |
| 2−1 基本ソフトウェア | 竹永晋吉 | |
| 2−2 言語とその処理系 | 安村通晃 | |
| 3−1 連立一次方程式の標準解法 | 長谷川秀彦 | |
| 3−2 基本数学関数 | 浜田穂積 | |
| 4−1 化学分野における応用 | 長嶋雲兵 | |
| 4−2 原子力研究での利用 | 石黒美佐子 | |
| 4−3 電気系CADへの応用 | 井原茂男、蒲原史朗、鳥谷部達、横溝剛一 | |
| 4−4 投資工学への応用 | 吉越昌治、小泉博嗣 | |
| 4−5 自動車開発への応用 | 猪田克美 |
| Vol.74(1991) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 小特集発行にあたって | 荒川泰彦 |
| 1.総論 | 谷口研二、浜口智尋 | |
| 2−1 不純物シミュレーション | 西謙二、海本博之 | |
| 2−2 形状シミュレーション | 小谷教彦 | |
| 3−1 ドリフト・拡散法 | 福間雅夫 | |
| 3−2 緩和時間近似法 | 松沢一也 | |
| 3−3 モンテカルロ法による半導体デバイスのシミュレーション | 冨沢一隆 | |
| 3−4 量子効果デバイスシミュレーション | 富沢雅彰 | |
| 4.数値解析技術 | 佐藤成生、中山範明 | |
| 5.統合化とユーザフレンドリー化 | 増田弘生、鳥谷部達 | |
| 6.シミュレーション技術の将来展望 | 羽根邦夫 | |
| 3月号 | 「光ファイバ増幅」小特集について | 東野秀隆 |
| 1−1 概説 | 島田禎晉 | |
| 1−2 光ファイバ増幅の原理と課題 | 藤井陽一 | |
| 2−1 増幅用光ファイバの現状と動向 | 田中紘幸 | |
| 2−2 増幅用励起光源の現状と動向 | 川井義雄 | |
| 2−3 光ファイバ増幅器モジュール | 鈴木和宣 | |
| 3−1−1 IM-DD,コヒーレント光伝送系 | 若林博晴 | |
| 3−1−2 光ソリトン伝送系 | 中沢正隆 | |
| 3−2 多チャネル映像光分配システム | 米田悦吾 | |
| 2月号 | 「通信ソフトウェア」小特集について | 西園敏弘 |
| 1.通信ソフトウェアの特徴と課題 | 寺田浩詔 | |
| 2−1 モデルと仕様記述 | 白鳥則郎 | |
| 2−2 通信システムのプログラム構造 | 富田修二 | |
| 3−1 公衆網交換サービスのソフトウェア | 重松直樹、上坂久一 | |
| 3−2 私設網交換システムのソフトウェア | 石原伸一、玉木正伸、帆苅誠 | |
| 3−3 汎用計算機を例にとったOSI通信機能の実現技術 | 小森斉 | |
| 3−4 通信端末のソフトウェア | 尾崎英之 |