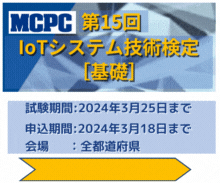IEICE ICT PIONEERS WEBINARシリーズ~第41弾~
無料
主催:(一社)電子情報通信学会サービス委員会
半導体光集積デバイス研究の40年
中野 義昭(東京大学 大学院工学系研究科 教授)
【開催日時】2023年8月25日(金)15:00~16:00
講演内容
1982年に大学院に入学した後、今日までの約40年間、半導体に基づく発光・光制御デバイス、光集積回路、太陽電池の研究、およびそれらを作製する基礎となるエピタキシャル成長・微細加工プロセス技術の研究に携わってきた経験をもとにお話ししたい。より具体的には、最初の10年は分布帰還型半導体レーザの研究、次の10年は有機金属気相エピタキシのメカニズム解明とモノリシック光集積回路作製への応用、その次の10年はデジタル光デバイス・回路の研究とフォトニックネットワークへの応用、最近の10年は新世代光通信、光コンピューティング、光センシングに向けた集積光デバイス・回路の研究、および化合物半導体高効率太陽電池の研究を行なってきた。この間、対象とする半導体は、GaAs系混晶、InP系混晶、GaN系混晶、シリコンと拡大し、結晶成長技術も液相エピタキシ、分子線エピタキシ、有機金属気相エピタキシと変遷してきた。今回の講演では、これまでの40年間を振り返って、何がうまく行ったか、何がうまく行かなかったかに着目し、皆様の参考にして頂けるようにお話ししたい。特に、中堅・若手研究者の皆様の将来に役立つメッセージを多く発することができればと思う。
川西哲也 エレクトロニクスソサイエティ会長からの紹介文
中野義昭先生は、長年にわたり一貫して光エレクトロニクス分野をリードしてこられました。その時々で重要となる応用分野を見据えて研究のトレンドをつくられてきました。通信、コンピューティング、エネルギーといった幅広い分野をターゲットとしつつ、高度なデバイス作製技術に裏打ちされた研究のスタイルには常々感銘を受けております。本会においては、エレクトロニクスソサイエティ会長、副会長などを歴任され、現在、監事をお務めです。今回のご講演では、中野先生の半世紀近くにわたる半導体光集積デバイス研究の歩みについてお話いただきます。多種多様な材料やプロセス技術を駆使し、各要素を集積化することで機能を発揮する集積デバイス分野を切り拓いてこられたご経験は、今後ますます大きな変化が求められる時代を担う若手研究者はもとより、後進指導にあたるベテラン研究者にとっても示唆に富むものと思います。
講師略歴

中野 義昭
1982年東大・工・電子卒、1984年同大学院修士課程了、1987年同博士課程了、工学博士。同年東大・工・電子助手、1988年同講師、1992年同助教授、2000年同教授、現在に至る。この間、1992年カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員助教授、2002-2012年東大・先端科学技術研究センター教授、2010-2012年同センター所長を歴任。電子情報通信学会功績賞、同学会エレクトロニクスソサイエティ賞、IPRM Award、応用物理学会光学論文賞、市村学術賞、産学官連携内閣総理大臣賞などを受賞。日本学術会議会員(第三部)、同電気電子工学委員会委員長、電子情報通信学会監事、同学会元副会長、同エレクトロニクスソサイエティ元会長、IEEEフェロー、IEEE前東京支部長、Opticaフェロー、エレクトロニクス実装学会前会長、応用物理学会フェロー、同学会元理事(APEX/JJAP誌編集長)、電気学会、レーザー学会、日本太陽光発電学会各会員。