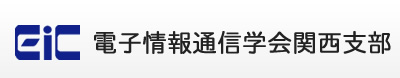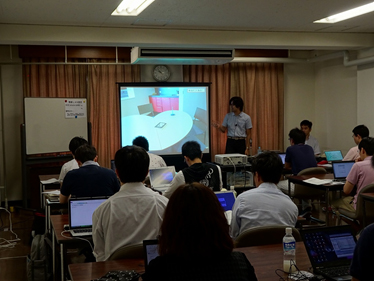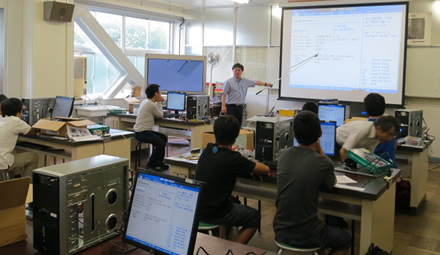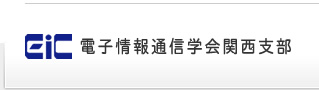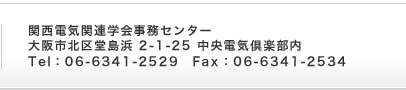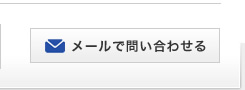トピックス
電子情報通信学会関西支部 イブニングセミナー
量子技術・NWの世界 ~技術概要・最新動向・社会実装~
| 日 時 | 1回目:2021年12月17日(金)、2回目:2022年1月21日(金)18時00分~20時00分 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
第1回(12/17) 18:00~18:05 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 18:05~19:55 「量子技術・NWの世界Ⅰ」 ~技術の概要と研究開発の最新動向~ KeyWord: 量子暗号、量子鍵配送(QKD)、量子インターネット 慶應義塾大学 理工学部電気情報工学科 教授 武岡 正裕 19:55~20:00 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 第2回(1/21) 18:00~18:05 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 18:05~19:55 「量子技術・NWの世界Ⅱ」 ~量子暗号の標準化と社会実装~ KeyWord: 量子暗号、量子鍵配送(QKD)、ITU-T、ETSI、ISO NICT 量子ICT協創センター 参事 釼吉 薫 19:55~20:00 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 |
| 要 旨 |
2021年度のイブニングセミナでは、「量子技術・NWの世界 ~技術概要・最新動向・社会実装~」と題し、2回シリーズで、量子技術の研究を行っている研究者よりご講演いただいた。 1回目では、量子暗号を始めとする量子通信技術の概要について述べ、また量子暗号の中核技術である量子鍵配送(QKD)の仕組みやネットワーク化、応用などについて、最新の研究開発動向も交えて解説いただいた。さらに、将来的に様々な量子技術を量子的に接続する量子インターネットの概念や技術課題、現状などについて解説いただいた。オンライン形式であったため参加者の反応が分かりにくい場面もあったが、質疑応答も活発に行われた。参加者からは、分かりやすいという反応が多かった。 2回目では、 QKDNに関するITU-T SG13ネットワークアーキテクチャ、ITU-T SG17 セキュリティ、ITU-TSG11 プロトコル等の標準化状況、ETSI/ISOで検討しているQKD装置の安全性評価について紹介いただき、これらの標準化仕様をベースに国内で構築を進めている量子暗号通信網について解説いただいた。参加者からは、標準化の取組の大切さ、意義について理解が深まったという反応が多かった。 新型コロナ対策としてオンライン講演が世の中においても定着し始めていること、夕方での開催という参加の容易性から、多数の方に参加頂き、参加者が大幅に向上した。年齢層では、若年層のみならず広い世代から参加いただいているように思える。 |
| 参加者(申込者) | 計155名(申込220名)(1回目83名、2回目72名参加) |
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
| 日 時 | 2021年11月17日(水) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | ZOOMによるオンライン開催 |
| 内 容 |
講師:白石 善明(しらいし よしあき) 神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 准教授
1.(9:40-11:10) 情報セキュリティの考え方 ・情報セキュリティとその対策 ・情報セキュリティの基本的問題 2.(11:20-12:45) アクセス制御の考え方 ・ユーザの認証 ・情報の保護 暗号技術の基礎 ・公開鍵暗号の原理 ・暗号で使われる数の世界 3.(13:45-15:15) ElGamal 暗号, Schnorr 署名 ・合同式,位数,原始元,フェルマーの定理 ・離散対数問題 ・ElGamal 暗号 ・Schnorr 署名 4.(15:20-16:50) セキュリティ設計の基礎 ・脅威分析 ・セキュリティ対策 テキスト:特になし(資料を事前に配布) 参考書:なし |
| 要 旨 | 本講座では,情報セキュリティの基本的な考え方から、盗聴・改ざん・偽造からデータを保護する暗号技術、公開鍵暗号と電子署名の解説が行われた。最近のセキュリティなどに関するトピックなども紹介されていたことから,受講生にとって有意義な講座であったと考えている。 |
| 参加者(申込者) | 16名 |
電子情報通信学会関西支部 一般講演会
「機械学習手法とDXの最新動向」
| 日 時 | 2021年9月24日(金) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
14:00~14:05 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 14:05~14:45 「ものづくり力を強化するIoT/AI活用 現場とデジタル技術の協調による改善加速」 住友電気工業株式会社 IoT研究開発センター センター長 高橋 覚氏 14:45~15:25 「エッジAIによる異常判断機能を搭載した無線振動センサモジュールの開発と回転機器予知保全ソリューション事例」 株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター 開発第一部 プロジェクトマネージャー 勝村 英則氏 15:25~15:35(休憩) 15:35~16:15 「先端計測と機械学習を融合する計測インフォマティクス -背景・目的と成果事例-」 大阪大学 産業科学研究所 教授 鷲尾 隆氏 16:15~16:55 「人間参加型機械学習による人とAIの協働問題解決」 京都大学 大学院 情報学研究科 知能情報学専攻 教授 鹿島 久嗣氏 16:55~17:00 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 |
| 要 旨 | コロナ禍の状況を鑑み、昨年同様にZOOMによるオンライン開催の運びとなりました。テーマとして「DX」とDXの中で重要な役割を果たす「機械学習手法」という、2つのキーワードに焦点を当て、企業から2名、大学より2名の方による、知見の深い内容の講演をいただきました。参加申込者が昨年を大幅に上回っており、また講演中の質疑も活発であり、今の時代ならではの幅広い情報を得られる良い機会となったと思われます。 |
| 参加者(申込者) | 申込者約200名/参加者171名 |
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2021年8月23日(月), 24日(火) 9:40~16:500 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
講師: 小枝正直(こえだ まさなお) 岡山県立大学 情報工学部 櫛田貴弘(くしだ たかひろ) 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは (9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理 など 【2日目】 1. 物体形状解析 (9:40-11:00) ・ラベリング、形状特徴の利用 2. 画像からの特徴抽出 (11:10-12:30) ・特徴点・局所特徴量の抽出 3. OpenCVを使った機械学習 (13:30-15:00) ・kNNなどのシンプルな機械学習手法 4. 演習 (15:10-16:50) ・課題は当日発表 テキスト:特になし(資料を事前に配布) 参考書: OpenCVによる画像処理入門:小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 OpenCVによるコンピュータビジョン・機械学習入門:中村恭之, 小枝正直, 上田悦子, 講談社 |
| 要 旨 | 本講座では,画像処理と機械学習に関する,基礎から応用までの解説と演習が行われた。1日目の講座内容としては主に画像処理であり,画像の読み込み,濃淡変換,フィルタ処理,二値化処理に関する解説及び演習が行われた。2日目の講座では,機械学習の基礎から,ディープラーニングを用いた画像分類の解説及び演習が行われた。本講座の受講生が少なかったこともあり,受講生と講師間で積極的な質疑が行われていたことから,受講生にとって有意義な二日間であったと考えている。 |
| 参加者(申込者) | 13名 |
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2021年5月7日(金)9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
講師:池田和司 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授 1.(9:40-11:10) イントロダクション 確率統計の基礎 2.(11:15-12:45) 分類問題に対する手法 ・ベイズ分類器 ・サポートベクターマシン 3.(13:45-15:15) 回帰問題に対する手法 ・線形回帰と正則化 ・ロジスティック回帰 4.(15:20-16:50) 最近の手法の紹介 ・ニューラルネットワーク ・ガウス過程 ・その他 テキスト:特になし 参考書: 杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
| 要 旨 | ビッグデータの解析に利用される機械学習について,その基礎となる考え方から応用例まで幅広い範囲に渡る講座が行われた。前半は主に,確率統計の基礎から機械学習の基礎理論まで,時折具体例を交えつつつ,初学者にもやさしい内容で解説された.後半では主に,より現実に即した使用例や,機械学習に関する最近のトレンドについても紹介された。オンライン開催であったが,多くの参加者があり,また,オンライン用に用意された資料や説明はわかりやすく,非常に充実した講義内容であった。 |
| 参加者(申込者) | 15名 |
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
| 日 時 | 2020年11月24日(火) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | ZOOMによるオンライン開催 |
| 内 容 |
講師:白石善明 神戸大学 大学院工学研究科電気電子工学専攻 准教授
1.(9:40-11:10) 情報セキュリティの考え方 ・情報セキュリティとその対策 ・情報セキュリティの基本的問題 2.(11:20-12:45) アクセス制御の考え方 ・ユーザの認証 ・情報の保護 3.(13:45-15:23) 暗号技術の基礎 ・公開鍵暗号の原理 ・暗号で使われる数の世界 ・ElGamal暗号、PKI ・位数、原始元、フェルマーの定理 ・離散対数問題 (15:33-15:48) ・PKI、ハッシュ関数 ・ディジタル署名 ・Schnorr署名 4.(16:00-16:50) セキュリティ設計の基礎 ・脅威分析 ・セキュリティ対策 ・デジタルテレビ ・ヘルスケア機器とクラウドサービス |
| 要 旨 |
導入部で「『つながる世界』だからこそ必要な危機感」と題した関連記事を例に脅威から情報を守ることの重要性を解説。続いて配布テキストの内容に沿って講義。中段で「サイバー人材13万人不足」と題した関連記事を例に、本業に加えてセキュリティを理解する10万人の人材を目標にすべきと訴えられた。また、国家が関与したサイバー攻撃を事例に、企業・個人を守る意識が「つながる世界」に必要であることを解説。セキュリティ専門を目指さずとも、基礎をもって現場に活かせる人材が求められるとも。続いて、テキスト内容に戻り講義。演習問題。 オンラインということもあり、残念ながら受講者の反応、意見を伺うことができなかったが、別紙のアンケートの通り、充実した内容であったと伺える。 |
| 参加者(申込者) | 11名(うち、学生10名 教員1名) |
|
講演会
電気三学会関西支部講演会
「Withコロナ時代の通信とアプリケーション」
| 日 時 | 2020年9月30日(木)14:00~17:00 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
14:00~14:05 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 14:05~14:45 「社会課題解決へ向けたニューノーマルにおけるICTの貢献」 西日本電信電話株式会社 ビジネスデザイン部 テックデザイン部門 部門長 本田 新九郎氏 14:45~15:25 「Withコロナにおける共創活動のオンラインシフト」 パナソニック株式会社 イノベーション戦略室 ワンダーLAB大阪 所長 福井 崇之氏 15:25~15:35 (休憩) 15:35~16:15 「電波COE研究開発プログラムの近況とオンラインでの活動事例」 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 波動工学研究所 所長 鈴木 義規氏 16:15~16:55 「Withコロナ時代のテレワークのあり方とセキュリティ」 立命館大学 情報理工学部 教授 上原 哲太郎 16:55~17:00 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部 |
| 要 旨 |
新型コロナウイスは、ほんの数か月で我々の生活様式を大きく変えました。一方で、通信技術が進歩していたことによって、在宅勤務やネット会議が比較的、速やかに導入することが出来ました。しかしながら、初めて使うアプリケーションに戸惑ったり、思うような機能が無いために不便を感じられた方も多くいらっしゃると思います。そこで今回は、コロナ時代だからこそ、ますます重要になる通信とアプリケーションに関して、知見の深い講師の方々にご講演をいただきました。 1講演目では、NTTが行う様々な新しいサービスやアプリケーションの紹介が行われた。2件目の講演では、パナソニックが進める共創活動と、コロナ禍における活動内容の変化などの説明があった。3講演目では、ATRが実施している電波COEの紹介と、オンラインでの講演会の開催結果や課題の話があった。最後の講演では、テレワークでのセキィリティのあり方について説明があった。 いずれの講演も、時節にあった内容であり、多くの方に興味を持っていただけた。 |
| 参加者(申込者) | 53名(87名)※担当者、事務局除く |
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2020年9月10日(木)、11日(金)9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | Zoomによるオンライン開催 |
| 内 容 |
講師: 小枝正直 岡山県立大学 情報工学部 准教授 大倉史生 大阪大学 情報科学研究科 准教授 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは (9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理 など 【2日目】 1. 物体形状解析 (9:40-11:00) ・ラベリング、形状特徴の利用 2. 画像からの特徴抽出 (11:10-12:30) ・特徴点・局所特徴量の抽出 3. OpenCVを使った機械学習 (13:30-15:00) ・kNNなどのシンプルな機械学習手法 4. 演習 (15:10-16:50) ・課題は当日発表 テキスト:事前配布 参考書: OpenCVによる画像処理入門:小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 OpenCVによるコンピュータービジョン・機械学習入門: 中村恭之, 小枝正直, 上田悦子, 講談社 |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリの一つであるOpenCVを用いて画像処理の基礎を学習し、実習を通してその理解を深めるための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理理論や実装方法について解説された。2日目は、物体形状解析や、OpenCVを使った機械学習など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者が画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する演習が行われた。今年度はコロナ渦の影響でZoomを用いたオンラインでの開催になったが、講師二人で対応することで、全体をとおして丁寧な指導を行うことができ、参加者の満足度が高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 1日目:20名、2日目:20名(20名) |
一般見学会記録
電気三学会関西支部 一般見学会
朝日放送テレビ株式会社
| 日 時 | 2019年12月5日(木) 13:30~17:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 朝日放送テレビ株式会社(大阪市福島区福島1-1-30) | ||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 |
我々の生活に非常に身近な存在であり、重要な社会インフラでもあるテレビ放送について、情報通信の観点から知る機会は非常に限られている中で、今回、朝日放送テレビ株式会社を訪問させて頂いた。 朝日放送テレビは大阪市中心部にあり、JR環状線福島駅から徒歩10分以内とアクセスが良く、当日は天候もよかったため、24名の参加者全員が遅刻もなく集まった。 見学会当日は、最初に朝日放送テレビにおける通信利用とファイルベースシステムの概要および見学スケジュールについて説明いただき、その後3班に分かれて各スタジオ(Aスタジオ、Cスタジオ)や回線センター、主調整室(マスター)、各副調整室(Cサブ、Gサブ)、報道フロア、ポストプロダクション設備、ライブラリ、中継ガレージの計10か所を見学した。 各所では各担当者から非常に丁寧で分かりやすい説明をいただき、それに対して見学者からも多くの質問があり活発な質疑応答が行われた。普段入ることのできないスタジオ、設備等や番組製作の様子を間近で見学することができ、最新の設備についての知識を得るとともに働く方々の熱意を肌で感じることができた。特に無線通信やネット(IP)の利用、ファイルベースシステムなど情報通信に関連した内容について詳しく説明をいただいた。非常に盛り沢山で濃密な見学内容であり、途中若干のスケジュールの遅延もあったが、各担当者の方々による調整のおかげで、最終的にはほぼスケジュール通りに見学を行うことができた。 企画/運営に関しては非常に好評であり、見学時間は75%が「適切」、難易度は83%が「適切」であり、有益度に至っては96%が「有益」と高い満足度であった。参加者からは「日ごろ見ることができないものを丁寧に解説していただいました」「非常に興味深い内容ばかりで楽しみながら見学できました」「すごく勉強になりました」等の意見も頂くなど、特に大きな課題は感じられなかった。 |
||||||||||
| 参加者(申込者) | 24名(24名) | ||||||||||
|
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
| 日 時 | 2019年11月26日(火) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 214号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) |
| 内 容 |
講師:白石善明 神戸大学 大学院工学研究科電気電子工学専攻 准教授
1.(9:40-11:10) 情報セキュリティの考え方 ・情報セキュリティとその対策 ・情報セキュリティの基本的問題 2.(11:15-12:45) アクセス制御の考え方 ・ユーザの認証 ・情報の保護 暗号技術の基礎 ・公開鍵暗号の原理 ・暗号で使われる数の世界 3.(13:45-15:15) ElGamal暗号、Schnorr署名 ・合同式、位数、原始元、フェルマーの定理 ・離散対数問題 ・ElGamai暗号 ・Schnorr署名 4.(15:20-16:50) セキュリティ設計の基礎 ・脅威分析 ・セキュリティ対策 |
| 要 旨 |
冒頭、自動車や過去の大規模インシデントの事例を紹介するとともに、なぜ脆弱性が起こるのか、脆弱性に他する攻撃の原理を解説された。 情報セキュリティに関する講義は、まずユーザの認証から始まり、公開鍵暗号、暗号技術の基礎、ElGamal暗号について、演習を交えながら進められた。 セキュリティ設計の基礎については、表を用いた方法論を交えて、脅威分析の重要性を説かれ、「スマートハウス」をモデルとしたシステムの基礎的なセキュリティ設計を演習形式で実施し講義を結ばれた。 出席者アンケート結果からも大変有意義な講義であったことがうかがえる。 |
| 参加者(申込者) | 7名(うち、学生5名 企業技術者1名 無回答1名) |
|
講演会
電気三学会関西支部講演会
IoTとモニタリングシステムを支える技術~サービス、セキュリティ、測位、無線について~
| 日 時 | 2019年9月20日(金) 14:00~17:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 |
様々な社会インフラがIoT技術の活用により徐々に進化している中、その進歩を支える技術について横断的に情報を得る機会は少なく本講演会を企画致しました。 本講演会では、IoTとモニタリングシステムを支える技術と題して、IoTを用いたサービス、測位技術、セキュリティ技術、無線技術と、4つの幅広い領域で活躍されている講師の方を産官学の分野からお招きして、最新動向を踏まえご講演を頂きました。 1講演目は、IoTを用いた様々なサービス事例について、株式会社オプテージより、ご講演を頂きました。 2講演目は、IoTのためのセキュリティ技術について、住友電気工業株式会社より、ご講演を頂き、IoTの利用者への加害リスク(生命・健康、経済活動、環境など)とその防護、検知、回復がポイントであるとのご紹介を頂きました。 3講演目は、IoTを代表するモニタリングシステムを支える測位技術とその適用事例について、産総研/筑波大学の蔵田武志先生よりご講演を頂き、多種測位技術の特質と建設・飲食分野における測位導入事例を基づくその費用対効果事例についてご紹介頂きました。 4講演目は、京都大学の原田博司先生よりIoTで活用されている様々な無線技術に関して、標準化や実用化も含めた内容でのご講演を頂きました。 各講演とも感心の高い分野ということもあり、聴講を頂いた一部の方には、座席の誘導やテキストの配布に苦慮するといった混み具合となる場面もありましたが、無事終了致しました。 |
||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 58名(68名) | ||||||||||||||
|
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2019年9月3日(火)、4日(水)9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 316号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) |
| 内 容 |
講師: 小枝正直 大阪電気通信大学総合情報学部 情報学科 准教授 大倉史生 大阪大学産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 助教 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは (9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理 など 【2日目】 1. 物体形状解析 (9:40-11:00) ・ラベリング、形状特徴の利用 2. 画像からの特徴抽出 (11:10-12:30) ・特徴点・局所特徴量の抽出 3. OpenCVを使った機械学習 (13:30-15:00) ・kNNなどのシンプルな機械学習手法 4. 演習 (15:10-16:50) ・課題は当日発表 テキスト:当日配布資料 参考書: OpenCVによる画像処理入門:小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 OpenCVによるコンピュータービジョン・機械学習入門: 中村恭之, 小枝正直, 上田悦子, 講談社 |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリの一つであるOpenCVを用いて画像処理の基礎を学習し、実習を通してその理解を深めるための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理理論や実装方法について解説された。2日目は、物体形状解析や、OpenCVを使った機械学習など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する演習が行われた。少人数の参加者に対して講師二人で対応することで、全体をとおして非常に丁寧な指導を行うことができ、参加者の満足度が非常に高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 1日目:8名、2日目:8名(8名) |
|
講演会記録
電子情報通信学会関西支部 中高生向け講演会
マイコンを使ってロボットカーを動かそう
| 日 時 | 2019年8月21日(水) 9:30~15:30、 22日(木) 9:30~15:30 |
|---|---|
| 場 所 | 明石工業高等専門学校 (兵庫県明石市) |
| 内 容 |
第一日目 令和元年8月21日(水) 9:30~10:10 受付、開講挨拶 10:10~10:30 講座の全体説明 10:30~12:00 マイクロビットコンピュータの基礎(講義形式) 13:0~15:30 マイクロビットコンピュータの基礎(演習形式) 第二日目 令和元年8月22日(木) 9:30~15:00 プログラミングとロボットカーの動作制御 15:00~15:30 修了証書授与、閉講挨拶 |
| 要 旨 |
本講演会の第一日目では、受付後、本講座共催の紹介と開校の挨拶を行った。マイコンやロボットカーについての全体説明を20分ほど行い、10:30からは、マイクロビットコンピュータのしくみについて説明を行った。午後の部は、LED点滅やモータ動作などマイコンの簡単な制御プログラムを演習形式で実施した。 第二日目では、第一日目に学習した基礎的なマイコン制御プログラムをロボットカーの動作制御用に発展させたプログラミング演習を実施した。モータ制御による前進、後退、右旋回、左旋回、LED点滅など動作確認を行った。15:00からは、学会の紹介と修了書の授与を実施した。 令和元年度の講演の応募者は小中学生のみで高校生の応募はなかった。また、女子は応募1名(参加者1名)のみであった。昨年度の結果(女子応募者ゼロ)と併せても、女子学生の参加を促す工夫が来年度以降必要と感じた。応募総数は定員の約2倍で抽選により受講者を決定した。参加者の多くは本校Web.を見ての参加であり、学会Web.を見ての参加者は1名であった。アンケートの結果、参加者の殆どが内容や使用した教材、総合的に大変良かったと回答しており、今後もこ小中高校生向けの積極的に講演会を開催したい。 |
| 参加者(申込者) | 小・中学生13名。(小学生高学年9名、中学生4名) |
|
ICT基礎講座記録
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2019年5月10日(金) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 316号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) |
| 内 容 |
講師:池田和司 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授 1.(9:40-11:10) イントロダクション 確率統計の基礎 2.(11:15-12:45) 分類問題に対する手法 ・ベイズ分類器 ・サポートベクターマシン 3.(13:45-15:15) 回帰問題に対する手法 ・線形回帰と正則化 ・ロジスティック回帰 4.(15:20-16:50) 最近の手法の紹介 ・ニューラルネットワーク ・ガウス過程 参考書: 杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
| 要 旨 | ビッグデータの解析に利用される機械学習について,その基礎となる考え方から応用例まで幅広い範囲に渡る講座が行われた。前半は主に,確率統計の基礎から機械学習の基礎理論まで,時折具体例を交えつつつ,初学者にもやさしい内容で解説された。後半では主に,より現実に即した使用例や,機械学習に関する最近のトレンドについても紹介された。多くの聴講者にご参加頂き,会場からの質問もあり,非常に充実した講義内容であった。 |
| 参加者(申込者) | 13名 |
|
電子情報通信学会関西支部 イブニングセミナー
クラウドAIサービスの動向と使い方 ~研究・開発への活用に向けて~
| 日 時 | 平成30年12月7日(金)18時00分~20時30分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 |
本セミナーでは、「クラウドAIサービスの動向と使い方 ~研究・開発への活用に向けて~」と題し、クラウドAIサービスを提供・活用する専門家の方々に講演いただいた。 1限目では、機械学習の研究活動を支えるAWSプラットフォームについてご講演いただいた。研究者が持つ典型的な課題をどう解決するかという視点で、AWSの特徴、サービス群についてご紹介頂いた後、具体的なデモ(SageMaker)を分かりやすく説明いただいた。 2限目では、IBM Watosonを用いた最新AI/データ活用技術と活用事例展開ついて、解説頂いた。特に、データ活用・AI活用のスタートにおける現場課題について留意すべきポイントやプロジェクトとしての考慮点等、実践的な知見が紹介された。 3限目では、Microsoft Azureの利用ユーザ(開発者)として、便利な機能の紹介やデモによる具体的なアプリ開発手順を説明頂いた。 夕方での開催という参加の容易性、また注目されている分野であるクラウドAIサービスを代表する3社のツールについての講演でもあり、多くの研究者・企業の開発者に参加頂いた。 また限られた時間ではあったが質疑も活発であり手ごたえは十分あったと考える。 次年度は、アンケート結果も踏まえ、より充実した企画とすることとしたい。 |
||||||||||
| 参加者(申込者) | 45名 | ||||||||||
|
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
| 日 時 | 2018年11月15日(木) 9:40~16:50 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 214号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||||||
| 内 容 |
講師:白石善明 神戸大学 大学院工学研究科電気電子工学専攻 准教授
|
||||||||||||||||||
| 要 旨 |
冒頭、最新のサイバー攻撃の現状を示しながら世界規模でのインシデント事例を紹介、現代社会生活における脆弱性とNICT等での対応状況を解説された。 情報セキュリティに関する講義は、まずユーザの認証から始まり、暗号技術の基礎、ElGamal暗号について、演習を交えながら進められた。 また、セキュリティ設計の基礎として、脅威分析を「ネットワークカメラ」を例に説明、その脅威からシステムを守る対策について講義された。その後「スマートハウス」をモデルとしたシステムの基礎的なセキュリティ設計を演習形式で実施、講義を結ばれた。 出席者アンケート結果からも大変有意義な講義であったことがうかがえる。 |
||||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 16名(うち学生6名 大学研究者5名 企業、他5名) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
電気三学会関西支部 一般見学会
関西電力グループ (株)エネゲート 千里丘事業所(吹田)
| 日 時 | 2018年11月8日(水) 13:30 ~ 16:50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | (株)エネゲート 千里丘事業所(吹田) | ||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 |
近年、IoTがキーワードとなる中、長年、電力業界を支える製造メーカとして創業100年以上の歴史があり、お客さまの電気ご使用量を30分ごとに計測・記録・通信できるスマートメータ500万台以上をはじめとする各電力設備の製造や、機器情報の遠隔収集・制御の取組みを行ってきた関西電力グループ (株)エネゲート 千里丘事業所を訪問した。 千里丘事業所が吹田市であり、JR京都線の千里丘駅から徒歩10分以内と比較的アクセスが良く、当日は天候もよかったため、19名の出席予定者のうち18名の参加者が集まった。 見学会当日は最初に事業所の概要を施設案内パンフレットと紹介動画を活用して効率的に説明し、その後2班に分かれてECOCUBE(計測システム事業部)、東館(制御機器事業部)、南館(トランス事業部)、スマートラボ(検証フィールド)の4つの屋内施設と、最後に合流して屋外設備(スマートグリッド設備、充電スポット)を見学した。 各施設では各施設担当者から分かりやすく説明をいただき、それに対して見学者からも多くの質問があり活発な質疑応答が行われた。スケジュールや移動は、見学担当者の方と調整しながら進めたため、最終的にはスケジュール通りに見学を行うことができた。 企画/運営に関しては概ね好評であり、見学時間は72%が「適切」、難易度は77%が「適切」であり、有益度に至っては100%が「有益」と高い満足度であった。参加者からは、「見慣れていない技術が多数あって面白かった。」「詳しくご説明いただいたので非常にわかりやすく、有意義な見学会でした」「プロの話に接して良かった」等の意見も頂くなど、特に大きな課題や反省点は感じられなかった。 |
||||||||||
| 参加者(申込者) | 18名(24名) | ||||||||||
|
電気三学会関西支部 専門講習会
宇宙航空分野の最新エレクトロニクス技術とビジネス動向 ~今、空が熱い!~
| 日 時 | 平成30年10月26日(金)9:55~17:05 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||||
| 要 旨 |
本講習会では、「宇宙航空分野の最新エレクトロニクス技術とビジネス動向 ~今、空が熱い!~」と題し、空、宇宙の応用技術・ビジネスに関わる専門家の方々に講演いただいた。 1限目では、電動航空機の開発状況・課題についてご講演いただいた。制御、空調からエンジンまで、電動装備品のカバー範囲が徐々に広がっている状況を分かりやすく説明いただいた。 2限目では、ドローンの応用展開の方向性について、市場の状況から技術動向まで解説いただいた。講演者様が注力される遭難者探索、建築構造物維持保全の分野について動画等を用いて詳しく紹介された。 3限目では、JAXAの国際宇宙ステーション「きぼう」での活動内容と、特に民間が利用するためのスキームについて紹介があった。超小型衛星の利用に関してもわかりやすい説明があった。具体的なサービスは徐々に民間に委託され、開放されつつある。 4限目では、流れ星を人工的に作り出すビジネスに関して、そのビジネススキーム、および技術的な背景の紹介があった。2020年には広島周辺で実験が予定されている。 5限目では、降雨のリモートセンシングに関する技術の紹介があった。世界的にみると日本のアメダスのような降雨を正確に観測できるシステムは少なく、全地球的な降雨の観測・地球環境の研究のために重要な技術である。 興味深い分野と思われたが、電子情報通信分野の専門家にとっては少し縁の薄い分野でもあり、参加者を集めるのに苦労した。多くの学会員が直接かかわる分野からテーマを選考する方が参加者を集めやすいのではないかと感じた。 |
||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 19名 | ||||||||||||||||
|
電気三学会関西支部講演会
サイバーセキュリティ技術とセキュリティ人材育成の最新動向
| 日 時 | 2018年09月21日(金) 14:00 ~ 17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室 (大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 |
本講演会では、IoTに代表されるように様々な機器がインターネットに接続されるようになっている中、サイバー攻撃への対策が急務になっています。サイバーセキュリティ技術の研究開発、セキュリティ人材育成で活躍されている講師陣をお招きし、最新の動向を中心にご講演いただいた。 1講演目は、IoT時代に向けた攻撃検知技術として、重要インフラにおける動作監視・解析技術、ホームネットワークにおける不正操作検知技術に関する取り組みをご紹介いただいた。 2講演目は、持続的なセキュリティ人材の供給に向けた取り組みとして、NICTで実施されているセキュリティ人材育成事業に関して、それぞれのプログラムの目的やトレーニング内容についてご紹介いただいた。 3講演目は、社会インフラに求められるサイバーセキュリティ技術への取り組みとして、2017年4月に設立された「産業サイバーセキュリティセンター」の概要、人材育成事業のプログラム内容に関してご紹介いただいた。 各講演とも感心が高まっている内容ということもあり、多数の聴講者に参加いただき、また活発な質疑もいただいた。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 50名(61名) | ||||||||||||
|
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2018年9月12日(水) 、13日(木) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 214号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) |
| 内 容 |
講師:大倉史生 大阪大学産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 助教 補助員:岩口尭史 奈良先端科学技術大学院大学 博士後期課程 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは (9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理 など 【2日目】 1.OpenCV を用いた独自の画像処理の実装 (9:40-11:00) ・画素値の直接操作 ・Region of Interest の利用 2. OpenCVによる実践的画像処理1 (11:10-12:30) 3. OpenCVによる実践的画像処理2 (13:30-15:00) 4. 演習 (15:10-16:50) テキスト:当日配布資料 参考書: OpenCVによる画像処理入門:小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 OpenCV 3 プログラミングブック:藤本雄一郎ら, マイナビ |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて、実習を通して画像処理技術を理解するための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理の理論や実装方法について解説された。2日目は、カメラからの3次元情報の取得とその利用や、パノラマ画像生成など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する演習が行われた。少人数の参加者に対して講師と補助員の二人で対応することで、全体をとおして非常に丁寧な指導を行うことができ、参加者の満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 1日目:10名、2日目:9名 (11名) |
|
電子情報通信学会関西支部 中高生向け講演会
IchigoJamコンピュータでロボットカーを動かそう
| 日 時 | 2018年8月22日(水) 9:30~15:30、 23日(木) 9:30~12:10 |
|---|---|
| 場 所 | 明石工業高等専門学校 (兵庫県明石市) |
| 内 容 |
第一日目 平成30年8月22日(水) 9:30~10:00 受付 10:00~10:10 開講挨拶 10:10~10:30 講 演「講座の全体説明」 10:30~15:30 実習Ⅰ「ロボットの製作とIchigoJamの実装」 第二日目 平成30年8月23日(木) 9:30~12:00 実習Ⅱ「プログラミングとロボットカーの動作制御」 12:00~12:10 修了証書授与、閉講挨拶 |
| 要 旨 |
本講演会では第一日目に、ロボットカー製作という機械系と、電池で駆動するマイコン、LED点滅、モータ動作確認など電子系を学び、第二日目にはその上位でプログラム制御を行う情報系、計三種の技術を組み合わせた実習であることを説明した。受講者全ての前向きな取り組み姿勢を感じる内容であった. 第二日目では、第一日目の製作したロボットカーに実装されたマイコンへのプログラミングを実習した。前後左右のモータ制御により、前進、後退、右旋回、左旋回など、作成したプログラムと比較しつつ動作確認を行った。あいにく台風が接近したため、終了時刻を12:10に変更した。また最後に修了書の授与を実施した。 今年度講演会の応募者は小中学生の男子のみで高校生及び女子からの応募はなかった。(来期へ向けた課題)応募総数は定員の約2倍で抽選により受講者を決定した。また参加者の多くは本校Webを見て参加していた。 アンケートの結果、参加者の殆どが内容や使用した教材、総合的に大変良かったと回答しており、今後もこのような機会があれば積極的に講演会を開催したい。 |
| 参加者(申込者) | 小・中学生15名。(小学生高学年7名、中学生8名) |
|
電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2018年5月31日(木) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 214号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) |
| 内 容 |
講師:池田和司 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 教授 1.(9:40-11:10) イントロダクション 確率統計の基礎 2.(11:15-12:45) 分類問題に対する手法 ・ベイズ分類器 ・サポートベクターマシン 3.(13:45-14:40) 回帰問題に対する手法 ・線形回帰と正則化 ・ロジスティック回帰 4.(14:50-16:00) 最近の手法の紹介 ・ニューラルネットワーク ・ガウス過程 5.(16:10-16:50) 人工知能の現状 参考書: 杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
| 要 旨 | ビッグデータの解析ツールである機械学習について,基礎的な考え方から代表的な手法まで解説され,具体的な応用例についても紹介した。統計的機械学習の基礎となる統計数学から応用事例まで,非常に幅広い話題であったために多少難解な部分も見受けられたが,シラパスの内容に加えて,高校生を対象として用意されたスライドでAIの現状と最新技術の紹介し,実際の応用事例など参加者の興味のある話題であったために,参加者にとって有意義で満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 15名(17名) |
|
一般見学会記録 電気三学会関西支部 一般見学会
情報通信研究機構 未来ICT研究所(神戸)
| 日 時 | 2017年11月22日(水) 13:30 ~ 16:30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 | 近年、情報通信ネットワークの複雑化や流通する情報量の爆発的な増加に伴い、消費電力量の増大や帯域の逼迫、サイバー犯罪の増加や通信ケーブルに必要な希少資源の供給不安など多くの課題が顕在化している。こういった課題を解決するための革新的な研究開発(ナノICT、超高周波ICT、バイオICT技術)の数々を見学するため、情報通信研究機構 未来ICT研究所(神戸市西区)を訪問した。 研究所が神戸市の外れにあり、大阪市内からは電車とバスを乗り継がなければならないという立地の不便さと、天候も良くなかったことから参加者数の減少が心配されたが、例年通りの広報手段により昨年度(参加者25名)と同程度の23名の見学者が集まった。 見学会当日は最初に研究所の概要を説明して頂き、その後2班に分かれて超伝導デバイスPJ、ナノ機能集積PJ、脳情報工学研究室、生体物性PJ、生物情報PJ、深紫外光ICTデバイス先端開発センターの6つの研究室を回った。各研究室では研究員の方から最新の研究成果を分かりやすく説明をしていただき、それに対して見学者からも多くの質問があり活発な質疑応答が行われた。研究室間の移動や各研究所の見学終了タイミングに関しては、研究所の見学担当者の方に先導して頂いためスケジュール通りスムーズに見学を行うことができた。 企画/運営に関しては概ね好評であり、参加者からは「知的好奇心が満たされた」「多くの通信技術について見学でき有意義であった」「説明が丁寧で分かりやすかった」「今後の応用に役立てられそう」等の意見を頂いた。また、昨年度から変更された「現地集合・解散、参加費無料」という見学形式に関しても特に不満の声は聞かれなかった。 |
||||||||||
| 参加者(申込者) | 23名(応募30名、キャンセル4名、事後連絡1名、連絡なし2名) | ||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
| 日 時 | 2017年11月16日(木) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:白石善明 神戸大学 大学院工学研究科電気電子工学専攻 准教授 1.(9:40-11:10) 情報セキュリティの考え方 ・情報セキュリティとその対策 ・情報セキュリティの基本的問題 2.(11:15-12:45) アクセス制御の考え方 ・ユーザの認証 ・情報の保護 3.(13:45-15:15) ElGamal暗号、Schnorr署名 ・合同式、位数、原始元、フェルマーの定理 ・離散対数問題 ・ElGamai暗号 ・Schnorr署名 4.(15:20-16:50) セキュリティ設計の基礎 ・脅威分析 ・セキュリティ対策 |
| 要 旨 | 冒頭、最新のサイバー攻撃の現状を示しながら世界規模でのインシデント事例を紹介され、現代社会生活における脆弱性と政府レベルでの対応状況を解説された。 そして暗号技術の基礎の基礎からの演習に始まり、ElGamal暗号の暗号化から復号に至るまでを理解できるレベルまで講義され、さらにPKI(公開鍵基盤)での認証を使った信用モデルへと進められた。 後半では、放送・医療・エネルギー分野での家庭内サービスに対する脅威分析と対策の考え方を教示され、参加者にとってレベルの高い、内容豊富な講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 15名(15名) |
|
専門講習会記録 電気三学会関西支部 専門講習会
高周波技術の応用展開と技術動向
| 日 時 | 2017年10月27日(金) 9:55~17:05 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||||
| 要 旨 | 本講習会では、「高周波技術の応用展開と技術動向」と題し、化学プラント、無線電力伝送、次世代移動体通信(5G)、医療、テラヘルツの各応用分野における専門家の方々に講演いただいた。 1限目では、6.8MHz~24GHz帯のISMバンドを用いた、高周波加熱を主とする化学プラント応用について、加熱原理や加熱対象、プラント立ち上げ事例等について講演された。 2限目では、マイクロ波を用いた無線エネルギー伝送に関し、伝送理論、製品応用事例、今後期待されるアプリケーションについて講演いただいた。 また、マイクロ波給電の標準化・法規制動向についても言及された。 3限目では、5Gの概要とドコモの取り組みに関し、massive-MIMO等の技術トピックスや新たな利用シーン等について講演された。 また、伝送/計測技術の実証実験についても紹介があった。 4限目では、高周波の医療応用に関し、マイクロ波過熱による癌等の腫瘍の治療原理や手術事例、切開や止血用手術道具への適用事例等について講演された。 5限目では、テラヘルツ帯の信号源の高出力化の紹介を中心とした技術紹介とともに、その信号源を用いた物質の指紋スペクトルとの照合による麻薬物質の検出等の応用事例講演された。 高周波の様々な分野での応用事例を一堂に集めた講習会となり、例年規模の参加者を集めることができた。アンケートにおいても満足度の高い評価が得られた。 |
||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 30名 | ||||||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2017年8月29日(火) 、30日(水) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師: (1) 大倉史生 大阪大学産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 助教 (2) 田中賢一郎 奈良先端科学技術大学院大学 助教 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは (9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理 など 【2日目】 1.OpenCV を用いた独自の画像処理の実装 (9:40-11:00) ・画素値の直接操作 ・Region of Interest の利用 2. OpenCV による実践的画像処理1 (11:10-12:30) ・カメラからの三次元情報の取得と利用 3. OpenCV による実践的画像処理2 (13:30-15:00) ・画像変形によるパノラマ画像生成 4. 演習 (15:10-16:50) テキスト:OpenCVによる画像処理入門:小枝正直, 上田悦子, 中村恭之, 講談社 参考書:OpenCV 3 プログラミングブック:藤本雄一郎ら, マイナビ |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて、実習を通して画像処理技術を理解するための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理の理論や実装方法について解説された。2日目は、カメラからの3次元情報の取得とその利用や、パノラマ画像生成など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する実習が行われた。少人数の参加者に対して講師二人で対応することで、実習における指導を丁寧に行うことができ、参加者の満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 17名(17名) |
|
講演会記録 電子情報通信学会関西支部 中高生向け講演会
「フィジカルコンピューティング-体感できるプログラミング-」
| 日 時 | 平成29年8月8日(火)、10日(木) 両日とも13:00~16:40 |
|---|---|
| 場 所 | 神戸市立工業高等専門学校(兵庫県神戸市) |
| 内 容 |
講習内容:
・マイコン及び使用する部品(各種LED,照度センサー,圧電スピーカなど)についての説明 ・プログラミングの説明 ・実習Ⅰ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅰ」 ・実習Ⅱ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅱ」 |
| 要 旨 |
まず,はじめにマイコンや素子の説明などを20分ほど行い,その後,USB 接続のマイコンボード本体に LED や圧電スピーカー,光センサなどを組合わせて “光る”,“鳴る”,“感じる” といったコンピュータを実現するためにマイコンプログラミングに取り組みました。 その過程において,繰り返しや分岐などのプログラムの説明などを行いました。また,各自で応用プログラムなどを作るなど非常に受講者の皆様のやる気を感じられる内容となりました. |
| 参加者(申込者) | 2日合計29名(89名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2017年6月2日(金) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:池田和司 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 教授) 1.(9:40-11:10) イントロダクション 確率統計の基礎 2.(11:15-12:45) 分類問題に対する手法 ・ベイズ分類器 ・サポートベクターマシン 3.(13:45-15:15) 回帰問題に対する手法 ・線形回帰と正則化 ・ロジスティック回帰 4.(15:20-16:50) 最近の手法の紹介 ・ニューラルネットワーク ・ガウス過程 参考書:杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
| 要 旨 | ビッグデータの解析ツールである機械学習について,基礎的な考え方から代表的な手法まで解説され,他分野への応用事例についても紹介された。基本的な数学から応用事例まで,非常に幅広い話題であったために多少難解な部分も見受けられたが,実際の応用事例など参加者の興味のある話題であったために,参加者にとって有意義で満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 20名(20名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「アルゴリズムから学ぶ暗号技術」
| 日 時 | 2016年12月9日(金) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:村上恭通(大阪電気通信大学 情報通信工学部通信工学科 教授) 1.(9:40-11:10) イントロダクション: ・暗号技術の基礎 ・秘密鍵暗号と公開鍵暗号 ・TLS概観 2.(11:15-12:45) Diffie-Hellman鍵共有法の解説と実習: ・有限環・有限体上の加減乗除とべき乗演算 (拡張ユークリッド互除法・高速指数演算法) ・フェルマーの定理とオイラーの定理 ・原始元と離散対数問題 ・PARI/GPによる実習 3.(13:45-15:15) RSA公開鍵暗号の解説と実習: ・素数生成法 (確率的・確定的素数判定法) ・素因数分解問題 ・中国人の剰余定理 ・RSA暗号とRSA署名 ・PARI/GPによる実習 4.(15:20-16:50) AESの解説と実装: ・AESアルゴリズム詳解 ・PARI/GPによるAESの実装 |
| 要 旨 | インターネットで安全な通信を提供するためのプロトコルであるTLSで利用される暗号技術について、必要となる数学的バックグラウンドから、秘密鍵暗号と公開鍵暗号のアルゴリズムの詳細な解説、さらにサンプルプログラムによるアルゴリズムの動作の確認までを含む講義が行われた。 非常に幅広い話題であったために時間が少し不足した感があるが、米国の暗号解読や映画の暗号技術など参加者の興味のある話題も盛り込まれており,参加者にとって有意義で満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 7名(8名) |
|
一般見学会記録 電気三学会関西支部 一般見学会
(1) NECイノベーションワールド(関西)
(2) 産業技術総合研究所 関西センター
| 日 時 | 2016年11月18日(金) 9:45~16:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
午前の部:
午後の部:
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 近年、新たな情報通信技術として、モノの管理や制御をインターネットを介して行うIoT技術や、クラウド上に多くの情報を収集しAI(人工知能)を活用して情報解析を行う技術などが注目されています。今回の見学会では、午前の部で、それらの最新技術を実体験するため、NECイノベーションワールド(関西)を訪問した。また午後の部で、情報化社会を支える最新の研究開発の取り組みを見学するため、産業技術総合研究所 関西センターを訪問した。 NECイノベーションワールドでは、最初に施設全体の説明をしていただき、その後、2班に分かれて、ワークスタイルイノベーション、インフライノベーション、ビジネスイノベーション、テーマゾーンという各テーマの技術説明を受けるとともに、実体験を行った。具体的には、音声の分析・合成技術、SDN技術、蓄電とHEMS技術、生体認証技術、IoT技術(画像認識、仮想現実)などの最新技術を見学した。各テーマとも、世の中で注目されている技術ということもあり、非常に多くの質問があり、用意されていた全ての展示を見きれないほどであった。 産業技術総合研究所・関西センターでは、最初に産総研全体の活動の説明があり、次に関西センターの歴史やこれまでの成果(四大発明)の説明があった。その後、2班に分かれて、ダイヤモンドウェハ開発と蓄電池研究を行っている研究室を見学し、各研究内容の説明や研究設備の説明をしていただいた。ダイヤモンドウェハを作る設備、蓄電池の評価設備、5mもある電子顕微鏡など、技術の粋を結集した設備が至る所にあった。参加者も多くの質問をされ、予定の時間を少しオーバーするほど活発な見学であった。 企画/運営に関しては概ね好評であり、参加者からは、実際の体験は良かった(NECイノベ)、研究現場を見学で来て良かった(産総研関西)、リタイア後は新技術開発に接する機会がないのでこの見学会を楽しみにしている(全体)、等の意見を頂いた。また、今年度は、以前からの見学形式を変更し、会場間の移動や昼食の提供は実施せず参加費無料という形式としたが、参加者からの不満は少なく、今年度の方式が良いという意見も多かった。 |
||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 午前18名、午後20名、総人数25人 (午前21名、午後24名、総人数29名) | ||||||||||||||
|
専門講習会記録 電気三学会関西支部 専門講習会
人の内面状態理解のための生体情報センシング最新動向
| 日 時 | 2016年10月28日(金) 9:55~16:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 本講習会では、人の内面状態理解のための生体情報センシング最新動向と題し、MRI、ウエアラブル生体センサ、ドライバモニタリング、バイオセンシング、ミリ波心拍センサの専門家の方々に講演いただいた。 1限目では、非侵襲的脳機能イメージング技術に関して、EEG, MEG, NIRS, MRI, PET等各種手法特徴や制約について、およびMRIの原理からfMRI等の活用事例について講演された。 2限目では、近年のウエアラブル生体センサの動向、計測原理についての説明の後、医療・ヘルスケア分野やスポーツ・フィットネス分野への応用事例について講演された。 3限目では、近年の交通事故状況分析からドライバモニタリングの必要性について説明の後、現状の各種ドライバモニタリング技術の長所、短所や、自動運転とのつながりについて講演された。 4限目では、医療・ヘルスケア応用を指向した化学・バイオセンシング技術、およびマイクロ流体デバイスの特徴とその具体的事例について講演された。 5限目では、各種非接触生体センシング技術の比較の後、パナソニック社のミリ波レーダ技術を用いた心拍推定技術について講演された。 近年注目されている生体センシング分野の講習会であったため、例年規模の参加者を集めることができた。アンケートにおいても満足度の高い講習会になり、人の内面状態理解のための生体情報センシングの可能性および現状の問題点を深く考える機会が与えられた。 |
||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 34名 | ||||||||||||||
|
講演会 電気三学会関西支部講演会
IoTのさらなる展開に向けた技術
~あなたの隣のセキュアでクレバーなシステムを目指して~
| 日 時 | 2016年9月16日(金) 14:00~17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | 本講演会では、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)の実用化を加速する鍵となる最先端の研究開発で活躍されておられる講師陣をお招きし、最新技術やトピックスを中心にご講演いただいた。 1講演目は、IoTを安心して活用するために必須となるセキュリティ技術に関して、基礎的な内容から、車載向けを中心に様々な脅威事例と対策技術をご紹介いただいた。 2講演目は、IoTの効果として期待の大きい省エネを支える技術として、スマートメーターやHEMS(Home Energy Management System)、ZEH(net Zero Energy House)等の概要とそのソリューション事例をご紹介いただいた。 3講演目は、スマートメーター等から得られるIoTデータを活用した研究事例と、家庭内IoTサービスの動向と課題に関してご紹介いただいた。 各講演とも具体的な事例を豊富にわかりやすくご紹介いただき、聴講者からは理解度と有意義度の両面で高い評価を頂いた。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 48名(63名) | ||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 2016年8月25日(木),26日(金) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:浦西友樹(大阪大学サイバーメディアセンター 情報メディア教育研究部門 准教授) 大倉史生(大阪大学産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 助教) 【1日目】 1. 画像処理プログラミングとは ( 9:40-11:00) 2. OpenCV のインストール (11:10-12:30) ・環境設定及びサンプルプログラムの実行 3. 画像の入出力 (13:30-15:00) ・カメラ画像の取り込みと表示 ・ファイルからの画像の読み込みと保存 4. OpenCV による画像処理のケーススタディ (15:10-16:50) ・幾何学変換、濃淡変換、フィルタ処理、二値画像処理など 【2日目】 1.OpenCV を用いた独自の画像処理の実装 ( 9:40-11:00) ・画素値の直接操作 ・Region of Interest の利用 2. OpenCV による実践的画像処理 1 (11:10-12:30) ・カメラからの三次元情報の取得と利用 3. OpenCV による実践的画像処理 2 (13:30-15:00) ・画像変形によるパノラマ画像生成 4. 演習 (15:10-16:50) ・課題は当日発表 テキスト:OpenCV による画像処理入門:小枝正直、上田悦子、中村恭之、講談社 参考書:OpenCV 3 プログラミングブック:藤本雄一郎ら、マイナビ |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて、実習を通して画像処理技術を理解するための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理の理論や実装方法について解説された。2日目は、カメラからの3次元情報の取得とその利用や、パノラマ画像生成など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する実習が行われた。少人数の参加者に対して講師二人で対応することで、実習における指導を丁寧に行うことができ、参加者の満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 16名(16名) |
|
講演会記録 電子情報通信学会関西支部 中高生向け講演会
「フィジカルコンピューティング-体感できるプログラミング-」
| 日 時 | 平成28年7月26日(火)、28日(木) 両日とも13:00~16:40 |
|---|---|
| 場 所 | 神戸市立工業高等専門学校(兵庫県神戸市) |
| 内 容 |
講習内容: ・マイコン及び使用する部品(各種LED,照度センサー,圧電スピーカなど)についての説明 ・プログラミングの説明 ・実習Ⅰ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅰ」 ・実習Ⅱ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅱ」 |
| 要 旨 | まず,はじめにマイコンなどの説明などを30分ほど行い,その後,USB 接続のマイコンボード本体に LED や圧電スピーカー,光センサなどを組合わせて “光る”,“鳴る”,“感じる” といったコンピュータを実現するためにマイコンプログラミングに取り組みました。 その過程において,繰り返しや分岐などのプログラムの説明や,早く終わった生徒の皆さんには応用課題などをしてもらうことで実習を進めていきました。 |
| 参加者(申込者) | 2日合計36名(93名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2016年6月13日(月) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:池田和司(奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授) 講義内容: 1.(9:40-11:10) イントロダクション 確率統計の基礎 2.(11:15-12:45) 分類問題に対する手法 ・ベイズ分類器 ・サポートベクターマシン 3.(13:45-15:15) 回帰問題に対する手法 ・線形回帰と正則化 ・ロジスティック回帰 4.(15:20-16:50) 最近の手法の紹介 ・ニューラルネットワーク ・ガウス過程 参考書:杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
| 要 旨 | ビッグデータの解析ツールである機械学習について,基礎的な考え方から代表的な手法まで解説され,他分野への応用事例についても紹介された。基本的な数学から応用事例まで,非常に幅広い話題であったために多少難解な部分も見受けられたが,実際の応用事例など参加者の興味のある話題であったために,参加者にとって有意義で満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 10名(10名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「アルゴリズムから学ぶ暗号技術」
| 日 時 | 平成27年12月4日(金) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 |
講師:村上恭通(大阪電気通信大学 情報通信工学部 通信工学科 准教授) 講義内容: 1.(9:40-11:10) イントロダクション: ・暗号技術の基礎 ・秘密鍵暗号と公開鍵暗号 ・TLS概観 2.(11:15-12:45) Diffie-Hellman鍵共有法の解説と実習: ・有限環・有限体上の加減乗除とべき乗演算 (拡張ユークリッド互除法・高速指数演算法) ・フェルマーの定理とオイラーの定理 ・原始元と離散対数問題 ・PARI/GPによる実習 3.(13:45-15:15) RSA公開鍵暗号の解説と実習: ・素数生成法 (確率的・確定的素数判定法) ・素因数分解問題 ・中国人の剰余定理 ・RSA暗号とRSA署名 ・PARI/GPによる実習 4.(15:20-16:50) AESの解説と実装: ・AESアルゴリズム詳解 ・PARI/GPによるAESの実装 |
| 要 旨 | インターネットで安全な通信を提供するためのプロトコルであるTLSで利用される暗号技術について、必要となる数学的バックグラウンドから、秘密鍵暗号と公開鍵暗号のアルゴリズムの詳細な解説、さらにサンプルプログラムによるアルゴリズムの動作の確認までを含む講義が行われた。参加者の要望に応じた内容で、参加者の満足度が非常に高い講義となった。 |
| 参加者(申込者) | 10名(10名) |
|
一般見学会記録 電気三学会関西支部 一般見学会
(1)京都大学生存圏研究所
(2)京都大学生存圏研究所 信楽MUレーダー
| 日 時 | 平成27年11月17日(火) 9:45~18:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | マイクロ波技術が地球環境の維持や人類の生存のために、今後どのように貢献できるか、貢献すべきなのかを学習することを目的として、京都大学生存圏研究所を見学させて頂いた。 京都大学生存圏研究所(宇治キャンパス)では、まず、研究所の由来や、マイクロ波利用に関わる研究について分かりやすく説明して頂いた。大型電波暗室(METLAB)では、宇宙からのマイクロ波電力伝送を目指した研究施設を見学した。次に、マイクロ波新材料生成実験室を見学し、木材からバイオエタノールを生成するために、マイクロ波が重要な技術になることを学んだ。最後に、異分野融合領域の研究として、居住圏劣化生物飼育棟(シロアリ研究施設)を見学した。 信楽MUレーダーでは、まず、講義形式で施設全体の概要とIEEEマイルストーンに認定されるに至った歴史等を説明して頂いた。その後、MUレーダーを見学した。参加者はその規模の大きさに驚くと共に、設備の運用維持や、アンテナの構造等で多くの質問がなされた。 参加者からは、分野が広く面白い研究所を見学でき非常に勉強になった、公共交通機関では訪れにくい施設を見学させていただいてありがたかった、説明および質問に対する回答も非常にていねいで分かりやすく研究内容に興味を持ったなどのコメントを頂いた。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 19名(18名) | ||||||||||||
|
専門講習会記録 電気三学会関西支部 専門講習会
自動運転技術の最新動向
| 日 時 | 2015年10月30日(金) 9:55~16:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 本講習会では、自動運転の実用化を見据えた研究開発の最新動向と題し、車両周辺センシング、パスプランニング、V2X、ドライバーセンシング、車載プラットフォームの専門家の方々に講演いただいた。
1限目では、自動運転全般(高速道自動運転と一般道自動運転)の概要、パスプランニング技術、および金沢大学における市街地公道走行実証実験の最新状況について講演された。 |
||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 31名 | ||||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎」
| 日 時 | 平成27年10月1日(木) 9:40~16:50 | 内 容 |
講師:池田和司 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 教授
講義内容: 参考書:C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (丸善出版) |
|---|---|
| 要 旨 | 大量なデータから有益な情報を抽出するには、計算機を利用した統計的手法が必要になる。本講座ではその方法論である統計的機械学習について、基本的な考え方と代表的な手法を紹介するとともに、具体的な応用例が紹介された。参加者は具体的な応用分野をもった社会人技術者が多かったが、講師の実経験を交えた解説が行われたので、参加者の満足度の高い講座となった。 |
|
講演会記録 電気三学会関西支部講演会
見える化技術の最新動向とその応用
| 日 時 | 平成27年9月11日 14:00~17:00 | 内 容 |
|
|---|---|
| 要 旨 | 近年、IoTやビックデータなどの情報通信分野のみならず様々な分野においてセンシング技術の利活用が進んできてる。一方でセンシング技術自体の進展も急速に進んでおり、これまで見えなかったものが見えるようになり、その応用範囲が拡大してきている。本講演会はそのような意味での幾つかの“見える化技術”に着目し、構成した。 まず、脳波の見える化技術として、脳波計側の基礎・応用と今後の発展性に関して、ウェアラブルな脳波計の開発や脳活動の可視化による潜在意識に関する情報を取得する技術など興味深い研究事例を交えながら紹介いただいた。次に、テラヘルツ波を利用した見える化技術として、テラヘルツ計測やテラヘルツカメラに関する技術紹介、テラヘルツ波ならではの応用事例と今後の発展性に関して紹介いただいた。更に、研究、通信、医療、建設など様々な分野で既に見える化技術として利活用されている3Dスキャナ・3Dプリンタ技術に関する、応用、将来展望について講演いただいた。各講演とも非常に興味深いお話であり会場からは、活発な質疑があった。聴衆講演会に関して理解度および有意義性の両方から比較的高い評価をいただいた。 |
| 参加者(申込者) | 31名 |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 平成27年8月31日(月)、9月1日(火) 両日とも9:40~16:50 | 内 容 |
講師:浦西 友樹 京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 助教 河合 紀彦 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 【1日目】講義内容
【2日目】講義内容 参考書:詳解 OpenCV: G. Bradski and A Kaehler(著)、松田 晃一(訳)、オライリージャパン |
|---|---|
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて、実習を通して画像処理技術の理解を深めるための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理の理論や実装方法について解説された。2日目は、カメラからの3次元情報の取得とその利用や、パノラマ画像生成など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する実習が行われた。少人数の参加者に対して講師二人で対応することで、実習における指導を丁寧に行うことができ、参加者の満足度の高い講座となった。 |
| 参加者(申込者) | 16名(20名) |
|
講演会記録 電子情報通信学会関西支部 中高生向け講演会
「加速度センサとビジュアルプログラミングで学ぶプログラミング」
| 日 時 | 平成27年8月2日(日)、8月9日(日) 両日とも10:00~16:00 |
|---|---|
| 場 所 | 奈良工業高等専門学校(奈良県大和郡山市) | 内 容 |
講習内容: ・センサ(照度センサ、温度センサ)についての説明 ・プログラミングとは ・プログラムの流れ(順次、繰り返し、分岐) ・実習Ⅰ、Ⅱ |
| 要 旨 | 中高生を対象に加速度センサとビジュアルプログラミングで学ぶプログラミングの公開講座を実施しました。受講者には、最初の45分で、センサ、プログラミング学習用のキット、ならびに、ビジュアルプログラミングの方法についての講義を受けてもらい、その後、プログラムの流れを制御する順次、繰り返し、分岐の説明を行いながら演習課題を含めてプログラミング実習を行ってもらいました。実習では、電子オルゴール、タイマ、照度センサ、温度センサなどを使い、プログラムの作成を行いました。 アンケートの結果、難易度も適切で、プログラミングに興味を持ってもらえ、満足度の高い講座となりました。 |
| 参加者(申込者) | 22名(34名) |
|
一般見学会記録 電気三学会関西支部 一般見学会
(1)大阪府立大学 植物工場研究センター
(2)京都大学 先端植物工場研究センター
| 日 時 | 平成26年11月7日(金) 9:00~17:20 | 内 容 |
|
|---|---|
| 要 旨 | 最先端の植物工場を見学し、より広い分野でのICT適用の可能性を探る事を目的に、大阪府立大学植物工場研究センター 並びに 京都大学 先端植物工場研究センター を見学させて頂いた。 大阪府立大学 植物工場研究センターでは、講義形式での説明に続いて、実稼働中の植物工場の現場に入り、主にフリルレタスの育苗~生育が行われている、多段型の栽培室を間近に見学。ロボット搬送装置が実際に栽培トレイを移動させている様子を見ることが出来た。 京都大学 先端植物工場研究センターでは、ゼロエミッションを目指した閉鎖系でのCO2リサイクル技術や、より変換効率の良い穀物への適用、生産量ではなく植物工場ならではの付加価値といった質へこだわりなど、実際に栽培された野菜の試食を交え、多岐にわたるトピックについて解説頂いた。 参加者からは、同様の2施設を見学し何が課題であるかを比較して知ることができ有意義であった、工程の大部分をロボットで行っている事に驚いた、研究に独自性が見られ感銘を受けた などのコメントを頂いた。 |
| 参加者(申込者) | 22名(24名) |
|
専門講習会記録 電気三学会関西支部 専門講習会
「医療情報基盤とビッグデータ解析の最新動向 ~ 医療データの取得・蓄積・解析・活用 ~」
| 日 時 | 平成26年10月21日(火) 9:55~16:45 | 内 容 |
|
|---|---|
| 要 旨 | 本講習会では、医療ビッグデータの取得・蓄積・解析・活用までの研究と実用化に関して、医学・工学の両分野の専門家の方々に講演いただいた。 1限目では,治す医療から予防する医療に向けて,遺伝や環境を考慮した人間のデータを蓄積することの重要性と,現在進めているコホート研究と課題が講演された. 2限目では,大量の医療情報を保持する電子カルテシステムについて講演された.多様なカルテの記述に対応する電子カルテのしくみや,カルテの病院間の相互運用について議論された. 3限目では,医療データを長期間に渡って蓄積する際の問題点として,検査方法の変更や精度の不安定さが指摘され,様々な解決方法について講演された. 4限目では,治療行為をするスタッフの行動を様々なセンサを用いて計測し,行動識別を行う機械学習手法について講演され,医療プロセスのモデル化と効率化への応用について議論された. 5限目では,現状の電子カルテから有益な医療情報を取り出すことの難しさについて講演され,環境中のセンサやタグなどを用いて,客観的な情報を切り分けて記述する方針が議論された. 近年注目されている医療ビッグデータ解析に注目を集められたためか,参加者も医学および工学の両方の分野に渡り,多数の参加者を集めることができた.アンケートにおいても満足度の高い講習会になり、医療ビッグデータ解析の可能性および現状の問題点を深く考える機会が与えられた. |
| 参加者(申込者) | 43名(44名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 2014年10月16日(木) 9:40~16:50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講 師 | 池田和司(奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授) | ||||||||
| 内 容 |
テキスト:杉山 将 「統計的機械学習」 (オーム社) |
||||||||
| 要 旨 | ビッグデータの解析ツールである機械学習について、確率・統計の基礎から最新の話題まで多岐にわたる内容の講義が行われた.講義の各時間毎に質疑応答時間が設けられ,受講者が多数の質問をすることができた.少人数の参加者に対して丁寧な講義が行われ,参加者の満足度の高い講座となった. | ||||||||
| 参加者(申込者) | 12名(14名) | ||||||||
|
講演会 電気三学会関西支部講演会
「ビッグデータの最新動向とビジネスへの適用例」
| 日 時 | 平成26年9月12日 14:00~17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | 情報通信技術の急速な普及に伴い、爆発的に情報が増え続ける“ビッグデータの時代”が到来し、このデータをビジネスのみならず社会や個人で、いかに活用するかが大きな関心事となっている。また、ビッグデータを適切に分析し、価値ある情報を導き出すビジネス・アナリティクスへの期待も高まっている。 本講演会では、ビッグデータ活用の基礎、話題の質問応答システム「Watson」、ビッグデータがもたらすパラダイム・シフトと、それを実現するビジネス・アナリティクスの挑戦について、デモを交えたご紹介、太陽及び宇宙空間観測データに機械学習を用いた宇宙天気予報についてお話しいただいた。 各講演とも非常に興味深いお話であり会場からは、それぞれの分野での実用性に関する質問やビッグデータを当会会員がどのように活かしていくかなど活発な質疑があり、講演会に関して理解度および有意義性の両方から高い評価をいただいた。 (写真は当日の講演の様子。) |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 61人(67人) | ||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 平成26年8月28日(木)、29日(金) 両日とも9:40~16:50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講 師 | 浦西 友樹 京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 助教 中島 悠太 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 |
||||||||
| 内 容 (1日目) |
|
||||||||
| 内 容 (2日目) |
・テキスト:OpenCV2プログラミングブック:OpenCV2プログラミングブック作成チーム、毎日コミュニケーションズ |
||||||||
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎の習得を目的とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて、実習を通して画像処理技術の理解を深めるための講座が行われた。1日目はOpenCVのインストールとカメラ画像の取り込みを始めとして、基礎的な画像処理の理論や実装方法について解説された。2日目は、3次元画像の取得できるMicrosoft Kinectを用いた3次元画像処理や、機械学習による文字認識など、具体的で実践的な画像処理とその応用について講義され、さらに受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する実習が行われた。少人数の参加者に対して講師二人で対応することで、実習における指導を丁寧に行うことができ、参加者の満足度の高い講座となった。 | ||||||||
| 参加者(申込者) | 16名(16名) | ||||||||
|
講演会記録 中高生向け講演会
「加速度センサとビジュアルプログラミングで学ぶプログラミング」
| 日 時 | 平成26年8月3日、31日(日) 10:00~16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 奈良工業高等専門学校(奈良県大和郡山市) | ||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 中高生を対象に加速度センサとビジュアルプログラミングで学ぶプログラミングの公開講座を実施しました。受講者には、最初の45分で、加速度センサについてやプログラミングとはなどの講義を受けてもらい、残りの時間でビジュアルプログラミングに取り組んでもらいました。加速度センサとビジュアルプログラミングには、加速度センサプログラマとビュートビルダーというソフトウェアを用いました。これは、加速度センサとプログラミングをビジュアル的に学ぶためのソフトウェアがセットになったプログラミング学習用のキットです。 受講者は実習を時間内に終了し、最後のアンケートにおいても評価の高い講座となりました。 |
||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 19名(24名) | ||||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電気四学会関西支部 ICT基礎講座
「アルゴリズムから学ぶ暗号技術」
| 日 時 | 平成25年12月20日(金) 9:40~16:50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講 師 | 村上 恭通 博士(工学) 大阪電気通信大学 情報通信工学部通信工学科 准教授 |
||||||||
| 内 容 |
|
||||||||
| 要 旨 | 本講座では、インターネットで安全な通信を提供するプロトコルTLS(Transport Layer Security)で使用される公開鍵暗号技術の動作原理や実装時に必要な数論アルゴリズムについて詳しく解説がされました。また、計算機代数ソフトウェアPARI/GPを用いた公開鍵暗号の鍵生成・暗号化・復号化について実習が行わました。 聴講者からは、暗号技術の基礎的なところから実装に必要なアルゴリズムまでを詳しく教えて頂き、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
||||||||
| 参加者(申込者) | 6名(6名) | ||||||||
|
専門講習会記録 電気四学会関西支部 専門講習会
M2Mを支える技術と近未来展望
| 日 時 | 平成25年12月6日(金) 9:55~16:20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||||||
| 要 旨 | M2Mを支える技術として、センサネットワーク系の電力供給方法に焦点をあてて概要から応用までを最前線でご活躍の専門家の方々にご紹介いただいた。 1限目では無線通信の省電力化技術が紹介された。定期的に微弱な通信をするエネルギーハーベストに対し、緊急時に必要な情報を送るニーズがあればどう対応できるか議論があった。 研究段階の技術は実用化に向けて課題が多く、実用化された技術も普及拡大にはコスト改善、性能向上、評価・アピールノウハウの蓄積等が必要であり壁は高いが、普及拡大された際の未来像を想像すると夢が膨らんだ。 |
||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 32名(38名) | ||||||||||||||||
|
一般見学会記録 電気四学会関西支部 一般見学会
(1)大阪ガス(株)ガス科学館
(2)関西電力(株)堺港発電所PR館・堺太陽光発電所・堺港発電所(火力)
| 日 時 | 平成25年11月22日(金) 9:00~17:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 | エネルギー問題に関する更なる意識向上を目的として,大阪ガスガス科学館と関西電力堺港発電所および堺太陽光発電所を見学させて戴いた. ガス科学館では,ガスの採掘から私たちの家庭に届くまでの工程や,エネルギーの有効利用とCO2フリー/CO2オフの環境問題についての取り組みをご紹介戴いた.また,天然ガスによる火力発電施設の堺港発電所では,世界最高の発電効率を誇るコンバイドサイクル方式についてご紹介戴き,更に,国内最大級のメガソーラー施設である堺太陽光発電所では,再生可能エネルギーの先端技術を見学させて戴いた. 参加者からは,地震や津波発生時のフェイルセーフに関する質問,メタンハイドレートや再生可能エネルギーの今後の展望に関する活発な質問が相次いた.今後希望する見学会の内容として,「太陽光発電関連施設,原子力発電施設,風力発電施設」というご要望があり,エネルギー問題への関心の高さが伺える.また,勉強になった,有意義な見学会だったとのコメントを多く戴いた. |
||||||||||
| 参加者(申込者) | 19名(21名) | ||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「OFDM通信基礎講座」
| 日 時 | 平成25年8月1日(木)、2日(金) 両日とも9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 | 講師:吉田 悠来 博士(工学) 大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 助教 【1日目】講義内容 【2日目】講義内容 参考書:J. Proakis, Digital communications, McGraw-Hill |
| 要 旨 | 今や携帯電話網をはじめ多くの無線通信システムに利用され、最近では光通信の分野でも注目をもたれているOFDM(直交周波数多重)方式について、数学的背景からその応用としての信号処理手法まで網羅的に解説された。さらにフリーウェアScilabを用いて、OFDM方式の伝送シミュレーション技術を実践的に習得できる形式で解説された。 講座専用のテキストやシミュレーションの実習が用意され、基礎から応用までをよく理解できたと受講者の評価は大変良好であった。 |
| 参加者(申込者) | 13名(13名) |
|
ICT基礎講座記録 電子情報通信学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 平成25年8月27日(火)、28日(水) 両日とも9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 | 講師:浦西 友樹 博士(工学)、大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教 中島 悠太 博士(工学)、奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 【1日目】講義内容 【2日目】講義内容 参考書:詳解 OpenCV: G. Bradski and A Kaehler(著)、松田 晃一(訳)、オライリージャパン |
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎を習得したい方を対象とし、オープンソースの画像処理ライブラリのひとつであるOpenCVを用いて画像処理の基礎について学習し、実習を通してその理解を深めるための講座が行われた。1日目はOpenCVのPCへのインストールとカメラ画像の取り込み、および画像ファイルの読み込みから、基礎的・実践的な画像処理の理論および方法について解説された。2日目は、より実践的な画像処理とその応用について講義され、受講者それぞれが独自の画像処理アルゴリズムをOpenCVにより実装する実習が行われた。 聴講者からは、画像処理の基礎から応用までの幅広い分野を対象にした優れた内容であり、説明が丁寧で講師の方の対応が非常に素晴らしく、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
| 参加者(申込者) | 18名(18名) |
|
ICT基礎講座記録 電気四学会関西支部 ICT基礎講座
「機械学習の基礎と応用」
| 日 時 | 平成25年10月3日(木) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 | 講師:池田 和司教授 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
1.(9:40-11:10) 2.(11:15-12:45) 3.(13:45-15:15) 4.(15:20-16:50) |
| 要 旨 | 池田和司教授から確率統計の基礎からスパース情報処理の応用まで、広範な内容の講義がありました。参加者数は定員15名を予定していましたが、キャンセル待ちの人が多数いたため、直前の運営委員会で受けいれることにして、29名(社会人13名、学生16名)が参加しました。講義の最後には、活発な質疑応答が熱心に行われ、盛況を極める講座とすることができました。 |
| 参加者(申込者) | 29名(30名) |
|
電気四学会関西支部講演会
農業へのICT(情報通信技術)活用の可能性
| 日 時 | 平成25年9月13日 14:00~17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | TPP加盟による競争環境の激化、少子高齢化による労働力・内需の縮小など、強い農業実現に向けたICT適用の期待は近年非常に大きくなっています。スマート農業、ビッグデータ、6次産業化、農業クラウド、植物工場などのキーワードが注目され、その達成にはICTの導入が前提とされています。具体的には、省力化や生産コストの低減に加えて、農産物の生育期間の短縮、品質の改善、自動化、そして配送スケジュールの最適化による配送時間の短縮化や電子商取引での新しい流通システムの開拓などが期待されており、様々な取り組みが始まっています。 本講演会では、大学での植物工場・施設園芸をはじめとする農業生産高度化に対する取り組み、及び植物体内の時計遺伝子をレーザー光で刺激して有用代謝物質を産生し高機能性作物を育成する技術、並びに日本の成長戦略「農業・農村の所得倍増」の施策に対し、ICT利活用による既存施設に最小限の投資で労働の省力化と収量拡大を同時に行う仕組みへの取り組みについてもお話しいただきました。 会場からは、各取組みの課題に対する対応策に関する質問やUECS規格の国際化に関する質問など活発な質疑があり、講演会に関して理解度および有意義性の両方から高い評価をいただきました。 (写真は当日の講演の様子。) | ||||||||||||
| 参加者(申込者) | 74人(89人) | ||||||||||||
|
|
講演会記録 中高生向け講演会
コンピュータの内部について学ぼう!!
| 日 時 | 平成25年8月1日(木) 10:00~16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 大阪府立大学工業高等専門学校(寝屋川市) | ||||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 昨年度に続き、身近なものになり過ぎたコンピュータの、基本的な仕組みを知ってもらうことを目的とした講習会を行いました。DOS-Vパソコンの組み立てを通して、コンピュータの歴史や内部構成を学びます。 組み立て作業のところどころで、コンピュータの歴史や構成要素についての講義の時間を取る形で進めました。全員、コンピュータの組み立てと、Linuxの起動までを行うことができました。 | ||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 10名(13名) | ||||||||||||||
|
|
講演会記録 中高生向け講演会
e-Gadgetを用いたロボット制御
| 日 時 | 平成25年8月2日(金) 10:00~16:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 大阪府立大学工業高等専門学校(寝屋川) | ||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | 昨年度に続き、中高生を対象にロボット制御の講習会を行いました。参加者には、最初の1時間、「ロボットの歴史と未来」と題した講義を受けてもらい、残りの4時間でロボット制御に取り組んでもらいました。ロボット制御には、ロボットキットe-Gadgetを用いました。これは、実際に動かしながら制御プログラムを学ぶためのキットです。 参加者は課題を着実にこなし、用意していた課題のほぼすべてをクリアしました。最後に、自作のプログラムでライントレースのタイムトライアルを行いまして、今年も参加者全員が完走しました。 | ||||||||||||
| 参加者(申込者) | 13名(16名) |
見学会記録 電気四学会関西支部 一般見学会
(1) 西日本電信電話株式会社 大阪支店オープンハウス
(2) ものづくりビジネスセンタ大阪 MOBIO
| 日 時 | 平成24年11月9日(金) 9:40~16:20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||
| 要 旨 | 本年度の見学会では、“西日本電信電話株式会社 大阪支店オープンハウス”と、“ものづくりビジネスセンタ大阪 MOBIO”を見学しました。 西日本電信電話株式会社 大阪支店オープンハウスでは、安心・安全な情報通信サービスの安定的な提供を支える「交換設備」、「伝送設備」、「線路設備(ケーブル、とう道等)」、「電力設備」を見学させていただきました。世界でも高品質を誇る日本の通信を支える大阪府下で総長100km近い"とう道"など各種設備を見学するとともに、情報通信設備の移り変わりについても学ばせていただきました。 また、ものづくりビジネスセンタ大阪では、「大阪のものづくり中小企業の現状や課題」と、「大阪府のものづくり支援」についてお話を聞かせていただくとともに、ものづくり企業の紹介、さらには当センタにおける価値創造、ビジネスマッチング、交流の促進、並びに産官学連携に向けた取組についてご紹介いただきました。 両見学先とも、質疑応答の時間をいただき、有意義な見学をさせていただきました。 | ||||||||||
| 参加者(申込者) | 14名(15名) | ||||||||||
|
|
専門講習会記録 電気四学会関西支部 専門講習会
「周波数再編とホワイトスペース ~周波数割り当ての今後の見通しと新たな無線活用の動向~」
| 日 時 | 平成24年11月2日(金) 9:55~16:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||||
| 要 旨 | 有限な無線周波数の有効利用に向けて、周波数割り当ての再編成が行われています。また、デジタル技術の進展により、地理的条件や時間的条件によって他の目的にも利用可能な周波数帯(いわゆる「ホワイトスペース」)が生まれ、“安心・安全の確保”や新たなサービスに利活用する動きも活発化しています。 本専門講習会では、周波数再編の全体概要,現時点での検討状況、および今後の新たなサービス展開について、最前線でご活躍の専門家の方々に幅広くご紹介頂きました。 | ||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 29名(30名) | ||||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電気四学会関西支部 ICT基礎講座
「OFDM通信基礎講座(無線通信基盤技術と光通信への展開)」
| 日 時 | 平成24年10月4日(木) 9:40~16:50 |
|---|---|
| 内 容 | 講師:吉田 悠来 大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 助教 講義内容
参考書:J. Proakis, Digital communications, McGraw-Hill |
| 要 旨 | 50年余にわたるOFDM通信の歴史は、再発見の連続であった。本講座では、OFDM方式の歴史を辿ることから始め、なぜ今日OFDM方式が通信分野においてこれほど広く用いられるのかを、その数学的背景を含めてご説明いただきました。また、今後OFDM方式を実際に応用する研究者・技術者のために、通信の確立までに要求される物理層の信号処理技術について解説をしていただきました。 さらに、光ファイバ上のOFDM通信を取り上げ、実験室で光OFDM通信を導通するまでの流れに関してもご説明いただきました。 聴講者からは、歴史的背景や基礎から応用までの幅広い分野を分かり易く講義をしていただき、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
| 参加者(申込者) | 11名(12名) |
|
講演会記録 電気四学会関西支部 学生会
「見学会・講演会」
| 日 時 | 平成24年9月6日(木)13時00分~16時10分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | Panasonicセンター大阪(大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号) | ||||
| 内 容 |
|
||||
| 要 旨 | 【見学会】家まるごと、町まるごとスマートライフとして、CO2ゼロの生活実現をめざした環境ソリューションの提案が説明された。また、3Dビエラ、インターネット接続ビエラなど、新しい生活スタイルの展示を見学した。環境革新企業を目指して生まれ変わろうとするパナソニックの意気込みが感じられました。 【講演会】省エネ技術開発の現状が紹介され、その具体的な取り組みとして海外プロジェクトが紹介された。特に、大連、シンガポールでの海外プロジェクトの特徴、日本における特区としての取り組み(藤沢市)での違いが興味深く、勉強になりました。 |
||||
| 参加者(申込者) | 31名(34名) | ||||
|
ICT基礎講座記録 電気四学会関西支部 ICT基礎講座
「統計的学習理論講座」
| 日 時 | 平成24年8月30日(木)、8月31日(金) 両日とも9:40~16:50 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
講師:池田 和司 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 【1日目】講義内容
【2日目】講義内容
参考書:C.M.ビショップ 「パターン認識と機械学習(上・下)」 (シュプリンガー・ジャパン) |
||||||||||||||||
| 要 旨 | 情報爆発といわれる現代では,センサと通信技術の発達により、大量のデータが比較的安価に入手できます.この宝の山から有益な情報を抽出するには,計算機を利用した統計的手法が必要です。本講座ではその方法論である統計的機械学習について,基本的な考え方と手法を紹介することを目的として講義をしていただきました。講義1日目は確率統計の基礎や基本的な事項について,講義2日目は比較的進んだ話題について,簡単な計算演習を交えながら概説していただきました。 聴講者からは、基礎から応用までの幅広い分野を分かり易く、また演習を取り入れた講義をしていただき、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 7名(7名) | ||||||||||||||||
|
講演会 電気四学会関西支部講演会
「スマートな社会・都市デザインのための電子情報通信技術」
| 日 時 | 平成24年8月29日 14:00~17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | エネルギー効率を高め、環境配慮を徹底したスマートな社会・都市の実現に向けた取り組みが進められており、その中でも様々な電子情報通信技術が活用されつつあります。 本講演では、(1)都市づくりのインフラを支えるスマートエネルギー(2)健康を支えるネットワークヘルスケアやホームメディカルケア(3)来春街開き予定の「うめきた」を題材にした都市デザイン/サービスの3つの視点から、そこで活用されている電子情報通信技術を切り口に最新動向や研究開発・実用化事例について3名の専門家の方よりご講演いただきました(写真は当日の講演の様子。左:石井先生、右:中嶋先生)。 会場からはスマートエネルギー領域におけるインフラのインターフェース標準化動向や遠隔制御におけるセキュリティ問題、ネットワークヘルスケアにおけるクラウドデータが大量に集まることで新たに得られる知見、まちづくりに必要なソフト・ハード的要素の役割などについての質問や、それにもとづく議論などが活発におこなわれたとともに、講演内容に対し理解度/有意義性の両方の観点から高い評価をいただきました。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 31名(40名) | ||||||||||||
|
講演会記録 中高生向け講演会
「e-Gadget-TTを用いたロボット制御」
| 日 時 | 平成24年8月9日(木) 10:00~16:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 大阪府立大学工業高等専門学校 情報技術実習室(寝屋川市幸町26-12) | ||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | 中高生を対象にロボット制御の講習会を行いました。最初に「ロボットの歴史と未来」と題した講義を1時間行い、次いでロボットを動かしてもらいます。実際に動かしながら制御プログラムを学ぶことができるロボットキットe-Gadget-TTを用いています。 講師の指示が終わらないうちから、早速プログラミングに取り組む様子が印象的でした。最後に、自作のプログラムでライントレースのタイムトライアルを行い、全員完走することができました。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 8名(10名) | ||||||||||||
|
講演会記録 中高生向け講演会
「コンピュータの内部について学ぼう!!」
| 日 時 | 平成24年8月7日(火) 10:00~16:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 大阪府立大学工業高等専門学校 情報技術実習室(寝屋川市幸町26-12) | ||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | DOS-Vパソコンの組み立てを通し、コンピュータの歴史や内部構成を学ぶ講習会を行いました。身近なものになり過ぎたコンピュータの、基本的な仕組みを知ってもらうことを目的としています。 参加者が全員中学生だったこともあり、パソコンの組み立ては初めてであったようです。組み立てのところどころで、講義の時間を取る形で進めました。全員、OSのインストールまで完了し、講義の方も熱心に聞いてもらえました。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 8名(10名) | ||||||||||||
|
ICT基礎講座記録 電気四学会関西支部 ICT基礎講座
「画像処理講座」
| 日 時 | 平成24年8月2日(木)、8月3日(金) 両日とも9:40~16:50 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
講師: 浦西 友樹 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 中島 悠太 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教 【1日目】講義内容
【2日目】講義内容
参考書:詳解 OpenCV, G. Bradski and A. Kaehler(著), 松田 晃一(翻訳), オライリージャパン |
||||||||||||||||
| 要 旨 | 画像処理プログラミングの基礎,および画像処理ライブラリOpenCVの導入から基礎を2日間にわたって解説していただきました。講義1日目は,OpenCVのPCへのインストールとカメラ画像の取り込みおよびファイル画像の読み込みから始め,基礎的・実践的な画像処理の理論および方法についてご説明いただきました。講義2日目は,実践的な画像処理についての講義と共に,OpenCVによる実装を通して理論及び使用方法をご説明いただきました。 聴講者からは、基礎から応用までの幅広い分野を分かり易く、また実習を多く取り入れた講義をしていただき、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
||||||||||||||||
| 参加者(申込者) | 4名(5名) | ||||||||||||||||
 |
講演会記録 電気四学会関西支部 講演会
「ライフログの現状と可能性」
| 日 時 | 平成24年1月27日(金)13時00分~17時00分 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 中央電気倶楽部 513号室(大阪市北区堂島浜2-1-25) | ||||||||||||
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | 携帯電話端末の高度化や情報通信機器のパーソナル化の進展によって、個人の生活行動に関する各種情報を収集し活用する「ライフログ」が注目を集めています。本講演会では、このライフログの活用においてさまざまな立場で取り組んでおられる、日本を代表する専門家の方々をお招きして、ライフログを取り巻く現状や具体的な応用事例、将来の展望についてご講演いただきました。 聴講者からも、ライフログの課題に対する取り組みについての質問など活発な議論を頂き、有意義であったとの評価を頂きました。 |
||||||||||||
| 出席者数 (申し込み者数) |
39名(49名) | ||||||||||||
 |
講演会記録 電気四学会関西支部 講演会
「無線通信の高度化と医療分野との連携の可能性について」
| 日 時 | 平成23年11月25日(金) 14:00~17:00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 容 |
|
||||||||||||
| 要 旨 | いつどこにいても被検者から血圧、呼吸などの生体情報を送受信できるユビキタス医療・ヘルスケアネットワークの実現や、手術室のオートメーション化を狙いとした内視鏡映像データの活用など、医療分野における通信技術利用ニーズは高まりつつあります。 本講演会では、新産業への応用に向けた研究開発・実利用が進められているテラヘルツ波を用いた無線技術、身につけた機器や体内埋め込み機器との通信に利用される無線ボディエリアネットワーク(BAN : Body Area Network)への取り組みと標準化の推進状況、最先端IT機器を活用した医療分野での先進的な取り組みについて、3名の専門家の方にご講演いただきました。(※写真は講演の様子。写真上:永妻先生、写真下:杉本先生) 聴講者からは、技術の医療以外への応用可能性や、国際的なアライアンスの状況、日本の技術競争力などについて質問が寄せられた他、有意義な講演であったと評価いただきました。 |
||||||||||||
| 参加者(申込者) | 24名(32名) | ||||||||||||
|