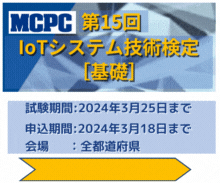ジャンル別 特別小特集
| Vol.107(2024) | ||
|---|---|---|
| 1月号 | DAO(分散型自律組織)の可能性について | |
| 編集にあたって | 佐波 孝彦 | |
| DAOの概要とポテンシャル | 豊田 健太郎 | |
| DID(Decentralized Identity)の現状と今後の研究動向について | 小松 隆、中村 聡 | |
| DEVプロトコルの概要とDEVプロトコルが支援するトークン経済圏のフレームワークについて | 原 麻由美 | |
| 学術活動のためのDAOの設計と実装 | 髙木 徹, 角田 仁 | |
| Vol.106(2023) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | Artificial Intelligence of Things (AIoT) for Smart Farming | |
| Editorial Preface | Yee-Loo Foo | |
| Image-based Classification of Leaf Diseases Using Convolutional Neural Networks | Muhammad Umair、Wooi-Haw Tan、Yee-Loo Foo | |
| Oil Palm Fresh Fruit Bunch Detection and Ripeness Classification Using YOLOv5 | Mohamed Yasser Mohamed Ahmed Mansour、Katrina D. Dambul、Kan Yeep Choo | |
| Mm-wave and THz Scanning for Non-invasive Farm Product Safety | Nguyen NGOC MAI-KHANH、Shintaro TAKADA、Keizo INAGAKI、Tran NGOC LE、Tran THI MY HANH、Hinano SUGIMOTO 、Akio HIGO、Hitoshi TABATA、Makoto IKEDA、Bich-Yen NGUYEN、Tetsuya KAWANISHI | |
| Wireless Sensor Network Optimization in Agriculture:Brief Review and Case Study Using 2.4GHz Transceivers | Wei Kitt WONG、Saaveethya SIVAKUMAR、Filbert H. JUWONO、Ing Ming CHEW | |
| 1月号 | 画像の高画質変換技術の最新動向 | |
| 編集にあたって | 髙村 誠之 | |
| 画像復元における分析・合成システム | 村松 正吾 | |
| カラー動画像雑音除去の最新動向 | 小松 隆、中村 聡 | |
| 高画質映像の品質評価技術 | 恵木 則次、山岸 和久、増田 征貴 | |
| ディスプレイの高画質化技術動向 | 薄井 武順 | |
| 映像フレームレート変換の技術動向 | 川田 亮一 | |
| ポストH.266/VVCに向けた最新映像高画質化処理 | 鈴木 拓矢、猪飼 知宏、中條 健、伊藤 典男 | |
| Vol.105(2022) | ||
|---|---|---|
| 1月号 | ネットワーク数理の新潮流 | |
| 編集にあたって | 笠原 正治 | |
| BDDを用いたネットワーク信頼性評価手法の進展 | 井上 武 | |
| ネットワーク上のデータのためのサンプリング定理──グラフサンプリング定理とその応用── | 田中 雄一 | |
| 無線ネットワークにおける連合機械学習 | 西尾 理志 | |
| 確率幾何アプローチによる無線通信ネットワークの性能解析 | 木村 達明 | |
| 複雑ネットワーク解析における非バックトラック | 小蔵 正輝 | |
| Vol.104(2021) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 特別小特集 ニューノーマル時代に求められる,ディジタルトランスフォーメーション(DX) | |
| 編集にあたって | 秋山 大 | |
| 子供の興味や発達を考慮した育児・教育支援の新しい「かたち」を探して | 小林 哲生 | |
| 高専における新型コロナウイルス対応後の教育のICT化──遠隔授業を想定した教育のICT化の変化── | 長尾 和彦、田房 友典 | |
| 香川大学DX化技術支援室の設置とその取組みについて | 八重樫 理人、後藤田 中、米谷 雄介、國枝 孝之 | |
| 高知県におけるNext次世代施設園芸農業IoP(Internet of Plants) | 福本 昌弘、北野 雅治、藤原 拓 | |
| プロアクティブなり障予測とレジリエントな復旧対応について | 仲 憲顕 | |
| 災害時に求められる自動車の新しい機能とその実用化──災害対応形水陸・空陸両用電気自動車の開発── | 山中 建二 | |
| 1月号 | 産業の新たな変革をけん引するICT | |
| 編集にあたって | 川端 明生 | |
| 持続可能な保険医療を支えるヘルスケア分野のAI応用 | 伴 秀行、近藤 洋史、長谷川 泰隆、竹内 渉 | |
| 金融情報システムにおける情報通信技術の貢献と今後の期待 | 岩下 直行 | |
| 流通・物流における情報システムのこれから | 浅野 耕児 | |
| 複数ロボットの遠隔制御による協調搬送システム | 吉田 裕志 | |
| 視聴者ごとの見たい・聴きたいを実現する音メディア技術 | 堀内 俊治 | |
| Vol.103(2020) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | AI時代の持続可能な地方分散社会を目指して | |
| 編集にあたって | 芥子 育雄 | |
| 北陸近未来ビジョン─2030年代中頃の北陸のありたい姿─ | 久和 進 | |
| ふくい×AI─未来の幸せアクションリサーチ─ | 細川 善弘、須藤 一磨 | |
| AI/IoTを活用するためのイノベーションデザイン手法の地域課題解決への適用 | 内平 直志、梅野 真也、岡田 将吾 | |
| IoTを活用した分散形雨水活用システムの構想と離島における実証実験 | 笠井 利浩 | |
| AI時代の自動運転最前線と永平寺町におけるラストマイル自動走行の実証評価 | 加藤 晋 | |
| AI時代のブロックチェーン最前線と地域活性化への活用提案 | 古瀬 正浩 | |
| 1月号 | いよいよ開催,オリンピック・パラリンピック─2020年に花咲く技術─ | |
| 編集にあたって | 石原 智宏 | |
| 超高臨場感通信技術の取組み | 南 憲一、宮武 隆、深津 真二、外村 喜秀、堤 公孝 | |
| 〜特別インタビュー〜オリンピック・パラリンピックを迎える東京都からのメッセージ―電子情報通信学会誌特別小特集に寄せて― | 小池百合子、山中 直明、佐々木 経世 | |
| 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたパブリックセーフティ | 横山 登、山際 昌宏 | |
| 音声翻訳サービスによる多言語コミュニケーション支援 | 内山 健、内田 渉、喜内 久雄、礒田 佳徳 | |
| 3Dセンシング・技認識による体操採点支援 | 桝井 昇一、手塚 耕一、矢吹 彰彦、佐々木 和雄 | |
| Vol.102(2019) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 北で輝く光科学技術の研究 | |
| 編集にあたって | 荒木 健治 | |
| 回折イメージングの情報 | 塩谷 浩之、郷原 一寿 | |
| 透明媒質表面の微細構造と光反射 | 酒井 大輔 | |
| 半導体量子ドット結晶が実現する新しい光機能性 | 村山 明宏 | |
| 量子暗号通信の最前線 | 富田 章久 | |
| ディジタル信号処理技術が開く超100Gbit/s短距離光通信システム | 佐々木 愼也 | |
| ナノ粒子の光マニピュレーション | 笹木 敬司 | |
| 1月号 | 新しい時代の知的財産戦略を考える | |
| 編集にあたって | 糸田 純 | |
| 第四次産業革命下における我が国の知的財産戦略――データとAI利活用社会に関する施策を中心に―― | 渡部 俊也 | |
| 研究者が特許を出した方がいい理由についての一考察 | 鮫島 正洋 | |
| 未来社会の知的財産戦略ビジョン | 住田 孝之 | |
| 経営学から見た「知的財産ミックス」 | 杉光 一成 | |
| 無線通信の発展を支えた知的財産戦略及び標準化戦略の歩みと今後の課題 | 鶴原 稔也 | |
| 我が国の産学連携の現状と東京大学におけるイノベーション創出 | 山本 貴史 | |
| iPS細胞技術の特許ライセンス | 工藤 周三 | |
| 社会共生型特許活用/a> | 広瀬 勇一 | |
| Vol.101(2018) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | イノベーションによる,地域の活性化に向けて──IoT,ビッグデータ,AIの現状とその次の未来の視点から,信越地区を例にとって── | |
| 編集にあたって | 木竜 徹 | |
| 持続的農業生産とインダストリー4.0 | 二宮 正士 | |
| ディジタルが開く地方創生 | 森川 博之 | |
| 安全・安心な地域を支えるセンサネットワークの構築・人材育成 | 不破 泰 | |
| 脳波のフラクタル解析を用いた多機能電話の操作性評価 | 中川 匡弘 | |
| データ可視化によるECHIGOイノベーション構想 | 山﨑 達也 | |
| 産業界からの期待と未来展望――パネルディスカッション要旨―― | 仙石 正和 | |
| Vol.100(2017) | ||
|---|---|---|
| 1月号 | 電子情報通信学会の今後100年に向けて──未来をひらく新しい科学研究への期待と展望── | |
| Future of Edge Cloud | Katherine GUO、Krishan SABNANI、Arun N. NETRAVALI | |
| IoTと人工知能に基づく新しい社会 | 岡野原 大輔 | |
| 編集にあたって | 伊東 匡 | |
| コンテンツプラットホームにおける機械学習,データセット公開・モデル公開による産学の発展 | 小田桐 優理 | |
| 社会課題を解く視点からの提言――人に尊重される健康と医療のデザイン―― | 友池 仁暢、塚田 信吾、江崎 禎英、山口 類、井元 清哉、宮野 悟 | |
| Vol.99(2016) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 地方創生,中国地方を元気に! | |
| 編集にあたって | 堀田 昌志 | |
| [島根発]Rubyを用いて構築した汽水域水質の準リアルタイムモニタリングシステム | 下舞 豊志 | |
| [鳥取発]鳥取県内の地域コミュニティにおける保健医療福祉システムへの取組み | 櫛田 大輔、松本 浩実、深田 美香 | |
| [広島発]産学官医連携体制による高齢者見守り支援システムの研究開発 | 谷口 和弘 | |
| [岡山発]テラヘルツ計測システム開発プロジェクト | 紀和 利彦 | |
| [山口発]「やまぐちグリーン部材クラスター」の取組み | 只友 一行、戸嶋 直樹 | |
| Vol.98(2015) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 東海発ワイヤレス | |
| 編集にあたって | 大平 孝 | |
| スマートフォンによるセンシングとモバイルネットワークを用いた見守りシステムTLIFESの実現 | 渡邊 晃 | |
| V2X通信技術の動向と将来展望 | 平山 泰弘、澤田 学 | |
| 頼れる無線制御を目指して | 片山 正昭 | |
| 車載センサネットワーク | 各務 学 | |
| 車載用ミリ波レーダ | 松沢 晋一郎 | |
| 在宅医療・介護情報の家庭内通信の国際標準化 | 水庫 功 | |
| 電波イメージングの医療分野への応用を目指して | 桑原 義彦 | |
| ワイヤレス電力伝送のkQ積理論入門 | 大平 孝 | |
| PHV/EVの非接触充電システム | 杉山 義信 | |
| 電気自動車に関わる電磁界に対する生体安全性の適合性評価技術 | 平田 晃正 | |
| 車載無線機器の評価法と国際標準化 | 花澤 理宏 | |
| 1月号 | 人間社会と調和する未来の電子情報通信技術への期待 | |
| 編集にあたって | 宮本 裕 | |
| 宇宙からの電子情報通信技術への期待 | 山崎 直子 | |
| 医療・ヘルスケアの現場から見たウェアラブル情報通信技術への期待 | 塚田 信吾 | |
| ニコニコ学会β――ユーザ参加型研究の最前線―― | 江渡 浩一郎 | |
| 技術の制御――制度の限界と社会科学的事後検証―― | 小林 哲郎 | |
| Powering the Democratization of Opportunity | Reiko A. MIURA-KO | |
| 若手からのメッセージ | 兼本 大輔、川嶋 喜美子、高武 直弘、榊 裕翔、佐々木 謙介、澤谷 雪子、田仲 理恵、広瀬 遥、森岡 康史、横山 良晃 | |
| 今後の日本の教育におけるICTのインパクトについて――オープンエデュケーションとMOOCをめぐる考察―― | 飯吉 透 | |
| Vol.97(2014) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | グリーンエネルギーとICT――九州における取組み―― | |
| 編集にあたって | 谷口 倫一郎 | |
| 電気事業の現状と,グリーンエネルギーにおけるICTの役割 | 岩崎 和人 | |
| スマートグリッドを支える通信システム | 貝崎 修治、田村 章、高橋 直雅、田頭 秀樹 | |
| 福岡スマートハウスコンソーシアムが描く未来のエネルギーシステム――複数のエネルギー源をいかにして融合し活用するのか―― | 中村 良道、有馬 仁志、黒川 不二雄 | |
| 太陽光発電出力の解析と予測――九州地区を例として―― | 村田 純一 | |
| マルチエージェント方式による再生可能エネルギー利用電源の運用と制御 | 檜山 隆 | |
| 沖縄・久米島から始まる海洋温度差発電の新しい展開――再生可能エネルギーにおける安定的な電源の役割を目指して―― | 池上 康之 | |
| 浮体式洋上エネルギーファーム──レンズ技術を利用した風力・水力の高効率取得── | 大屋 裕二 | |
| 九州地域での家畜排せつ物を用いた発電プラント | 鳥居 修一 | |
| 九州における地熱発電の現状と将来 | 糸井 龍一 | |
| 1月号 | 超成熟社会,発展のための科学と社会システム | |
| 編集にあたって | 山中 直明 | |
| 超成熟社会を発展させる経済学 | 竹中 平蔵 | |
| バーチャル座談会「超成熟社会,発展のための科学と社会システム」を考える | 山中 直明、石井 孝明、源田 浩一、廣瀬 明、麻生 英樹 | |
| 超成熟社会のリーダー人材育成 | 大西 公平 | |
| 超成熟社会を生き抜く,グローバル人材の姿 | 村上 憲郎 | |
| アジア社会から見る日本の超成熟社会の姿 | 猪口 孝 | |
| 超成熟社会と生活の質工学 | 金出 武雄 | |
| 超成熟社会を見据えたエネルギービジネスの将来像 | 藤原 洋 | |
| 超成熟社会を支えるスマートモビリティ | 永井 正夫 | |
| 超成熟社会に向けたイノベーション――プラチナ革命の時代―― | 小宮山 宏 | |
| Vol.96(2013) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 東北から明るい未来を創るICT技術 | |
| 編集にあたって | 亀山 充隆 | |
| 災害に強いネットワークと光通信技術 | 中沢 正隆 | |
| 移動通信事業者としての取組み | 荒木 裕二 | |
| 地域通信事業者としての取組み | 五十嵐 克彦 | |
| 被災地における一次情報取得と発信の重要性──原発事故に直面した地域の大学で── | 山口 克彦 | |
| 東日本大震災とVGI(Volunteered Geographic Information)について | 関 治之 | |
| 防災ロボットの未来 | 田所 諭 | |
| 垂直磁気記録技術と高密度情報ストレージ | 村岡 裕明、田中 陽一郎、高野 公史 | |
| スピントロニクスを用いた集積回路と省エネ社会への貢献 | 大野 英男、遠藤 哲郎、羽生 貴弘、安藤 康夫、笠井 直記、池田 正二 | |
| 画像処理技術とオープンイノベーションの展開 | 青木 孝文、伊藤 康一 | |
| 1月号 | Cool Japan を支えるICT 技術 | |
| 編集にあたって | 斎藤 洋 | |
| Cool Japanから見る日本のゲームが抱える課題と将来への可能性 | 新 清士 | |
| ゲーム開発を支えるミドルウェア | 新井 タヒル | |
| 携帯ゲーム機を支える最先端グラフィックス処理LSI 技術 | 大渕 栄作 | |
| 文化産業を支えるイノベーション──Cool Japanにおける技術と産業の連関── | 七丈 直弘 | |
| クリエータを支えるコンテンツ共有サイト | 戀塚 昭彦 | |
| 映画におけるCool JapanとICT 技術 | 藤井 哲郎、佐藤 一彦、白川 千洋 | |
| 歌声合成と新しい音楽 | 剣持 秀紀 | |
| Vol.95(2012) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 関西の伝統文化と先端産業技術 | |
| 編集にあたって | 高橋 達郎 | |
| 伝統行事のディジタルアーカイブ | 八村 広三郎 | |
| 白色LED照明の清水寺文化財照明への応用 | 島田 順一 | |
| 高松塚古墳壁画におけるディジタルアーカイブ | 宮内 康弘 | |
| 高精細・高品質のアウトプットに適したディジタル撮影及び画像処理技術について | 橋本 禎郎 | |
| 広がる,進化するタッチパネル技術 | 八代 有史 | |
| リチウムイオン電池の開発動向について | 湯浅 浩次 | |
| 関西発,宇宙への挑戦──まいど1号から大学衛星へ── | 大久保 博志 | |
| 太陽光発電出力変動分析のための日射強度推定技術 | 安並 一浩、井上 剛、鷲尾 隆 | |
| 1月号 | 学会から世界への学術情報発信──未来への展望── | |
| 編集にあたって | 今井 浩 | |
| 世界に向けての学術情報発信 | 安達 淳 | |
| 化学分野の学術誌の現在と学術情報流通の将来像 | 林 和弘 | |
| 電子情報通信学会会誌・論文誌による学術情報発信 | 酒井 善則 | |
| 大学図書館から見た電子ジャーナルの現状と課題 | 高橋 努 | |
| 学会から社会への情報発信 | 原島 博 | |
| Vol.94(2011) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | ICT 活用によるモニタリングシステムと関連技術 | |
| 編集にあたって | 服部 哲郎 | |
| オンデマンドモニタリングシステム技術(openATOMS)の開発と適用 | 中西 美一 | |
| 画像センサを用いた信号制御システム | 東久保 政勝、田中 佳代、山口 順一 | |
| 電源供給が不要な無線遠隔監視システム | 増田 眞一 | |
| けい動脈血流速度測定装置の開発 | 芥川 正武、榎本 崇宏 | |
| かがわ遠隔医療ネットワークK-MIX | 原 量宏 | |
| 香川衛星KUKAI と超小型衛星の環境モニタ利用への展望 | 能見 公博 | |
| 前方散乱法を用いた流星電波エコー自動方探システム | 山本 真行、埜口 和弥 | |
| 地球観測衛星「だいち」搭載立体視センサによる災害監視への取組み | 高木 方隆 | |
| 地域WiMAX による防災システム | 伊藤 直人 | |
| 漁場環境監視システムの開発 | 末永 慶寛 | |
| 1月号 | 情報通信分野のグローバル化にどう取り組むべきか?──外から見た我が国のICT 産業とR & Dへの期待── | |
| 編集にあたって | 三宅 功 | |
| 韓国におけるICT産業のグローバル展開の現状 | 朴 容震 | |
| グローバル時代の人材育成と地域協力 | 牛 志升 | |
| グーグルから見た日本ICT産業への苦言 | 村上 憲郎 | |
| 社会ニーズに基づく技術開発と日本への期待 | Ashir Ahmed | |
| 「テレビ放送」から「インターネット配信」へ──欧米におけるコンテンツ配信ネットワーク(CDN)サービスに見るグローバル化への取組み── | James F. RYAN | |
| 欧州のICT企業から見たグローバル化展開戦略 | 小津 泰史 | |
| Vol.93(2010) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 電磁波で紡ぐ北陸の自然と伝統・先端技術 | |
| 編集にあたって | 堀 俊和 | |
| 電磁波を利用した北陸の冬季雷観測とその特徴 | 川村 裕直 | |
| 光を用いた北陸の生き物の生体制御 | 平間 淳司 | |
| 伝統的な繊維産業における電波対策技術 | 吉村 慶之、打越 伸一、林 豊、登坂 俊英、西方 敦博 | |
| 三軸織物複合材の宇宙分野への応用 | 酒井 良次 | |
| 九谷焼とセラミック基板技術 | 毛利 護 | |
| ユビキタス社会を支えるアンテナ技術 | 斎藤 裕 | |
| 安心・安全を支えるRFID技術 | 小林 英樹 | |
| 1月号 | あの技術は今 | |
| 編集にあたって | 田中 良明 | |
| コンピュータ端末の元祖になった電信機「テレタイプ」 | 安岡 孝一 | |
| マイクロプロセッサの夜明け | 小檜山 智久 | |
| 伝票印刷で生き続けるインパクトプリンタ | 浅田 尚、石田 浩 | |
| 真空ナノエレクトロニクスへ進化し続ける真空管 | 中本 正幸 | |
| 科学技術演算向け言語Fortran | 黒澤 一平 | |
| Vol.92(2009) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 知の創出を支える次世代IT基盤技術──北海道大学グローバルCOEプログラムと北海道内情報通信系研究グループの活動── 北の国から明日のICTに架ける橋 | |
| 編集にあたって | 小柴 正則 | |
| 「知識創出学」とは? | 有村 博紀 | |
| 情報系異分野共同研究プロジェクト | 有村 博紀 | |
| 生命系異分野共同研究プロジェクト | 渡邉 日出海、金子 俊一、長谷山 美紀 | |
| ナノ系異分野共同研究プロジェクト | 末岡 和久 | |
| メディア系異分野共同研究プロジェクト | 宮永 喜一、吉澤 真吾、湊 真一 | |
| 北海道内情報通信系研究グループの活動 | 平山 浩一、鈴木 幸司、三木 信弘、真田 博文 | |
| 1月号 | 2030年の科学技術大予想 | |
| 編集にあたって | 山本 浩治 | |
| 2030年の映像制作 | 大口 孝之 | |
| グローバル視点から見た日本の未来 | 内海 善雄 | |
| 科学技術は地球と人類のために | 荒川 薫 | |
| 夢を語る | 松本 零士、塩本 公平 | |
| 地震発生予測とその未来像 | 板井 陽俊 | |
| 異種間の接面に着目して | 安部 素実 | |
| 科学技術の進展と世界の更なるフラット化 | 山本 高至 | |
| 「考える」TV | 髙橋 正樹 | |
| BNCによる「伝気通心」の実現 | 富永 英義 | |
| Vol.91(2008) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 自然災害からの復興の取組みと課題 | |
| 編集にあたって | 仙石 正和、島田 正治 | |
| 信越地域での自然災害における情報通信網の状況と対策 | 田中 宏雄 | |
| 地震からの復興に向けて──新潟県中越沖地震被災地から── | 宮澤 正幸、田口 太郎、田村 裕 | |
| 新潟県中越地震におけるGISを活用した被災地内外からの復旧・復興支援 | 澤田 雅浩 | |
| 新潟県中越沖地震に対する新潟大学医歯学総合病院の医療支援活動 | 畠山 勝義 | |
| 中山間被災地復興へ向けた無線ブロードバンド提供の実践的取組み──山古志ねっと共同実験プロジェクトの概要── | 間瀬 憲一、岡田 啓、大和田 泰伯 | |
| 高耐障害性アドホックネットワークシステム | 不破 泰 | |
| 洪水害減災に向けた河川水位ビデオ監視システム | 岩橋 政宏 | |
| 1月号 | 私の七転び八起き | |
| 編集にあたって | 森川 博之 | |
| 行く手を阻む絶壁と悪戦苦闘した日々──計算機れい明のころの秘話── | 渡部 和 | |
| 最先端ICTへの挑戦──失敗を経験し,次へたくましく── | 木戸出 正継 | |
| 人生の岐路考──本当に「人間万事塞翁が馬」なのか?── | 中島 秀之 | |
| 半導体メモリによる磁気ディスク置き換えへの挑戦 | 坂上 好功 | |
| 英語ダメ人間と国際規格作成 | 大賀 寿郎 | |
| テレビ電話とその標準化 | 大久保 榮 | |
| 技術者の先見性と進むべき道 | 古池 進 | |
| Vol.90(2007) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | ハイパヒューマン技術が開く新世界 編集にあたって | 山下英生 |
| 1.超速ハイパヒューマンビジョンとその応用 | 石井抱、山本健吉 | |
| 2.非接触硬さイメージャ | 金子真、岡島正純 | |
| 3.非侵襲高速眼剛性センシング | 栗田雄一、金子真、三嶋弘 | |
| 4.三次元を見せるグラフィックス技術 | 金田和文、三嶋弘、曽根隆志 | |
| 5.生体信号でロボットを自在に操る | 辻敏夫、島圭介 | |
| 6.超速ハイパヒューマンロボットシステム | 東森充、石井抱、金子真 | |
| 1月号 | 研究者・技術者の倫理観・人生観 編集にあたって | 篠原弘道 |
| 5.学術・技術分野における専門的職業人の使命と市民としてのモラル | 榊裕之 | |
| 6.研究者としての人生観 | 小林久志 | |
| 7.論文誌周辺の研究倫理 | 今井浩 | |
| 8.電波とともに生きた半世紀を振り返って | 桑原守二 | |
| 1.「史上空前の論文捏造」から考える科学の変容と倫理 | 村松秀 | |
| 9.ITによる社会構造の変容と情報倫理 | 辻井重男 | |
| 10.企業の技術者が報われるとき | 水谷幹男 | |
| 11.我が人生のコンパス | 関根征士 | |
| 12.光ファイバの研究開発を通じての雑感 | 大西正志 | |
| 13.情報倫理の本丸−私の倫理観,そして人生観− | 笠原正雄 | |
| 14.ニューヨークの小学校で10歳の私が学んだこと | 佐古和恵 | |
| 15.持続可能な情報環境を | 斎藤恵一 | |
| 2.若き技術者への期待−深みのある研究者になろう!− | 吉田進 | |
| 3.電子情報通信への思い | 小柴正則 | |
| 4.楽しむ研究、支え合う人生 | 外山比南子 |
| Vol.89(2006) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 最先端映像技術 −東海の挑戦− 編集にあたって | 谷本正幸 |
| 1.自由視点テレビFTV−「イ」の字から80年− | 谷本正幸 | |
| 2.CMOSイメージセンサ−Camera-on-a-chip− | 川人祥二 | |
| 3.映像・音声IP伝送の知覚サービス品質保証 | 田坂修二 | |
| 4.ディジタルヒューマン映像 | 栗山繁 | |
| 5.仮想化人体と医用画像診断支援−ナビゲーション型診断支援システム− | 森健策 | |
| 1月号 | 情感のコミュニケーション 編集にあたって | 酒井善則 |
| 障害のある人の情感コミュニケーション | 岡本明 | |
| 情動の表出と理解の神経機構 | 杉田陽一 | |
| 情感のコミュニケーションを活性化するメディア環境へ向けて | 片桐恭弘 | |
| 芸術の情感は工学で高められるのか | 林正樹 | |
| 感性情報の抽出と表現 | 井口征士 |
| Vol.88(2005) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | エレクトロニクスの新展開−未来を担う若者に向けたメッセージ− 編集にあたって | 香田徹 |
| 1.感性バイオセンサ | 都甲潔 | |
| 2.ロボット医療−ロボット手術を中心に− | 家入里志、田上和夫、橋爪誠 | |
| 3.次世代自動車の課題−運転支援を中心とした知能化自動車の視点から− | 高橋宏 | |
| 4.LSIの未来 | 後藤敏 | |
| 5.新世代放送受信チップ | 和田知久 | |
| 6.マルチメディア技術とマン・マシンコミュニケーション | 谷口倫一郎 | |
| 1月号 | 未来への手紙 編集にあたって | 須藤昭一 |
| 3.巨大システムの行末 | 当麻喜弘 | |
| 4.エージェント技術から見たテレビの未来像 | 宮崎勝、浦谷則好 | |
| 5.若手からのメッセージ | 鈴木智也、伊藤朋彦、永井祐介、山田徹、淺井裕介、齊藤研次、榎本敦之、マラットザニケエフ、荒武淳、熊野尚美、司城徹、新庄真太郎、大前良介、清本晋作、望月貴裕、松尾賢治 | |
| 1.2050年の経済大国 | 後藤尚久 | |
| 2.2025年の電子情報通信−20年前の芽は今− | 伊賀健一 |
| Vol.87(2004) | ||
|---|---|---|
| 1月号 | 2.DVD−技術と業界ニーズの結合による成功− | 山田尚志 |
| 3.高速無線LAN技術の誕生 | 守倉正博 | |
| 4.第3世代携帯電話(W-CDMA)国際標準暗号の誕生 | 松井充 | |
| 5.新しい光ナノ構造−フォトニック結晶− | 野田進 | |
| 発行にあたって | 吉田進 | |
| 1.ミューチップ−ユビキタスネットワークの世界を広げる砂粒チップ− | 宇佐美光雄、井村亮 |
| Vol.86(2003) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 発行にあたって | 小山正樹 |
| 1.龍安寺の石庭を科学する | ハルト・バン・トンダ、マイケル・ライオンズ、江島義道 | |
| 2.関西都市と芸能を科学する | 赤間亮、小島一成 | |
| 3.味と匂いのセンサからみた関西・日本文化 | 都甲潔 | |
| 4.くらし価値を育むこれからの家電に向けて | 渡邊和久 | |
| 5.「夢の実現」メイドイン東大阪 人工衛星計画 | 青木豊彦 | |
| アイデアは西から | 電子情報通信学会 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 岡本龍明 |
| 3.快適な暮らし | 中村英夫 | |
| 4.宇宙のロマン−宇宙をとらえる観測技術− | 鈴木敏一 | |
| 1.ものづくり−職人の技術− | 中村肇 | |
| 5.真理を求めて−日本人名のついた数学の理論− | 桂利行 | |
| 6.マニアの世界−日本文化としてのおたく− | 山形浩生 | |
| 2−1 認知発達ロボティクス−身体図式と共同注意を例に− | 浅田稔 | |
| 2−2 ヒューマノイドロボットと人間研究 | 高西淳夫 |
| Vol.85(2002) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 発行にあたって | 木内陽介 |
| 1.新規検出技術を用いた次世代マイクロDNAチップ | 山口央、三沢弘明 | |
| 2.血液成分分析バイオセンサ | 中井正、上甲茂樹 | |
| 3.ダイヤモンドDNAチップ「ジーンダイヤ(R)」の応用とプロテインチップ開発 | 木戸博、奥村裕司、日吉峰麗、坂東美和、木下盛敏、福田陽司 | |
| 4.マイクロテクノロジーのナノ・バイオへの適用 | 橋口原、大平文和 | |
| 5.マイクロCTで肺の微細構造を見る | 仁木登、河田佳樹、松井英介、森山紀之 | |
| 6.レーザ光を用いた非接触マイクロ操作技術 | 田中芳夫 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 宮原秀夫 |
| 3.スポーツのディジタル化について | 片山宗臣 | |
| 4.運動スキルへの計算論的アプローチ | 宇野洋二 | |
| 1.ゴルフインパクトの計測と弾道シミュレーション | 鳴尾丈司 | |
| 5.IT時代のスポーツマーケティング | 広瀬一郎 | |
| 2.スポーツにおけるビデオ処理技術の動向 | 越後富夫 |
| Vol.84(2001) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 発行にあたって | 村本健一郎 |
| 1−1 レーザレーダで大気環境を観る | 小林喬郎 | |
| 1−2 高出力遠赤外光による大気圏・環境リモートセンシング | 出原敏孝 | |
| 2−1 バイオセンサで環境を観る | 民谷栄一 | |
| 2−2 細胞外電位で植物の日周のリズムを観る | 中村清実 | |
| 3−1 画像処理で降雪を観る | 村本健一郎、椎名徹 | |
| 3−2 レーダで降雪を観る | 椎名徹、村本健一郎 | |
| 4−1 電磁波で産業・医療現場の環境を観る | 深見哲男、桜野仁志、小島一彦、長野勇 | |
| 4−2 低周波数交流磁界で生化学的影響を観る | 山田外史、山本博 | |
| 5−1 ヘリコプターで植生を観る | 久保守、鎌田直人、川西琢也 | |
| 5−2 衛星画像データの定量的解析 | 川田剛之 | |
| 5−3 シミュレーションで地球環境を観る | 堀口進 | |
| 著者紹介 | 電子情報通信学会 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 佐野浩一 |
| 2.マルチメディア信号処理 | 西谷隆夫 | |
| 3.量子計算と量子情報通信−何が可能になるのか− | 竹内繁樹 | |
| 1.次世代インターネット技術 | 村井純 | |
| 4.ナノフォトニクスとその展望 | 大津元一 | |
| 5.非線形問題を解く道具としての精度保証付き数値計算 | 大石進一 | |
| 6.RoboCup-Rescue | 北野宏明、田所諭、RoboCup-Rescue技術委員会 | |
| 7.コミュニティネットワークの発展に期待する | 山口治男、藤原洋、宮沢正幸、福田豊、坂巻資浩、三木哲也 | |
| 8.大学における技術者教育と改革の方向 | 篠田庄司 |
| Vol.83(2000) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 青木由直 |
| 1.画像で見せる−CG技術のヒューマンコミュニケーションへの応用− | 青木由直、山形積治 | |
| 2.画像をさばく−画像処理とその応用− | 下野哲雄、北島秀夫、前田純治 | |
| 3.画像をあやつる−仮想現実感とその応用− | 伊福部達、川嶋稔夫 | |
| 4.画像で見る−可視化技術とその応用− | 青田昌秋、飯田浩二、小柴正則、清水孝一、山本克之 | |
| 5.画像で伝える−ネットワーク・放送と画像技術− | 加治屋安彦、山本強、藤原祥隆 | |
| 1月号 | 1−3 テレビジョンの登場と進化 | 西沢台次 |
| 2−1 フィルタ理論から信号処理論への展開 | 古賀利郎 | |
| 2−2 ディジタル通信 | 青木利晴、行松健一、佐藤健一 | |
| 2−3 半導体レーザの歩み−光エレクトロニクスのキーデバイスとして− | 末松安晴 | |
| 発行にあたって | 西谷隆夫 | |
| 2−4 コンピュータビジョン | 金出武雄 | |
| 1−1 トランジスタの誕生 | 菊池誠 | |
| 1−2 日本における計算機の歴史と発展 | 弓場敏嗣 |
| Vol.82(1999) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 木下真二郎 |
| 1.有限体のフーリエ交換に憑かれて | 杉村立夫 | |
| 2.量子計算と量子暗号 | 松枝秀明 | |
| 3.Large Deviation Theoryの待ち行列特性評価への応用 | 中川健治 | |
| 4.シグナルプロセッシングアレーとモバイル通信 | 山田寛喜、山口芳雄、仙石正和 | |
| 5.周波数有効利用技術におけるグラフネットワーク理論の適用 | 佐藤拓朗、田村裕、阿部武雄 | |
| 6.プルーフチェッカを用いたLSI回路設計の正しさの検証−演算用,通信用LSI等− | 中村八束 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 佐藤健一 |
| 3.カーボンナノチューブ:発見の背景 | 飯島澄男 | |
| 4.マイクロコンピュータ開発における新しい概念の創造活動 | 前島英雄 | |
| 1.2足歩行ロボット開発への挑戦 | 平井和雄 | |
| 5.ディジタルメディア時代のヒューマンインタフェース研究の魅力 | 竹林洋一 | |
| 6.インターネット研究分野の開拓 | 村井純 | |
| 2.青色発光デバイス開発における創造性 | 中村修二 |
| Vol.81(1998) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 吉田典可 |
| 1.階層構造の脳型コンピュータ | 阿江忠 | |
| 2.WSI(ウェーハスケール集積)におけるフォールトトレランス | 高浪五男、松野浩嗣 | |
| 3.アナログ・ディジタル融合回路による知能処理LSI | 岩田穆、永田真、森江隆 | |
| 4.単電子回路による知能集積デバイスの可能性 | 雨宮好仁、岩田穆、広瀬全孝 | |
| 5.システムオンシリコン時代を支えるCAD技術 | 若林真一、渡辺孝博、小出哲士 | |
| 6.システムのインテリジェント化を支えるディジタル設計教育 | 高橋隆一、吉田典可 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 白川功 |
| 3.学生ベンチャー企業として | 藤原礼征 | |
| 4.21世紀の新規事業を目指して | 福島博昭 | |
| 1.ベンチャー事業事始め | 伊東正展 | |
| 5.私が起業した理由 | 浮川和宣 | |
| From Idea to IPO:The Venture Process in Sillicon Valley | Alain ROSSMANN | |
| 2.社内起業家制度で誕生したベンチャー企業 | 白田耕作 |
| Vol.80(1997) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 畑雅恭 |
| 1.交通システムのインテリジェント化は社会を変えるのか? | 森川高行 | |
| 2.交通システムの高度情報化と交通ネットワーク流の予測・制御理論−過去・現在・未来− | 赤松隆 | |
| 3.将来の航空宇宙交通輸送のための電子システム | 鈴木智、松岡芳人 | |
| 4.自動車用レーダとその応用 | 所節夫 | |
| 5.将来の交通システムにおける自動料金収受 | 時津直樹 | |
| 6.未来の交通システムのためのアンテナ技術 | 菊間信良 | |
| 1月号 | 2−1 わかりやすい技術論文の書き方 | 酒井善則 |
| 2−2 英語論文をわかりやすく書く方法 | 池辺八洲彦 | |
| 2−3 技術文書を効率的に作る最新テクニック | 梅木秀雄 | |
| 3−1 文献検索と電子図書館−より多くの人に読んでもらうために− | 飯田元、小山正樹 | |
| 発行にあたって | 太田直久 | |
| 3−2 学会の取組み−これからの情報発信に向けて− | 太田直久 | |
| 1.初夢−21世紀における技術情報の発信はこうなる− | 浅見徹 |
| Vol.79(1996) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 上野文男 |
| 1.回路とシステム理論をめぐって−教育と研究の諸相− | 古賀利郎 | |
| 2.常識としての計算機教育 | 安浦寛人 | |
| 3.VLSIの開発設計の現場から教育に期待する−シリコンアイランドからのメッセージ− | 杉渕清 | |
| 4.スイッチング電源とエネルギーエレクトロニクス | 原田耕介 | |
| 5.自然言語処理から感性情報処理へ | 吉田将 | |
| 6.通常資源から知識資源へ | 牛島和夫 | |
| 1月号 | 1−3 コンピュータシステムの状況 | 竹井辰典、宮地輝雄 |
| 1−4 神戸大学からの報告 | 樽磨和幸、蛯名邦禎、大月一弘、田中克己 | |
| 1−1 阪神・淡路大震災における通信サービスの状況 | 武井務 | |
| 1−5 インターネットによる災害情報の流通 | 法林浩之 | |
| 2−1 阪神・淡路大震災における通信サービスの課題 | 高島秀行、石川宏 | |
| 2−2 通信機器の耐災害設計 | 青田陽悦、川井睦美、池田連也 | |
| 2−3 コンピュータ機器の地震対策 | 柳田真理雄、椿信男、松村唯伸、内田康彦 | |
| 地震予知のための情報ネットワーク | 鷹野澄 | |
| 1−2 衛星通信の利用状況 | 野原光夫、小林英雄 | |
| 発行にあたって | 小林功郎 |
| Vol.78(1995) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 1−1 国際動向と課題 | 正田英介 |
| 1−2 EMI測定サイト | 杉浦行 | |
| 1−3 アンテナ−EMC/EMIにおける特性とその測定− | 岩崎俊 | |
| 1−4 近傍電磁界問題 | 沢谷邦男 | |
| 2.情報通信関連機器のイミュニティに関する規制の動向−世界の動向,我が国の対応− | 雨宮不二雄 | |
| 3−1 球状ダイポールアンテナ | 徳田正満 | |
| 3−2 イミュニティ試験法−通信線に現れる誘導電圧に対する取組み− | 井手口健 | |
| 3−3 電磁環境シミュレータ | 井上浩 | |
| 4−1 ステップ応答波形の解析による電気的特性の測定 | 馬場健造 | |
| 4−2 タイムドメイン測定法 | 佐藤由郎、堀田幸雄 | |
| 5−1 金属物体で発生する静電気放電(ESD)の脅威 | 本田昌実 | |
| 5−2 ESD現象をとらえるソースモデルと界特性 | 藤原修 | |
| 6.EMC/EMI問題と大学の基礎研究 | 仁田周一 | |
| 発行にあたって | 山口宏二 | |
| 大学の先生方へのお願い | 高木相 | |
| 1月号 | 2.テレパシー通信 | 関英男 |
| 3.植物との対話 | 三輪敬之 | |
| 4.社会性をもつロボット | 国吉康夫 | |
| 5.夢の科学 | 井上昌次郎 | |
| 発行にあたって | 加藤修三 | |
| 1.SFがSFでなくなる日 | 石原藤夫 |
| Vol.77(1994) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 1.情報通信と社会 | 村上陽一郎 |
| 2.文化の中の技術 | 杉田繁治 | |
| 3.情報通信と政治・経済 | 今井賢一 | |
| 4.マルチメディア時代に向けた我が国の状況−情報通信基盤の整備− | 秋山稔 | |
| 5.マルチメディア時代の情報基盤 | 貝淵俊二 | |
| 6.マルチメディアと著作権−コピー・マート(COPYMART):著作権市場論− | 北川善太郎 | |
| 7.標準化動向−パラダイムの変革− | 安田浩 | |
| 発行にあたって | 葉原耕平 | |
| 1月号 | 2−2 大量に伝える−光ファイバによる超大容量通信− | 秋葉重幸 |
| 子孫へ伝える−遺伝情報の伝達− | 石浜明 | |
| 3−1 翻訳して伝える−国際自動翻訳電話− | 森元逞 | |
| 3−2 感性で伝える−感性情報処理− | 野口正一 | |
| リアルに伝える−バーチャルリアリティ− | 広瀬通孝 | |
| 2−1 遠くへ伝える−宇宙空間での超遠距離通信− | 高野忠 | |
| 発行にあたって | 渡辺貞一 |
| Vol.76(1993) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 1.色の変る蛍光ランプ | 青野正明 |
| 2.InGaN青色発光ダイオード | 中村修二 | |
| 3.シリコン上集積化光源 | 酒井士郎 | |
| 4.メソスコピックOEIC | 松枝秀明 | |
| 5.光磁気記録の信号処理 | 田崎三郎 | |
| 6.光磁気記録システム | 伊藤秀彦 | |
| 7.光を用いたミカンの測定 | 戸井田秀基 | |
| 発行にあたって | 大西秀臣 | |
| 1月号 | 2−1 高齢化社会におけるロボット技術 | 米田隆志、舟久保煕康 |
| 2−2 福祉機器と研究開発 | 高山忠雄 | |
| 2−3 高齢化社会における情報通信技術−ライフラインシステムを考える− | 高橋紘士 | |
| 3−1 高齢者保健福祉システムの課題 | 村川浩一 | |
| 3−2 高齢化社会と産業構造 | 原豊 | |
| 4.人生の達人が語る | 只野文哉 | |
| 1−1 高齢化社会の予測 | 高橋重郷 | |
| 1−2 高齢化社会と社会生活 | 小笠原祐次 | |
| 1−3 脳の老化とその対策 | 植村研一 | |
| 発行にあたって | 山口治男 |
| Vol.75(1992) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 1.神経情報工学とエレクトロニクス | 八木寛 |
| 2.声の音響分析による声帯疾患の診断 | 小泉卓也 | |
| 3.不整脈の外科的治療へのコンピュータ利用 | 船田哲男、三崎拓郎 | |
| 4.フロー方式による生体細胞の計測方法 | 谷口慶治 | |
| 5.画像計測・信号解析の医療への応用 | 松浦弘毅、村本健一郎、堀田素志 | |
| 6.失われた機能をとりもどす | 垣田有紀、島田洋一 | |
| 7.剣道打撃動作時の生体電気現象 | 佐々木弘、勝木豊成 | |
| 8.放射線画像情報の抽出と診断支援システム | 小島一彦 | |
| 発行にあたって | 小泉卓也 | |
| 1月号 | 発行にあたって | 中村道治、日向隆 |
| 2−2 酸性雨問題の現状と対策技術 | 指宿堯嗣 | |
| 2−3 特定フロン対策技術における最近の進歩 | 古高靖久 | |
| 1.総論−人類を取巻く地球環境システム− | 市川惇信 | |
| 3.地球環境科学の情報システムとそのネットワーク化 | 杉浦正久 | |
| 4.地球環境保全と近代社会の発展 | 茅陽一 | |
| 2−1 地球温暖化への対策技術 | 石谷久 |
| Vol.74(1991) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 小川吉彦 |
| 1.電波と雪氷の研究事始め | 浅見義弘、松本正 | |
| 2.南極の氷を電波で調べる | 前晋爾、浦塚清峰 | |
| 3.雪の降る街での衛星受信−アンテナへの着雪の測定と対策− | 伊藤精彦、初田健、小川恭孝 | |
| 4.雪雲を電波で調べる | 西辻昭、遠藤辰雄 | |
| 5.積雪内部を電波で映像化する | 青木由直、鈴木勝裕、松本正 | |
| 6.氷の格子欠陥をシンクロトロン放射光で調べる | 本堂武夫、河田洋、東晃 | |
| 7.降雪地帯のソーラセルの性能 | 村上寛之、山崎和弘、柏倉宏聿 |
| Vol.73(1990) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 発行にあたって | 阿部武雄 |
| 和文要約:磁気記録技術の最近の進歩と今後の動向 | 武笠幸一 | |
| 1.RECENT ADVANCES AND FUTURE DEVELOPMENTS IN MAGNETIC RECORDING TECHNOLOGY | Jack H. Judy | |
| 2.磁気記録と材料 | 松本光功 | |
| 3.有限要素法による磁気ヘッドの磁界解析 | 金井靖、飯島泰蔵、武笠幸一、阿部武雄 | |
| 4.トモグラフィ手法による漏れ磁界の3次元計測 | 松田甚一 | |
| 5.微弱磁界計測用SQUID | 浜崎勝義、山下努 | |
| 1月号 | 2.通信網の発展と情報化社会−通信網の将来展望と社会へのインパクト− | 寺田浩詔 |
| 3.ソフトウェアエンジニアリングの展望 | 高村真司 | |
| 4.ヒューマンインタフェースの展望 | 森健一 | |
| 5.材料・デバイス技術の展望 | 田中昭二 | |
| 6.技術パラダイムの変化 | 児玉文雄 | |
| 7.JAPAN,USA,AND TECHNOLOGY IN THE 21st CENTURY | Robert W. Lucky | |
| 発行にあたって | 小柳津育郎 | |
| 1.コンピュータが情報化社会に及ぼすインパクト | 相磯秀夫 |