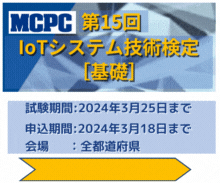ジャンル別 巻頭言
| Vol.107(2024) | ||
|---|---|---|
| 4月号 | 研究に意味的価値を | 水落 隆司 |
| 3月号 | 技術革新を産み出す場としての学会の役割 | 梶川 嘉延 |
| 2月号 | 人と叡智が集まる場 | 伊達木 隆 |
| 1月号 | 価値創造と価値獲得 | 森川 博之 |
| Vol.106(2023) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学び直しの時代における学会の役割 | 太田 賢 |
| 11月号 | オンライン時代の論文媒体の在り方 | 佐波 孝彦 |
| 10月号 | 多様な分野とのコラボレーション | 山本 健太郎 |
| 9月号 | 変化は不可避である | 井上 真杉 |
| 8月号 | 学会運営のインセンティブ | 岡 宗一 |
| 7月号 | 学会が提供する価値,会員が受け取る価値 | 浅井 光太郎 |
| 6月号 | ポストコロナにおける研究会・大会 | 眞田 幸俊 |
| 5月号 | リスクマネジメントとResearch Integrity | 三宅 功 |
| 4月号 | 「会員拡張」のための学会 | 佐藤 真一 |
| 3月号 | つながりつむぐ | 尾上 孝雄 |
| 2月号 | 学会が生き延びるための差別化戦略を考えよう | 陳 強 |
| 1月号 | 論文の多言語化サービス | 川添 雄彦 |
| Vol.105(2022) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 多言語化による新たな開国 | 藤島 実 |
| 11月号 | 今後の大会,研究会の在り方について | 山本 剛之 |
| 10月号 | 研究開発から事業化へ,リーダーへの期待 | 小林 正宏 |
| 9月号 | 学会という集合,要素としての会員 | 髙村 誠之 |
| 8月号 | この一年で気付いたこと | 鎌部 浩 |
| 7月号 | 産業界のイニシアティブで学会を進化させましょう | 西原 基夫 |
| 6月号 | 学会は何のためにあるのか? | 相澤 清晴 |
| 5月号 | 電子情報通信学会の現状と将来 | 西原 明法 |
| 4月号 | コミュニケーションの枠組み | 柏野 邦夫 |
| 3月号 | より大きな見返りを | 髙橋 篤司 |
| 2月号 | 研究者 学会に集い 技術が発展 | 塩本 公平 |
| 1月号 | 若手研究者の評価にインパクトファクタは必要ですか? | 石田 亨 |
| Vol.104(2021) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 雑談のススメ | 安部田 貞行 |
| 11月号 | オンライン化とグローバル化の下での持続可能な編集事業に向けて | 笠原 正治 |
| 10月号 | 情報通信はCOOLである | 神野 正彦 |
| 9月号 | 技術の発展と赤の女王仮説 | 足立 朋子 |
| 8月号 | 研究者同士の議論・連携の活性化に向けて | 寺田 純 |
| 7月号 | 2035年 電子情報通信学会が作るBeyond 5Gの未来 | 山中 直明 |
| 6月号 | 学会サービスを使い倒そう | 植松 友彦 |
| 5月号 | パンデミックのSDGsへの影響と学会の社会的役割 | 鈴木 正敏 |
| 4月号 | 変わっていくもの,残すべきもの | 立元 慎也 |
| 3月号 | 変われない人間,変貌する環境,ICTの役割 | 津田 裕之 |
| 2月号 | コロナの時代だからこそ,新しい出会いの場の創出を | 山田 昭雄 |
| 1月号 | 3度目のニューノーマルに向けて | 笹瀬 巌 |
| Vol.103(2020) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | コロナ禍での日本の研究 | 松井 知子 |
| 11月号 | 様々な困難を乗り越えて | 川端 明生 |
| 10月号 | もっと教育的に条件付き採録を!もっと光が来るように | 菊島 浩二 |
| 9月号 | これからの研究会のスタイルと役割 | 菊間 信良 |
| 8月号 | 新しい日常におけるICTと学会 | 中山 正敏 |
| 7月号 | 明るい将来に向けて | 大橋 弘美 |
| 6月号 | 新型コロナ禍とICT | 松島 裕一 |
| 5月号 | 知のトリックスターを探して | 前田 英作 |
| 4月号 | ICT利用と理科離れ | 眞田 幸俊 |
| 3月号 | ||
| これからの学会が目指すべき会員サービスについて | 坂井 博 | |
| 2月号 | 必要は発明の母 | 柴田 随道 |
| 1月号 | 学会における不易流行 | 中沢 正隆 |
| Vol.102(2019) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | もっと大きなコミュニティへ | 石原 智宏 |
| 11月号 | お札 | 大槻 知明 |
| 10月号 | 北の国から思うこと | 柏 達也 |
| 9月号 | シニア世代への期待 | 藤井 輝也 |
| 8月号 | 新しい運営体制下での基礎・境界ソサイエティの今後 | 田口 亮 |
| 7月号 | イノベーション時代の学会 | 滝田 亘 |
| 6月号 | ICTによる学会活動の推進 | 今井 浩 |
| 5月号 | 判断は我にあり | 土井 美和子 |
| 4月号 | AIの光と影 | 淺谷 耕一 |
| 3月号 | 情報・システムソサイエティの今 | 相澤 清晴 |
| 2月号 | 歳をとったら学会で楽しもう | 河東 晴子 |
| 1月号 | 持続可能な開発のためのアジェンダへ向けた学会の方向性――社会との対話―― | 安藤 真 |
| Vol.101(2018) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 何をしていいのか分からない混乱の時代こそ学問(技術)をやる | 山中 直明 |
| 11月号 | 融合と連鎖 | 糸田 純 |
| 10月号 | 地方創成と人材 | 山本 博章 |
| 9月号 | 幾つかの数字とビジネスモデル | 浅井 光太郎 |
| 8月号 | シンギュラリティの果てに | 堀 修 |
| 7月号 | 電子情報通信学会の国際セクション | 佐古 和恵 |
| 6月号 | ||
| 平成と電子情報通信学会の30年 | 中野 義昭 | |
| 5月号 | 研究教育環境に対する思い | 山本 博資 |
| 4月号 | アウトリーチ活動の強化 | 津田 俊隆 |
| 3月号 | 社会の大きな変革を目の前にして | 植之原 裕行 |
| 2月号 | 創立100周年を顧みて考えたこと | 石川 悦子 |
| 1月号 | 電子情報通信学会次の100年へ | 篠原 弘道 |
| Vol.100(2017) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 輝かせたいコミュニケーションの夢・未来 IEICE100周年 | 笹瀬 巌 |
| 11月号 | 学会における価値観 | 高田 潤一 |
| 10月号 | 出会いは新しい発見の場 | 杉山 一雄 |
| 9月号 | 融合領域の広がる中で | 喜多 泰代 |
| 8月号 | 変化と進化 | 辻 ゆかり |
| 7月号 | 先端技術と説明責任 | 安浦 寛人 |
| 6月号 | インベンションとイノベーション | 森川 博之 |
| 5月号 | 私の研究と学会 | 小川 恭孝 |
| 4月号 | “100年”を考える――次の100年に向けた学会のデザイン―― | 江村 克己 |
| 3月号 | 学会のグローバル化に思うこと | 村田 正幸 |
| 2月号 | ICTは人間を賢くしたか | 永妻 忠夫 |
| 1月号 | 創立100周年の年初にあたり | 佐藤 健一 |
| Vol.99(2016) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 自由自在 | 山尾 泰 |
| 11月号 | 発信と受容――知の相乗効果に向けて―― | 伊東 匡 |
| 10月号 | ICT活用による地方創生 | 伊藤 良生 |
| 9月号 | グローバル化について思う その2:スコープを広げるということ | 本島 邦明 |
| 8月号 | 創立100周年記念事業の準備状況 | 小林 岳彦 |
| 7月号 | 日本の将来にとって不可欠な「英語」のすゝめ | 中沢 正隆 |
| 6月号 | 受け継ぎ,実行し,託す | 大石 進一 |
| 5月号 | 社会の変化に沿った学会 | 鈴木 博 |
| 4月号 | 学会の横の顔東京支部活動について | 相澤 清晴 |
| 3月号 | 国際社会と電子情報通信学会 | 宮永 喜一 |
| 2月号 | まなざしと空気感 | 川村 龍太郎 |
| 1月号 | ICTの未来――超スマート社会に向けて―― | 小柴 正則 |
| Vol.98(2015) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 特別シンポジウムからの熱いメッセージ | 保田 佳之 |
| 11月号 | 論理性を磨くための学会との関わり | 三瓶 政一 |
| 10月号 | イノベーションと学会の役割 | 武田 一哉 |
| 9月号 | 新たな社会価値創造に向けた役割 | 西原 基夫 |
| 8月号 | 次の100年 | 茨木 久 |
| 7月号 | デザイン思考で総合大会を変える | 石田 亨 |
| 6月号 | 個性あふれるグローバルリーダーを育てよう | 笹瀬 巌 |
| 5月号 | グローバル化の中で生き抜いていける学会へ | 桑原 秀夫 |
| 4月号 | グローバル化とアカデミア | 淺谷 耕一 |
| 3月号 | 歴史に学べない時代 | 安浦 寛人 |
| 2月号 | 2050年の社会を支えるICT | 長谷山 美紀 |
| 1月号 | 教育・研究の場としての学会 | 酒井 善則 |
| Vol.97(2014) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 技術の楽しみと責任を伝える学会 | 浅井 光太郎 |
| 11月号 | 未来へ伝えたい学会の宝物 | 宮本 裕 |
| 10月号 | 地域コミュニティをもっと生かそう! | 福田 晃 |
| 9月号 | 56年ぶりの東京オリンピック/パラリンピック開催 | 荒木 純道 |
| 8月号 | 学会は運営するものか,経営するものか | 土井 美和子 |
| 7月号 | 3年前の大震災から学んだこと | 安達 文幸 |
| 6月号 | 研究専門委員会の活力を結集し,課題研究へ | 安藤 真 |
| 5月号 | 感性に磨きをかけた学会へ | 吉野 秀明 |
| 4月号 | 忙中閑話 | 坂庭 好一 |
| 3月号 | 学会の成果 | 榎木 孝知 |
| 2月号 | 人間の認知力とICT | 佐古 和恵 |
| 1月号 | 次の100年に向けて | 井上 友二 |
| Vol.96(2013) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | いよいよ本格化するICTの異分野融合 | 村瀬 淳 |
| 11月号 | 真の電子情報による電子情報通信学会を目指して | 山中 直明 |
| 10月号 | 地域の活性化を図るためにICTをどう活用するか | 玉本 英夫 |
| 9月号 | 異分野交流できる出会いの場を提供 | 守倉 正博 |
| 8月号 | ストーリーとしての研究開発 | 森川 博之 |
| 7月号 | グローバル化と日本社会 | 佐藤 健一 |
| 6月号 | 長寿命社会と学会 | 秋葉 重幸 |
| 5月号 | また,○○したくなるような専門家集団の魅力向上と情報発信力の強化 | 木戸出 正継 |
| 4月号 | 未来予想と情報通信技術者のリーダーシップ | 鈴木 博 |
| 3月号 | グローバル化の課題 | 田中 良明 |
| 2月号 | 国際学会IEICE実現への道しるべ | 佐々木 繁 |
| 1月号 | ICT技術者の存在感向上を目指して | 吉田 進 |
| Vol.95(2012) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | グローバル化について思う | 本島 邦明 |
| 11月号 | 論文誌の未来から見えるもの | 斎藤 洋 |
| 10月号 | ディジタル雑感 | 高橋 明 |
| 9月号 | 財務状況,併せてボランティアについて | 小林 岳彦 |
| 8月号 | 一般社団法人としての再出発 | 西原 明法 |
| 7月号 | 三種の神器 | 間瀬 憲一 |
| 6月号 | 先端的ICTを駆使するプラットホーマ学会を目指す? | 喜連川 優 |
| 5月号 | 新しい未来を開拓しよう | 村上 篤道 |
| 4月号 | 心に刻むこと | 持田 侑宏 |
| 3月号 | 科学技術と幸福 | 貴家 仁志 |
| 2月号 | 人々を引き付ける学会を目指して | 荒川 薫 |
| 1月号 | 和の世紀を築こう | 安田 浩 |
| Vol.94(2011) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 会員増強と学会活動活性化 | 澤田 寛 |
| 11月号 | ICTのICTによる情報発信──編集の立場から── | 今井 浩 |
| 10月号 | 私と電子情報通信学会 | 中野 好典 |
| 9月号 | 持続可能な学会 | 太田 直久 |
| 8月号 | 学会の価値を高めるために | 江村 克己 |
| 7月号 | 見えた課題,明日に向かって | 北山 研一 |
| 6月号 | 役割の変化 | 中嶋 信生 |
| 5月号 | 東北地方太平洋沖地震による甚大な被害を乗り越えて | 羽深 龍二 |
| 4月号 | 国際志向の人材育成 | 三木 哲也 |
| 3月号 | 内向き思考とグローバル化 | 横矢 直和 |
| 2月号 | インターネット時代の電子情報通信学会 | 安達 文幸 |
| 1月号 | 外に飛び出し,世界を広くしよう | 津田 俊隆 |
| Vol.93(2010) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 電子情報通信学会への夢 | 大石 進一 |
| 11月号 | 学会の価値向上に向けて | 三宅 功 |
| 10月号 | 情報通信の移り変わり | 畔上 修一 |
| 9月号 | 変革中の電子情報通信学会 | 桑原 秀夫 |
| 8月号 | 大学生の目の輝き | 中沢 正隆 |
| 7月号 | 「ガラパゴス」への挑戦状 | 小柴 正則 |
| 6月号 | 近代の終わりに電子情報通信技術は… | 原島 博 |
| 5月号 | 「ICT が実現する未来世界」を映す窓 | 正村 達郎 |
| 4月号 | 電子情報通信技術と日本の自然 | 酒井 善則 |
| 3月号 | あってよさそうだけれども「ないもの」──学会を楽しむこと── | 益 一哉 |
| 2月号 | 平城京から思う国際化 | 山田 敬嗣 |
| 1月号 | 電子情報通信技術の発展を二次元から四次元へ | 青山 友紀 |
| Vol.92(2009) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 最近の出来事――マーケットイン発想でのアプローチ―― | 大村 佳久 |
| 11月号 | 電子ジャーナル戦略 | 田中 良明 |
| 10月号 | 情報通信が果たすべき役割 | 戸島 秀喜 |
| 9月号 | インターネットの野望 | 秋葉 重幸 |
| 8月号 | 知の交流の場としての学会 | 村田 正幸 |
| 7月号 | 国際交流に思う | 吉田 進 |
| 6月号 | かせぎとつとめ | 広崎 膨太郎 |
| 5月号 | 外向けの活動を─夢のある未来社会実現に向けて─ | 平田 康夫 |
| 4月号 | 脱欧入亜? | 荒木 純道 |
| 3月号 | 私のどこでもインターネット | 間瀬 憲一 |
| 2月号 | ICTと人間の未来 | 花澤 隆 |
| 1月号 | IT革命と柔らかい専門家──求められる人材── | 宮原 秀夫 |
| Vol.91(2008) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 日本の研究教育環境 | 西原 明法 |
| 11月号 | 会誌の目指すことと時流──望まれる知識── | 山本 浩治 |
| 10月号 | 「人文の知」に学ぶ | 宮澤 正幸 |
| 9月号 | 社会人教育 | 高橋 達郎 |
| 8月号 | 学会の基本サービス | 坂庭 好一 |
| 7月号 | 若者から魅力ある学会へ | 伊藤 弘昌 |
| 6月号 | 元気が出る“場”の創造 | 津田 俊隆 |
| 5月号 | 東京と地方の格差問題を考える | 後藤 敏 |
| 4月号 | アジア太平洋地域のリーダーかつ奉仕者として | 古井 貞煕 |
| 3月号 | ソサイエティの自律が促す学会の発展 | 大石 進一 |
| 2月号 | ダイバーシティ(多様性)を活用する時代 | 喜多 泰代 |
| 1月号 | 学会の機能と役割のパラダイムシフト───学問と技術の年譜─── | 富永 英義 |
| Vol.90(2007) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学会の価値と権威 | 得井慶昌 |
| 11月号 | 性能品質から魅力品質へ | 森川博之 |
| 10月号 | 挑戦者を育てよう | 藤岡清人 |
| 9月号 | 技術+α──これからの学会のあり方について── | 江村克己 |
| 8月号 | 脳を鍛えよう,しなやかな筋肉のように | 萩本和男 |
| 7月号 | 初等中等教育における情報教育に目を向けよう | 雨宮真人 |
| 6月号 | 新たなイノベーションの基礎を──自然事象基盤から人間事象基盤へのパラダイムシフト── | 安田浩 |
| 5月号 | 標準化における競争と協調 | 羽鳥光俊 |
| 4月号 | 電子情報通信学会の理念とは | 中嶋正之 |
| 3月号 | 家庭人は科学者,技術者だ!! | 土井美和子 |
| 2月号 | 発言していける,グローバルな, 競争力のある学会に | 桑原秀夫 |
| 1月号 | 創立90周年を迎えて | 伊澤達夫 |
| Vol.89(2006) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 日本学術会議と電子情報通信学会 | 青山友紀 |
| 11月号 | 次の上昇機運を目指して | 今井和雄 |
| 10月号 | 時定数 | 谷本正幸 |
| 9月号 | 業績の評価について | 赤岩芳彦 |
| 8月号 | もっと人の集まる,オモロイ学会に | 木戸出正継 |
| 7月号 | 技術の品格 | 篠原弘道 |
| 6月号 | 見えない所で,見えるものを支える | 並木淳治 |
| 5月号 | 電子情報通信技術史への誘い | 篠田庄司 |
| 4月号 | 人口の減少と学会活力の維持について | 中野博隆 |
| 3月号 | アナログ・ディジタル考 | 成宮憲一 |
| 2月号 | 新技術と流行語 | 森広芳照 |
| 1月号 | ネットワーク時代の学術情報流通 | 齊藤忠夫 |
| Vol.88(2005) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | “事実”と“真実”の違い | 鈴木滋彦 |
| 11月号 | 若い芽を花開かせよう | 後藤裕一 |
| 10月号 | 夢を創れるか | 長谷川勉 |
| 9月号 | 戦略的な産官学連携型共同研究 | 白川功 |
| 8月号 | 電気系の危機と科学技術立国としての日本 | 中沢正隆 |
| 7月号 | 改革と学会 | 酒井善則 |
| 6月号 | 急がず休まず… | 間瀬憲一 |
| 5月号 | 学会は「経験」,「発見」,「創造」が交わる「市場」に | 弓場英明 |
| 4月号 | 仮想社会10周年 | 青山友紀 |
| 3月号 | 現場が大事 | 赤岩芳彦 |
| 2月号 | 2006年問題 | 小柴正則 |
| 1月号 | 過去と未来をつなぐ現在 | 甘利俊一 |
| Vol.87(2004) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | IT(情報通信技術)と学会 | 阪田史郎 |
| 11月号 | 意思と判断と実行による進化論 | 須藤昭一 |
| 10月号 | 競争と調和 | 根元義章 |
| 9月号 | 子供の理数離れと学会 | 津田俊隆 |
| 8月号 | “はらはら・どきどきの学会へ” | 小林功郎 |
| 7月号 | Back to Science | 池上徹彦 |
| 6月号 | 評価力 | 三木哲也 |
| 5月号 | テクノロジーバリューチェーンをつなごう | 持田侑宏 |
| 4月号 | 国際化・情報化 | 寺田浩詔 |
| 3月号 | 改善と新規立ち上げ | 仙石正和 |
| 2月号 | 多視点知識専門集団と知識増幅型ネットワークの構築 | 木戸出正継 |
| 1月号 | 新たな学術研究の振興 | 伊賀健一 |
| Vol.86(2003) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 論文と特許 | 河内正夫 |
| 11月号 | 学会と“教育” | 吉田進 |
| 10月号 | ITの進歩から生れた新たな課題 | 田中初一 |
| 9月号 | 変化の激しい時代こそ,自分の技術を磨くべき | 山田尚志 |
| 8月号 | 学会の役割と精神 | 中嶋信生 |
| 7月号 | 山車からくりから見えるもの | 稲垣康善 |
| 6月号 | 産・官・学の再生 | 富永英義 |
| 5月号 | グローバルプラットホーム | 木村達也 |
| 4月号 | 国際規格化活動の諸問題 | 高木幹雄 |
| 3月号 | アインシュタインの心 | 小川英光 |
| 2月号 | ソフトウェア技術・システム技術・そして学会 | 雨宮真人 |
| 1月号 | 安定なインターネット接続,安定なパソコン | 羽鳥光俊 |
| Vol.85(2002) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 強さは弱さ,安定は不安定,激動の情報通信事業環境と学会のあり方 | 並木淳治 |
| 11月号 | より安全なシステムの構築を目指して | 岡本龍明 |
| 10月号 | 理科離れと学力低下に思う | 竹内賢一 |
| 9月号 | だれがための学会,これからの学会とは | 安田浩 |
| 8月号 | 世代の更新なのか,パラダイムのシフトなのか | 青山友紀 |
| 7月号 | 企業の技術管理職のみなさんへ | 小山正樹 |
| 6月号 | グローバル化の中の学会 | 斉藤忠夫 |
| 5月号 | 日本のITは遅れているのか | 石川宏 |
| 4月号 | 文理融合か文理連続か−定理と証明− | 辻井重男 |
| 3月号 | グローカルな学会活動を目指して | 伊藤弘昌 |
| 2月号 | 技術予測 | 村上仁己 |
| 1月号 | 「骨太研究」とその他 | 内藤喜之 |
| Vol.84(2001) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 『感覚』について | 石原直 |
| 11月号 | “評価”,“ランキング”ばやり | 宮原秀夫 |
| 10月号 | 地域での次世代インターネットの取組み | 中野慎夫 |
| 9月号 | これからの学会 | 村岡洋一 |
| 8月号 | 改革と変化−いま学会に求められるもの− | 後藤裕一 |
| 7月号 | 仕事は忙しい人に頼めと言うけれど | 池田克夫 |
| 6月号 | 学会の新しい流れ | 石黒辰雄 |
| 5月号 | 情報交流の場 | 三木哲也 |
| 4月号 | ブロードバンド時代と学会 | 酒井善則 |
| 3月号 | 2010年,ある学会役員の思い | 青山友紀 |
| 2月号 | 関連学会の連合・統合の夢 | 中村僖良 |
| 1月号 | 「学会」の変革−IT革命の中で− | 青木利晴 |
| Vol.83(2000) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学会と顧客志向 | 小林功郎 |
| 11月号 | 非常識の常識化 | 佐野浩一 |
| 10月号 | 客員会員制による学会活性化 | 酒井保良 |
| 9月号 | 北海道経済と学会 | 白髭博司 |
| 8月号 | 会員として・役員として | 倉本実 |
| 7月号 | 若者の学力不足について | 森永規彦 |
| 6月号 | 変化への対応・学会の対応 | 下村尚久 |
| 5月号 | ネットワーク時代と学会 | 塚田啓一 |
| 4月号 | 規格調査会の活動について | 高木幹雄 |
| 3月号 | 首都機能移転問題と学会活動 | 井口征士 |
| 2月号 | ゆとりの功罪 | 小柴正則 |
| 1月号 | 年頭に想う | 安田靖彦 |
| Vol.82(1999) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 次の世代へ継ぐ | 津田俊隆 |
| 11月号 | 学会活動を更に活気あふれた自由なものに | 西谷隆夫 |
| 10月号 | 先端技術と基礎研究 | 酒井善則 |
| 9月号 | グローバリゼーション | 仙石正和 |
| 8月号 | フェアネスとは | 鈴木滋彦 |
| 7月号 | 専門教育と予備教育 | 板倉文忠 |
| 6月号 | 研究開発における産業界の役割 | 佐々木元 |
| 5月号 | 「研究者市場」の形成を | 池上徹彦 |
| 4月号 | 世界に向けて英文論文別刷を送ろう | 辻井重男 |
| 3月号 | 学会のパーソナル化 | 森永規彦 |
| 2月号 | ボランティアとしての学会活動 | 今井秀樹 |
| 1月号 | 夢を抱いて進もう | 長尾真 |
| Vol.81(1998) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学会のグローバル化,国際化を考える | 後藤敏 |
| 11月号 | 21世紀に向けた期待 | 佐藤健一 |
| 10月号 | 出会いの場としての学会 | 持田侑宏 |
| 9月号 | マルチメディア時代に向けて | 福井敏明 |
| 8月号 | ボランティア活動 | 木村達也 |
| 7月号 | 若手会員へのエール | 池田博昌 |
| 6月号 | 近ごろ思い出したこと | 安田靖彦 |
| 5月号 | ネットワーク社会における学会 | 今井秀樹 |
| 4月号 | 日本の科学技術政策はこれで良いのか | 富永英義 |
| 3月号 | 論文の著作権使用料金とは | 村岡洋一 |
| 2月号 | 産・学・学会 | 神谷武志 |
| 1月号 | 本学会における電子化の推進 | 金子尚志 |
| Vol.80(1997) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 「労働」から「脳働」へ | 岡村敏光 |
| 11月号 | 設計能力拡充に向けての産学共同 | 白川功 |
| 10月号 | 学会の寿命 | 伊土誠一 |
| 9月号 | 若い人達に夢を | 小川明 |
| 8月号 | マルチメディア時代の論文誌 | 加藤邦紘 |
| 7月号 | アグレッシブさとクールさ | 川上彰二郎 |
| 6月号 | 新しい時代のための新しい研究を | 青木利晴 |
| 5月号 | バランスシート | 伊沢達夫 |
| 4月号 | 個の独創と群の創造 | 植之原道行 |
| 3月号 | ソサイエティ制のテークオフ | 三木哲也 |
| 2月号 | 美しき“ことば”よ.時空を越えて,人間(じんかん)に,飛翔せよ. | 笠原正雄 |
| 1月号 | 新世界における社会的存在 | 辻井重男 |
| Vol.79(1996) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学会と私 | 前田稔 |
| 11月号 | 将来はサイバー学会? | 太田直久 |
| 10月号 | 偶然と必然 | 吹抜洋司 |
| 9月号 | 「電気通信学会」入会から30年 | 迫江博昭 |
| 8月号 | ネットワーク時代の学会 | 石黒辰雄 |
| 7月号 | 理詰めの研究と夢の研究 | 佐々木昭夫 |
| 6月号 | 研究体制の新しい息吹き | 甘利俊一 |
| 5月号 | 法人と課税 | 高梨裕文 |
| 4月号 | ソサイエティを自分達の手で | 小川英光 |
| 3月号 | 学会と国際標準化活動 | 高木幹雄 |
| 2月号 | 20年前と違うところ | 伊藤隆司 |
| 1月号 | 電気通信基盤は「人工土地」のようなもの | 堀内和夫 |
| Vol.78(1995) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | マルチメディアにエールを | 愛沢慎一 |
| 11月号 | 学会によるさまざまな“場”の提供へ | 小林功郎 |
| 10月号 | “さあ,分散処理システムに電源は入ったぞ!” | 青山友紀 |
| 9月号 | 大学院後期課程進学希望者の伸び悩みを憂う | 米山務 |
| 8月号 | 学会の活動 | 下村尚久 |
| 7月号 | 学会活動電子化の意義 | 寺田浩詔 |
| 6月号 | 学会と賞 | 後藤尚久 |
| 5月号 | 半導体分野における産学関係 | 佐々木元 |
| 4月号 | 本学会のこれから | 伊賀健一 |
| 3月号 | より良き会員サービスを求めて | 植之原道行 |
| 2月号 | 情報の供給と消費のアンバランスを解消したときこそ,真のマルチメディア時代 | 小川圭祐 |
| 1月号 | マルチメディア時代に向けての学会活動 | 宮津純一郎 |
| Vol.77(1994) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 迅速な技術情報の公表とソサイエティ制の役割 | 板倉文忠 |
| 11月号 | 日本的ソサイエティの実現に向けて | 加藤修三 |
| 10月号 | 製造業離れ理工系離れに思う | 塚田啓一 |
| 9月号 | 夢・うつつ | 石井康一 |
| 8月号 | ソサイエティ制雑感 | 池上徹彦 |
| 7月号 | 情報社会の生態学 | 長尾真 |
| 6月号 | アメリカの半導体復活 | 黒川兼行 |
| 5月号 | マルチメディア時代がやってきた | 青木利晴 |
| 4月号 | 新しい時代には新しい論文誌を | 浦野義頼 |
| 3月号 | 共存と協調の時代に思うこと | 古賀利郎 |
| 2月号 | 倫理と学会 | 今井秀樹 |
| 1月号 | エレクトロニクス技術者の栄光と責任 | 大越孝敬 |
| Vol.76(1993) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 学会e-mailシステムに期待する | 石川宏 |
| 11月号 | 研究開発に想う | 渡辺貞一 |
| 10月号 | 改革のとき | 小山正樹 |
| 9月号 | 期待される四国の開発 | 為貞建臣 |
| 8月号 | 変化の節−学会の機能と役割− | 富永英義 |
| 7月号 | 何を研究すべきか | 安達三郎 |
| 6月号 | 機は熟すソサエティ制 | 辻井重男 |
| 5月号 | 学会活動の国際競争力と英文論文誌の役割 | 岩垂好裕 |
| 4月号 | OA化は一石二鳥 | 村野和雄 |
| 3月号 | 次世代を担う学生の方々へ | 宮津純一郎 |
| 2月号 | 学会の国際化について | 大附辰夫 |
| 1月号 | 新しい開拓の芽に寛容に | 末松安晴 |
| Vol.75(1992) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 雑感 | 加藤孝雄 |
| 11月号 | ユーザの立場に立つ | 山口治男 |
| 10月号 | 活力を生かす仕組みを | 石黒辰雄 |
| 9月号 | 地域情報の発信 | 内山登 |
| 8月号 | “文明”を維持発展させるために | 吹抜敬彦 |
| 7月号 | 視点の転換−二人称のすすめ− | 葉原耕平 |
| 6月号 | 大学雑感−学問の発展と大学教育− | 堀内和夫 |
| 5月号 | 国際化に向けて | 池田博昌 |
| 4月号 | 環境関連研究への参加 | 中村道治 |
| 3月号 | サービスと感性 | 榎本肇 |
| 2月号 | 再び,学会と工学教育について | 柳井久義 |
| 1月号 | 国際化 | 岩崎昇三 |
| Vol.76(1991) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 技術力 | 柳川隆之 |
| 11月号 | 若者の理工系離れについて | 田崎公郎 |
| 10月号 | 原点 | 原島博 |
| 9月号 | 人間に優しく暖かい技術を | 高梨裕文 |
| 8月号 | 流行と創造性 | 甘利俊一 |
| 7月号 | 21世紀に引継がれる課題を問う | 稲場文男 |
| 6月号 | 次世紀に向けた社会基盤 | 末松安晴 |
| 5月号 | 創造性と文化 | 黒川兼行 |
| 4月号 | 一方通行でない国際化を | 後藤敏 |
| 3月号 | InteractionからInterfaceへ | 榎本肇 |
| 2月号 | 学会の将来の発展に向けて | 柳井久義 |
| 1月号 | 英文論文誌の改革について | 関口利男 |
| Vol.75(1990) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 情報革新と高齢化社会 | 堀口孝雄 |
| 11月号 | 全国大会 | 下村尚久 |
| 10月号 | “電”の字の行方 | 青山知紀 |
| 9月号 | 学会の財政について | 西川清史 |
| 8月号 | 日本の国際化と学会活動 | 佐々木元 |
| 7月号 | 学際交流と学会の役割について | 古賀利郎 |
| 6月号 | 光ファイバ網構築を機会に都市の美化を−ふたたび電線地中化問題について− | 大越孝敬 |
| 5月号 | 技術者養成雑感 | 柳沢健 |
| 4月号 | 日本の大学の終焉 | 村岡洋一 |
| 3月号 | 電子,情報,通信の統合による新文明基盤へ向けて | 榎本肇 |
| 2月号 | 日本人と日本語 | 柳井久義 |
| 1月号 | 独創性を育てる環境づくり | 関口利男 |