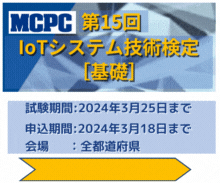ジャンル別 回想
| Vol.105(2022) | ||
|---|---|---|
| 4月号 | 無線ディジタル化れい明期でのPLLの研究 | 小久保 優 |
| 1月号 | ディジタル映像伝送の開拓と国際標準化の始まり | 山本 英雄 |
| Vol.101(2018) | ||
|---|---|---|
| 3月号 | 昇圧回路の研究を通じて学んだこと | 丹沢 徹 |
| Vol.99(2016) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | アドホックネットワーク・無線メッシュネットワークの社会応用を目指して | 間瀬 憲一 |
| 4月号 | ユビキタス技術の社会応用を目指して | 佐藤 良明 |
| Vol.98(2015) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 教育工学50年の歩み | 清水 康敬 |
| Vol.97(2014) | ||
|---|---|---|
| 4月号 | 印鑑と電子印鑑の歴史と比較分析 | 佐々木 良一 |
| Vol.96(2013) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 車載用ステレオカメラ誕生物語 | 実吉 敬二 |
| Vol.95(2012) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | モールス通信のお話 | 有澤 豊志 |
| Vol.93(2010) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | ポストシリコンデバイスはどうなったか──GaAs FET,LSI の発展の経過── | 上西 勝三 |
| Vol.92(2009) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 依佐美送信所の歴史とマイルストーン | 田中 浩太郎、石田 正治、松本 栄寿 |
| 6月号 | 電子交換国際会議(ISS)の舞台裏──Mr. Switching:Amos E. Joel, Jr. 氏の功績を偲ぶ── | 葉原 耕平 |
| Vol.91(2008) | ||
|---|---|---|
| 6月号 | 電子情報通信技術とスイッチング電源 | 原田 耕介 |
| Vol.89(2006) | ||
|---|---|---|
| 4月号 | マイクロ波工学のパイオニア森田清先生を偲んで(【追悼抄】に換えて) | 末武国弘 |
| 2月号 | コンピュータビジョンの誕生と成長 | 白井良明 |
| 1月号 | 局用ディジタル交換の開発を顧みて−研究から半世紀,導入から四半世紀− | 池田博昌 |
| Vol.87(2004) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 四半世紀を経た光通信システムの技術開発−歴史に学ぶ− | 島田禎晉 |
| 4月号 | 企業における研究開発の事例−音声認識の商品化− | 平岡省二、二矢田勝行 |
| Vol.86(2003) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 日本語ワープロが果たした社会的役割 | 森健一、河田勉、天野真家 |
| 6月号 | ディジタル移動通信技術の歴史 | 赤岩芳彦 |
| 4月号 | 我が国における初期のコンピュータ開発 | 山田昭彦 |
| Vol.85(2002) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 移動体通信を支える水晶技術−古賀カットから現代まで− | 平間宏一 |
| 6月号 | 化合物半導体のほそ道 | 福田益美 |
| 3月号 | ある米国Start-upのてんまつ記 | 宮下忠 |
| Vol.84(2001) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | CCD撮像素子の歴史と将来展望 | 越智成之 |
| 7月号 | 面発光レーザ−その誕生と発展− | 伊賀健一 |
| Vol.83(2000) | ||
|---|---|---|
| 5月号 | 我が国人工衛星開発の思い出 | 斎藤成文 |
| 量子回路理論への道−回路理論・ディジタル信号処理論から得る量子力学− | 永田信夫 | |
| 3月号 | ブラインド等化発想秘話 | 佐藤洋一 |
| Vol.82(1999) | ||
|---|---|---|
| 9月号 | 電波吸収体研究のいまむかし | 内藤喜之 |
| 8月号 | ガン効果ダイオードから自己形成量子ドットへ | 佐々木昭夫 |
| 3月号 | 音声研究−雑音との戦いを振り返って− | 鈴木誠史 |
| 1月号 | ミリ波研究私史 | 米山務 |
| Vol.81(1998) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 夢中の40年 | 甘利俊一 |
| 5月号 | 今,移動通信を振り返る | 松坂泰 |
| Vol.80(1997) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | 環境電磁工学誕生 | 佐藤利三郎 |
| 弾性波素子の研究回顧−弾性表面波素子をめぐって− | 柴山乾夫 | |
| 5月号 | コンピュータ開発 | 矢島脩三 |
| Vol.79(1996) | ||
|---|---|---|
| 10月号 | フォールトトレラントコンピューティングと私 | 当麻喜弘 |
| 8月号 | 電波の研究と私 | 小口知宏 |
| 5月号 | メカニカルフィルタから振動ジャイロスコープまで | 近野正 |
| 3月号 | 第五世代コンピュータ研究 | 渕一博 |
| 営為としての研究について | 嵩忠雄 |
| Vol.78(1995) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 画像処理の夜明け | 尾上守夫 |
| 10月号 | 光エレクトロニクスの30年を振り返って | 霜田光一、稲場文男、末松安晴 |
| 電話機設計の思想の流れ | 大賀寿郎 | |
| 8月号 | ディジタルシステムの自動設計30年の歩み | 山田昭彦 |
| 7月号 | 高次コミュニケーション | 野口正一 |
| 5月号 | 日本語ワードプロセッサ開発の回想 | 森健一 |
| 1月号 | MCAシステムの設計はどのように進められたか | 鈴木行三 |
| Vol.77(1994) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | オンラインシステムの誕生 | 穂坂衛 |
| 8月号 | 一音響技術者の回想 | 城戸健一 |
| 5月号 | カオス発見のころ | 上田皖亮 |
| Vol.76(1993) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 正規表現と有限オートマトン | 山田尚勇 |
| 9月号 | 創造的研究はいかになされるか−独創を育てる環境・阻む環境− | 高木俊宜 |
| 8月号 | 実用化研究30年の回想 | 中込雪男 |
| 3月号 | HEMTの開発経緯 | 三村高志 |
| Vol.75(1992) | ||
|---|---|---|
| 8月号 | 昭和20年代の我が国のマイクロ波通信の研究実用化 | 小口文一 |
| 5月号 | なぜ私はこの道を選んだか | 植之原道行 |
| 3月号 | 周波数標準小史のエピソード | 大浦宣徳 |
| Vol.74(1991) | ||
|---|---|---|
| 12月号 | 私の歩いた道−計算機と共に− | 萩原宏 |
| Vol.73(1990) | ||
|---|---|---|
| 7月号 | 半導体工学のあゆみ−独創的発想の成果− | 西沢潤一 |