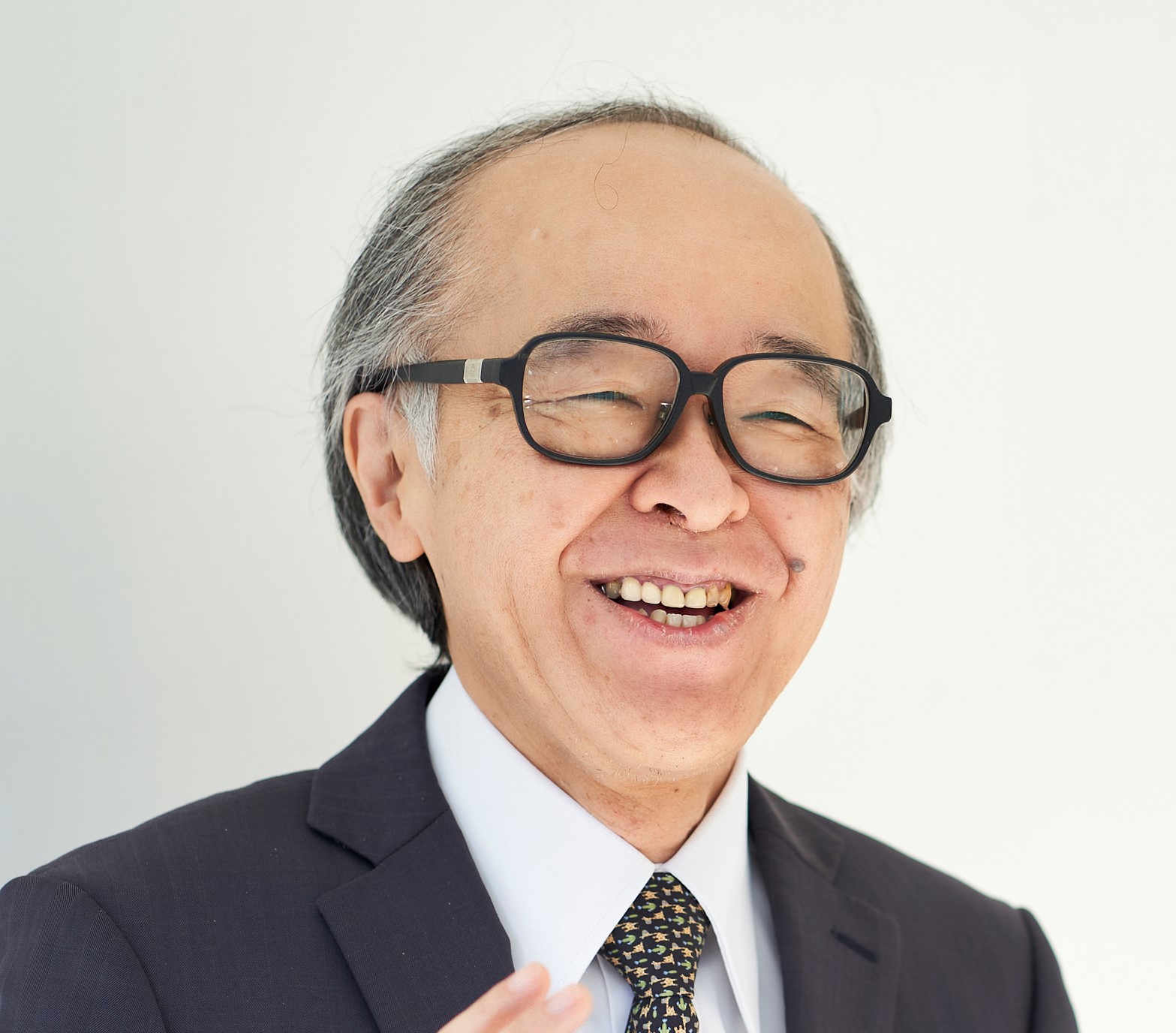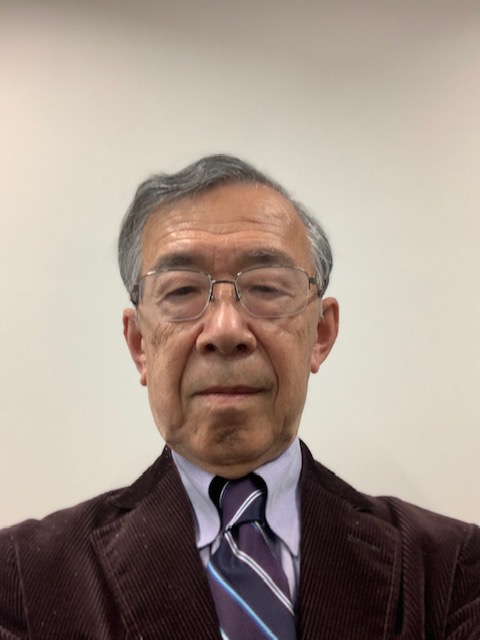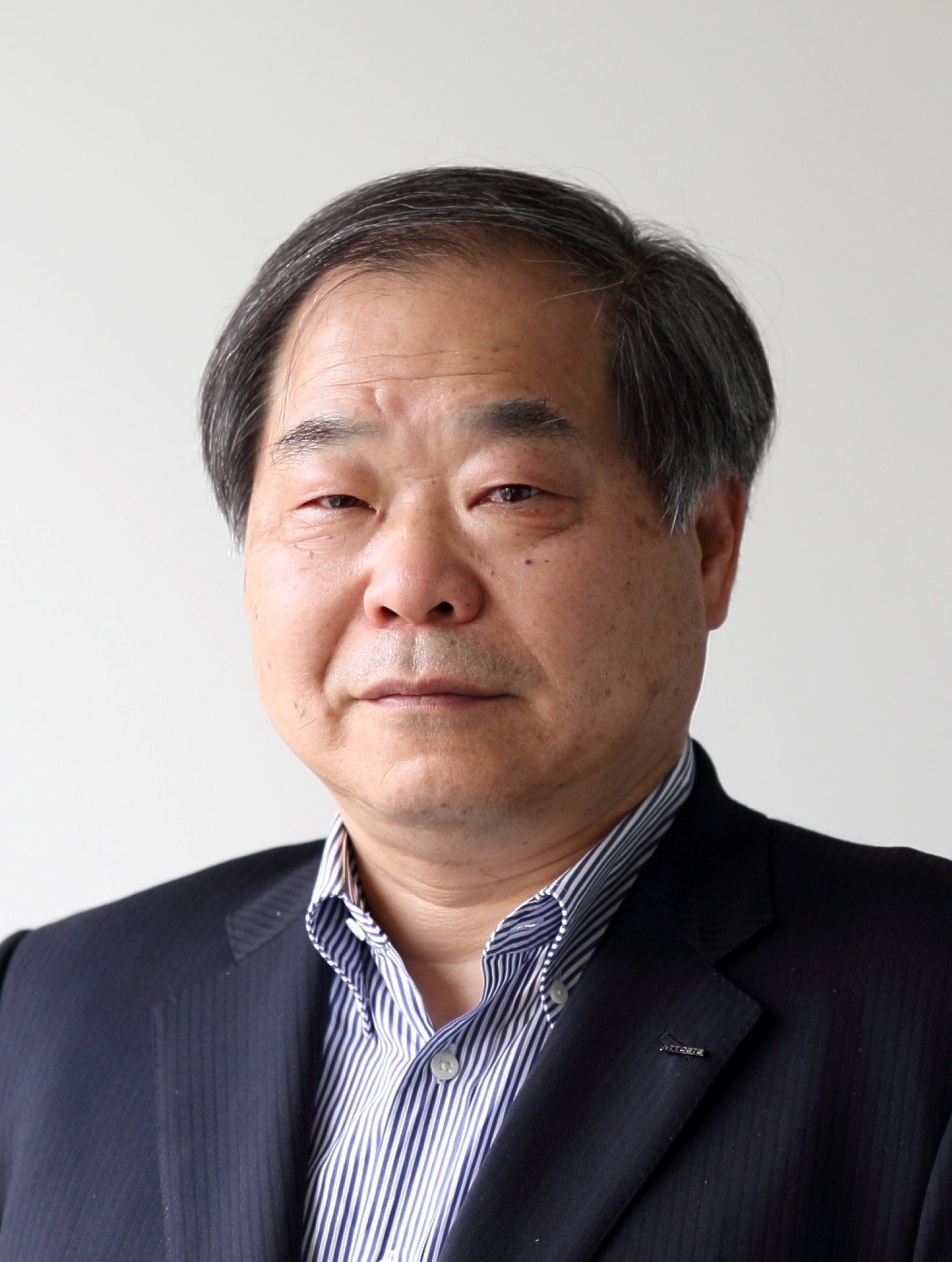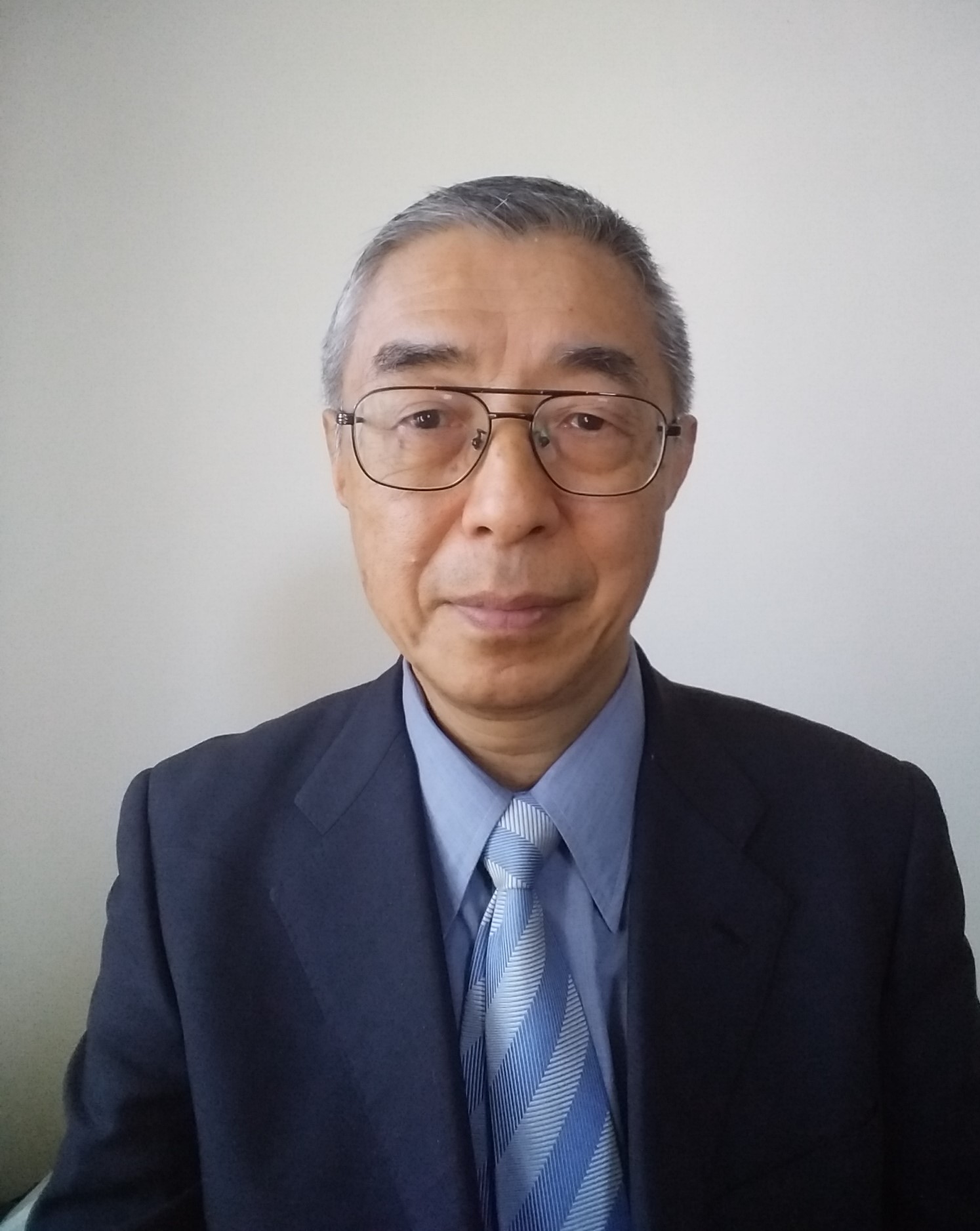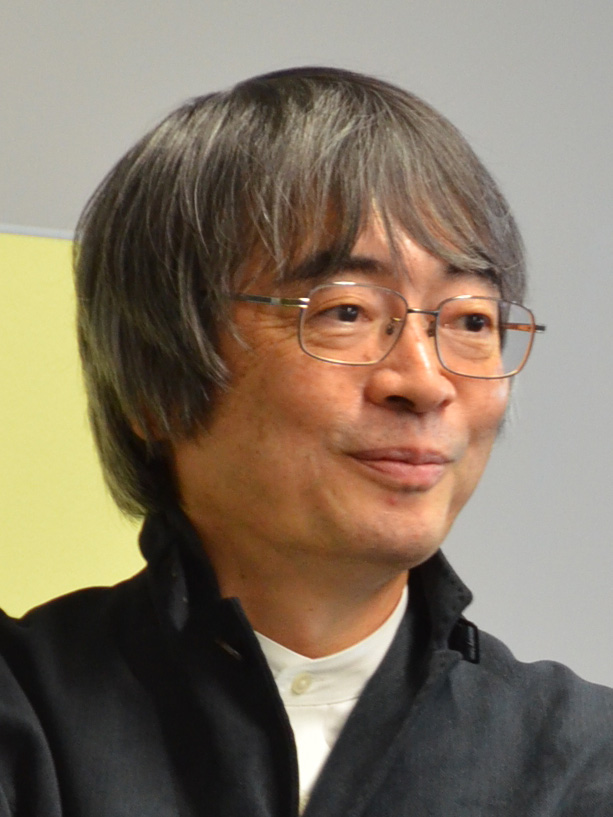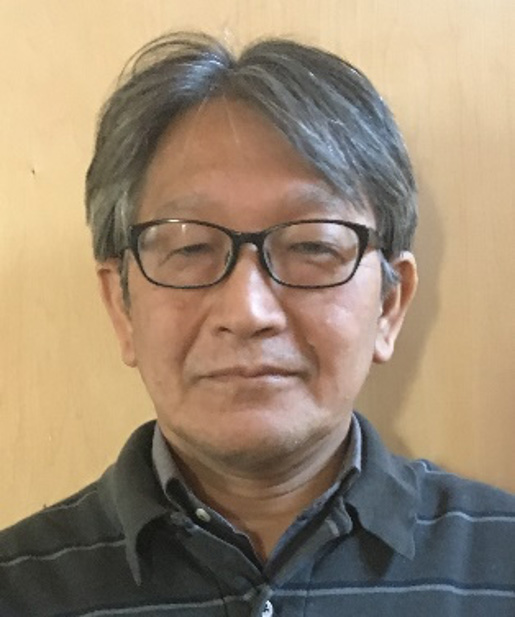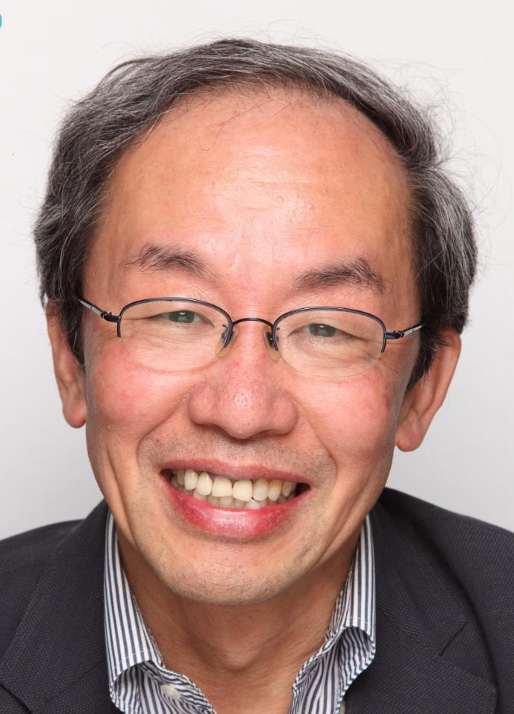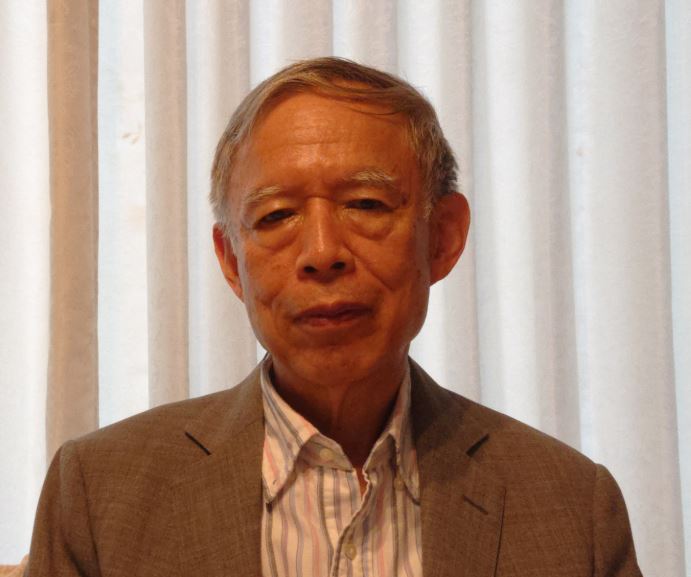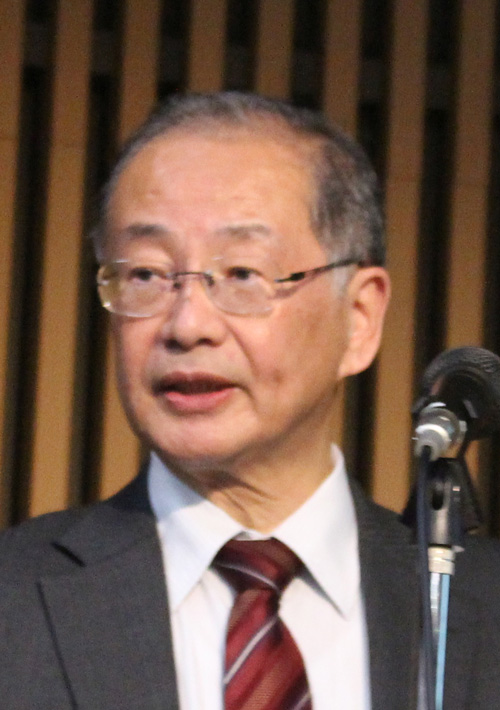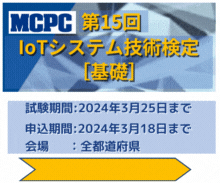No
開催月
講演内容
講演者(所属)
1
2022年1月
脳に学ぶ視覚情報処理
【講演内容】
福島 邦彦(ファジィシステム研究所 特別研究員)
2
2022年2月
ポストコロナとVR
【講演内容】
廣瀬 通孝(東京大学名誉教授)
3
2022年3月
長距離光海底ケーブル通信システムの研究開発:背景、経緯、現状、将来に向けて
【講演内容】
秋葉 重幸(元株式会社KDDI研究所 代表取締役所長)
4
2022年4月
移動通信とともに歩んだ研究生活を振り返りつつICTのこれからを考える
【講演内容】
吉田 進(京都大学名誉教授)
5
2022年5月
企業での研究開発を経験して―ディジタル信号処理からネットワークビジョンまで―
【講演内容】
津田 俊隆(早稲田大学GITI・顧問)
6
2022年6月
集積回路開発40年の歩み―ADC、アナ・デジ混載SoC、ミリ波CMOS技術を中心として―
【講演内容】
松澤 昭(株式会社テックイデア 代表取締役)
7
2022年7月
Beyond 5Gへの挑戦~分散OSの黎明期からSociety5.0を俯瞰して
【講演内容】
徳田 英幸(国立研究開発法人 情報通信研究機構 理事長)
8
2022年8月
デジタル時代のサイバーセキュリティ
【講演内容】
三宅 功(NTTデータ先端技術株式会社 フェロー)
9
2022年9月
音声通信の歴史と未来―音声音響符号化技術の視点から―
【講演内容】
守谷 健弘(NTTコミュニケーション科学基礎研究所 NTTフェロー)
10
2022年10月
浮草研究者と人工知能研究
【講演内容】
池内 克史(米国マイクロソフト)
11
2022年11月
複雑系数理モデル学とICT
【講演内容】
合原 一幸(東京大学特別教授)
12
2022年12月
心を持った機械
【講演内容】
橋本 周司(早稲田大学名誉教授)
No
開催月
講演内容
講演者(所属)
1
2021年1月
スーパーコンピュータ「富岳」の開発とコデザイン
【講演内容】
佐藤 三久(理化学研究所計算科学研究センター・副センター長)
2
2021年2月
情報の時代を勝手に俯瞰する
【講演内容】
原島 博(東京大学名誉教授)
3
2021年3月
社会情報基盤を構築するための工学とは?
【講演内容】
安浦 寛人(九州大学 名誉教授)
4
2021年4月
電波科学の100年と持続可能な発展への取り組みの道すがら、想うこと
【講演内容】
安藤 真(東京工業大学 名誉教授)
5
2021年5月
本当の感覚通信を求めて ーリアルハプティックスの歴史と未来ー
【講演内容】
大西 公平(慶應義塾大学 ハプティックス研究センター 特任教授)
6
2021年6月
データの時代:定年まで続けたデータベース工学研究の振り返りとコロナ時代におけるノーノーマルの考察
【講演内容】
喜連川 優(東京大学 特別教授)
7
2021年7月
移動無線通信技術の発展と将来展望,そして研究開発の醍醐味
【講演内容】
安達 文幸(東北大学 名誉教授)
8
2021年8月
"情報ネットワークの周辺で画像と共に半世紀"ーファクシミリ通信から通信政策まで、実践から研究へー
【講演内容】
酒井 善則(東京工業大学 名誉教授)
9
2021年9月
"フェイクとの闘いー暗号学者の視た理念と現実・太平洋戦争からコロナまでー
【講演内容】
【主な項目】
①小学校高学年の戦争体験と皇道理念
辻井 重男(中央大学研究開発機構 フェロー・機構教授)
10
2021年10月
デジタル社会の創生
村井 純(慶應大学教授・内閣官房参与(デジタル政策分野担当)
11
2021年10月
"光ファイバ通信の200THzポテンシャルの開拓:研究から社会インフラへ昇華の過程に支えられて
【講演内容】
萩本 和男(NTTエレクトロニクス株式会社)
12
2021年10月
AI時代にリーダーシップをとるために
【講演内容】
古井 貞煕(国立情報学研究所研究総主幹・東京工業大学栄誉教授)
13
2021年11月
面発光レーザーの創案と応用分野の広がり
【講演内容】
伊賀 健一(東京工業大学・名誉教授/元学長、本会元会長)
14
2021年12月
AIの時代に玄人をめざす人へのメッセージ
【講演内容】
金出 武雄(カーネギーメロン大学 ワイタカー記念全学教授)