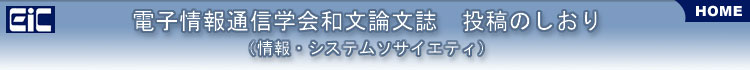
基本的に,次の4条件について査読を行う.
| (1) | 新規性:投稿の内容に著者の新規性があること. |
| (2) | 有効性:投稿の内容が学術や産業の発展に役立つものであること. |
| (3) | 信頼性:投稿の内容が読者から見て信用できるものであること. |
| (4) | 了解性:投稿の内容が明確に記述されていて読者が誤解なく理解できるものであること. |
信頼性については必須の要件であるが,新規性と有効性についてはいずれかが高ければ採録の対象となる.すなわち,新規性が高い場合は,有効性はさほど高くなくても採録の対象となり,有効性が高い場合は,新規性がさほど高くなくても採録の対象となる.
新規性,有効性の評価では,できるだけ視点を広げて論文の良い点をみつけるようにする.このような観点で評価するときの参考として,新規性,有効性,信頼性に関するチェック項目を設定した.もちろん,これらのチェック項目をひとつでも満たす論文は採録可能であるというわけではない.論文の信頼性を確認したり,新規性,有効性に関する客観的な主張を明確にしたりする際に,参考にして頂きたい.
■ 新規性
様々な観点から論文を吟味して,できるだけ幅広く新規性を見出すように心がける.たとえば,次のような要件を満たす場合には,論文の新規性があると評価する.新規性のレベルの判定は,従来の論文(信学論の平均的な掲載論文)を基準にする.いずれかの要件において,従来の論文に比べて,大きな差異が認められる場合には新規性が極めて優れていると評価する.
また,複数の要件において差異が認められる場合には,新規性を総合的に判断して評価を高くする.
新しい概念が提案されている.
新しいアルゴリズムが提案されている.
新しい実現方式が提案されている.
概念や方式の新しい組み合わせ方が提案されている.
理論上の新しい結果が述べられている.
新しいデータが (それを得るに至った方法に関する議論とともに)提示されている.
新しい解釈が提示されている.
新しい事例が提示されている.
新しい問題領域が提示されている.
要素技術の新しい利用方法が(従来のものとの独立性を明確にした上で)提示されている.
実践的システムへの最新技術の新しい適用例が提示されている システム開発経験に関する新しい知見が述べられている.(注1) システム開発論文における「新しさ」の主張方法について
・論文で述べたシステムと同じ範疇に属する製品が存在する場合,カタログやパンフレット,マニュアル等を用いて比較する必要はなく,その旨を論文で述べ,何が違うのかを明確にしておけばよい.
・論文で述べた技術を使用して構築されたことが明白なシステムが存在する場合にも,その旨を論文で述べ,何が違うのかを明確にする.(注2) 国際会議等に発表した論文を拡張して投稿する場合の注意
投稿論文・レターは,その内容の一部あるいは全部が公知・既発表である場合には,その部分における新規性の評価は0となる.ただし,内容が公知・既発表であっても、その対象となる既発表の文献が以下に記す要件のすべてを満たす場合は、公知・既発表である部分についても新規性評価の対象とする。(1) 該当文献が1.2.2 著作権の遵守に抵触していない
(2) 該当文献が以下のいずれかであること
a) 特許公開/公告公報等
b) 大学の学士論文・修士論文・博士論文・テクニカルレポート等
c) 本会や他学会の大会・研究会・国際会議等の予稿集・プロシーディング等
d) 企業の技報等
e) 書籍,新聞記事等
f) 公共性の高いプレプリントサーバ,著者個人のホームページ等
■ 有効性
様々な観点から論文を吟味して,できるだけ幅広く有効性を見出すように心がける.たとえば,次のような要件を満たす場合には,論文の有効性があると評価する.有効性のレベルの判定は,従来の論文(信学論の平均的な掲載論文)を基準にする.いずれかの要件において,従来の論文に比べて,大きな差異が認められる場合には有効性が極めて優れていると評価する.
また,複数の要件において差異が認められる場合には,有効性を総合的に判断して評価を高くする.
得られた効果が大きい.
得られた結果を適用できる領域が広い.
得られた結果を適用したい人が多い.
得られた結果を適用した場合に得られる利益が大きい.
得られた結果により大きな利益が得られたことが,客観的に示されている.
得られた結果に対する分析が十分になされている.
十分広い範囲に渡って問題が考慮されている.
現実世界との対応付けが十分に考慮されている.
新しい研究につながる可能性が高い.
他の研究へ大きな刺激を与える可能性が高い.
新しい研究分野を開く可能性が高い.
実務データを用いていなくとも,新規性を主張した部分に適した例題を挙げ,その実行例を基に成果が論理的に示されている.実践的システムへ最新技術を適用した場合に,当該技術を適用したことにより得られた利益が大きかったことが客観的に示されている.
(注) システム開発論文でも,学術論文としてふさわしい客観的な主張が含まれていなければ,有効性が高いと判断しない.
■ 信頼性
次のような条件をすべて満たすとき,信頼性があると判定する.
十分具体的に記述されている.
技術的な裏付けが示されている.
議論の展開に誤りがない.
前提条件が明確である.
特に,システム開発論文では,システム構築の際になされた幾つかの意思決定のうち,特に重要な部分を採り上げ,そこで下された意思決定が正しく,かつ,その根拠が説得力のある形で記述されていることが論文の信頼性につながる.
(注) システム開発論文では,システム構築において方式選択したときに,その方式を選択したこと自身が論文の主題でないならば,選択理由を詳細に述べなくてもよい.
■ 了解性
論旨の展開が,読者に十分理解できるように,分かりやすく,順序立てて,明瞭に記述してあること.
論文,サーベイ論文は複数の査読者,レターは原則1人の査読者の報告をもとに,編集委員会において,次のいずれかに判定する.
| ア) | 採録:5.1の条件を総合的に判断し,会員にとって有益であると認めた場合には採録とする. |
| イ) | 条件付採録:このままでは採録の条件を満たさないが,少しの修正により採録の条件に達すると見込める場合は条件付採録とする.条件付採録の処置は原則として1回とし,5.3で定める修正原稿が採録の条件を満たしていないときは不採録とする. |
| ウ) | 不採録:5.1の条件を満足せず,かつ短期間では改善されないと判断されたもの,及び,内容的に大幅な修正を要するものは不採録とする.なお,極めて読みにくいもの,及び,分野が不適切なものは不採録になることがある. |
条件付採録と判定された場合は,著者には条件付採録通知とともに編集委員会からの「採録の条件文」が送付される.著者は,当該条件を満足するように原稿を修正するとともに,「条件付採録に対する回答文」を作成し,条件付採録判定通知の日付から60日以内に事務局まで提出するものとする.これを修正原稿と呼ぶ.理由なくして60日を経過した原稿は取り下げとみなし,その後提出された原稿は新規投稿扱いとする.なお,特集号の場合には,修正期間は60日よりも短縮されることがある.
なお,修正原稿提出の際に論文題名を変更する場合には,条件付採録に対する回答文中にその旨を必ず明記する.その際には,Copyright Transfer and Article Processing Charge Agreementを再作成し,事務局まで送付すること.送付方法は,スキャンしPDF化したものをメールの添付にて送付,ファックスによる送信,郵送による方法のいずれの手段でも構わない.
また,初回投稿時からページ数が大幅に増加する場合,及び刷り上がりが15ページ以上となる場合は,ページ数の超過を理由に不採録とする場合があるので簡潔な記述に努めること.
5.3.1修正原稿提出方法
条件付採録通知に明記されたURLにアクセスし,次のファイルをアップロードする必要がある. ファイルをアップロード後,5日以上経過しても「回答文受領書」が届かない場合には,事務局へ問い合わせること.
(1) 採録の条件に対する回答文及び条件付採録通知(採録の条件文を含む):(単一ファイル※1)
(2) 修正原稿PDFファイル(修正箇所をマーキングしたもの)
(3) 編集用電子ファイル※2
※1 単一ファイルにするには Adobe Acrobatの機能をご利用下さい.
参考:http://www.adobe.com/jp/
※2 編集用電子ファイルには,以下の(a)〜(c)を収める.(a)〜(c)は,できれば1つのフォルダに保存して圧縮したものが望ましい(1ファイルにつき10MBまで).
| (a) | 修正原稿PDFファイル(修正箇所にマーキングしていないもの) |
| (b) | 修正原稿や図表等を作成したすべての電子データ(LaTeX,Word,Excel,Power Point,Epsファイル等) |
| (c) | 著者写真(再利用を希望する場合は著者写真再利用申請書) |
この時提出頂いた編集用電子ファイルの形式により編集作業を進める. 掲載料はこの時の編集用電子ファイルの形式を基に決定するので,予めご了承頂きたい.
※万一,上記編集用電子ファイルに誤り(例:投稿原稿PDFと元ファイルのLaTeX または Word ファイルの不一致,等)があり,採録後の編集作業にやり直しが発生した場合,当該作業費に相当する費用を追加の掲載料として著者に請求することとなるため,原稿のバージョン管理を適切に行うこと.
著者変更は,原則として認めない.ただし,条件付採録となった原稿の修正過程において著者の増減や順序変更が必要になった場合には,修正原稿提出時に理由書の添付をもって申し出ることができる.著者変更を申し出る場合には,条件付採録に対する回答文中にもその旨を必ず明記するとともに,Copyright Transfer and Article Processing Charge Agreementを再作成し,事務局まで送付すること.送付方法は,スキャンしPDF化したものをメールの添付にて送付,ファックスによる送信,郵送による方法のいずれの手段でも構わない.編集委員会が理由書の内容を妥当と判断した場合には,これを認める.採録決定後の著者変更は認めない.
投稿の取下げは,編集委員会及び査読委員のボランタリーな貢献を無駄にするので,著者は投稿論文を取り下げるべきではない.しかし,やむをえない理由がある場合には取り下げることができる.投稿を取り下げる場合は,次の手順に従わなければならない.
1.著者は,論文採録通知の前に,以下の情報を記載した取下げ申請書を,スキャンしたPDFのメール添付,もしくはファックスにて事務局に提出しなければならない.
(a)受付番号
(b)論文題名
(c)全著者名
(d)取下げ理由
(e)全著者の署名(もしくは連絡著者の署名)及び日付
※ 連絡著者のみが署名をする場合は,全著者から取下げに関する了解を得て,その旨を取下げ申請書に記載しなければならない.
2.採録通知後は,原則として取下げが認められない.たとえ取下げが認められた場合でも,著者は掲載料を支払わなければならない.
3.取下げの諾否は当該論文誌の編集委員長が決定する.事務局は著者に諾否通知を送付する.諾否の通知が届かない場合は,著者は事務局に問い合わせなければならない.
4.投稿取下げの成立日は.許諾通知に記載した日付とする.
5.上記の手続きに従わない投稿の取り下げ申請は無効とする.
なお,剽窃あるいは二重投稿といった不正な投稿が発見された場合は,投稿の取下げは認められず,規定に基づき罰則を科せられる.
不採録と判定された論文を修正したもの,あるいは条件付採録の判定を受けながら自ら取り下げた論文を修正したものは再投稿できる.前回の査読結果が参照されることを希望する場合は,投稿時に前論文の受付番号を記入すること.
不採録となった原稿について,その判定に異議がある著者は,「異議申し立て」と題する書面をもって理由を明記し,編集委員会に再審を請求することができる.
再審請求は,書面によって提出されたもののみを受理する.提出期限は不採録判定通知の日付から60日以内とする.再審請求にあたっては,不採録となった原稿に対する修正・追加は認めない.
下記URLにて,投稿原稿の進捗状況が確認できる.掲載1か月前には掲載ページ番号も確認できるので利用されたい.
https://review.ieice.org/
|
(C) Copyright
2004-2010 IEICE.All rights reserved.
|